提供:株式会社リクルート
人手不足や業務効率化に悩む飲食店にとって、「モバイルオーダー」は有効な解決策として注目されています。スマートフォンを活用したこの注文システムは、回転率が速く注文数の多い「居酒屋業態」を中心に導入が進んでいる、スタッフの負担軽減やサービス品質の向上につながる仕組みです。
本記事では、モバイルオーダーの基本的なしくみや種類を紹介するとともに、特に居酒屋で導入する場合にフォーカスし、メリット・デメリットや導入の流れ、具体的な注意点をわかりやすく解説します。実際に利用したユーザーの声も紹介するため、導入すべきか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
目次
モバイルオーダーとは?
モバイルオーダーとは、自分のスマートフォンを使って飲食店などの商品やサービスを注文できるシステムのことです。店内や来店前に、Webサイトや専用アプリからメニューを選んで注文します。
注文後は店内で会計する形式が一般的ですが、決済機能が付属したサービスであれば、注文から支払いまで一貫して完結することも可能です。
従来の対面注文と異なり、お客様自身がスマートフォンで注文するセルフサービス型のしくみで、飲食店を中心に小売業やサービス業など幅広い業種で普及が進んでいます。
モバイルオーダーが普及した背景
モバイルオーダーの急速な普及には、さまざまな社会情勢や経済的な要素が影響しています。以下では、モバイルオーダーの普及に大きく関係している要因を3つ解説します。
人手不足の深刻化
飲食業界の人手不足の深刻化は、モバイルオーダー普及の重要な要因のひとつです。少子高齢化に伴う労働人口の減少とサービス業の厳しい労働環境により、人手不足問題が顕在化しています。
こうした状況下で、ホール従業員の接客や注文受付業務を効率化できるモバイルオーダーは、限られた人員で店舗運営を継続するための有効な解決策として注目を集めました。
モバイルオーダーの活用によって、一人の従業員でより多くのテーブルをカバーできるようになり、人件費削減と業務効率化の両面から経営者に支持されています。
非対面サービスへの抵抗感の薄れ
消費者側が非対面サービスに対する抵抗感が薄れてきたことも、モバイルオーダー普及の背景のひとつです。
近年、キャッシュレス決済の普及や、ECサイトでの購入・セルフレジの導入など、日常生活の中で「人と接しなくても完結できる」サービスの体験が、当たり前になりつつあります。
多くの方がスマートフォンを通じて予約や支払い、注文を行うことに慣れてきた結果、モバイルオーダーのような仕組みの受け入れもスムーズになりました。
特に、2019年の消費税増税に伴う「キャッシュレス・ポイント還元事業」は、こうした流れを強く後押ししたといえるでしょう。経済産業省の調査では、日本のキャッシュレス決済比率は2019年から2024年までの5年間で26.8%から42.8%まで上昇しています※。
※ 出典:経済産業省「2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました」
コロナ禍による非接触ニーズの高まり
2020年初頭から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、モバイルオーダーの普及に大きく関係しています。感染予防のための「非接触」「密回避」の政府要請は、従来の対面型サービスに大きな変革をもたらしました。
飲食店では人との接触機会を減らすため、メニューの共有・店員との会話・レジでの支払いなど、接触ポイントの削減が求められました。
この社会的要請に応える形で、店内での接触を最小限に抑える店内型モバイルオーダーや、テイクアウトやデリバリーを前提とした店外型モバイルオーダーの導入が急速に進みます。
当初は緊急対応として始まったものの、感染症対策だけでなく、利便性が高く人手不足問題の解消にもつながる点が評価され、コロナ収束後も注文方法のひとつとして根付いています。現在は、コロナ収束に伴い、主に人手不足対策の意味合いで定着が進んでいます。
モバイルオーダーの基本的なしくみ

モバイルオーダーの基本的なしくみは、「注文」「提供」「決済」の3ステップです。
まず、お客様はQRコードや専用アプリからメニュー画面にアクセスし、商品を選択して注文情報を送信します。注文データは店舗の伝票プリンターやオーダーディスプレイに転送され、従業員の確認後、調理から商品提供まで行われるのが一般的な流れです。
会計は従来通りレジで決済しますが、モバイルオーダーのなかにはオンライン上で決済まで完結できるサービスもあります。
モバイルオーダーの種類
モバイルオーダーは大きく分けて「店内版」と「店外版」の2つに分類されます。以下では、それぞれの特徴を解説します。
店内版
店内版モバイルオーダーは、店舗に来店したお客様がその場で利用するシステムです。近年、特に注目を集めており、既に多くの店舗で採用されています。
店内版モバイルオーダーでは、テーブルに設置されたQRコードをお客様が自分のスマートフォンで読み込み、席に座ったまま注文を行います。お客様は従業員を呼ぶ手間が省けるだけでなく、混雑時の待ち時間短縮にもなり、店舗側は接客の効率化・再注文率の向上などの効果が見込めます。
店外版
店外版モバイルオーダーは、来店前に注文を済ませておくシステムです。事前にWebサイトや専用アプリから注文し、指定した時間に商品を受け取るしくみで、テイクアウトやデリバリーでの注文に適しています。
お客様は待ち時間なく商品を受け取ることができ、店舗側は事前準備を行えるため、スムーズなオペレーションが可能となり、店内の混雑緩和にも効果的です。なお、店外版モバイルオーダーの多くは、注文時点で決済まで完了する機能が備わっています。
居酒屋でモバイルオーダーを導入するメリット

居酒屋でモバイルオーダーを導入する場合のメリットは、以下のとおりです。
| ・従業員の業務負担を軽減できる ・注文数や客単価の向上が期待できる ・インバウンド需要に対応できる |
それぞれ詳しく説明します。
従業員の業務負担を軽減できる
モバイルオーダーを導入すると、少ない人員でも効率的に店舗運営を実現できる点が大きな魅力です。お客様が自分で注文できるため、従業員による注文受けやキッチンへの伝達、場合によっては会計処理などの業務が削減されます。
特に繁忙時間帯の混雑緩和に効果的で、従業員はより質の高いサービスを提供できるようになることがメリットです。例えば、飲み放題のドリンク注文や小皿料理の追加など、注文頻度が高い居酒屋では、接客の手間を軽減しながらスムーズな提供につなげられます。
また、聞き間違いなどのヒューマンエラーも減らせるため、再調理の手間やクレームの発生なども防げます。
注文数や客単価の向上が期待できる
デジタル画面での視覚的なメニュー表示により、お客様は全商品を確認しやすくなります。「おすすめ商品」「人気ランキング」などの表示やセット提案機能を活用すれば、追加注文や高単価商品への誘導が可能です。
なお、食べ放題・飲み放題など居酒屋ならではのプランにおいても、お客様のタイミングで効率的に注文できるため、お客様満足度の向上はもちろん、回転率や注文総数のアップにもつながります。
また、お客様心理として、混雑時に従業員に声をかけづらいなどの遠慮や気まずさがなくなるため、注文のハードルも下がります。実際に多くのモバイルオーダー導入店舗で客単価の向上が実感されています※。
インバウンドへの対策ができる
モバイルオーダーのなかには、多言語に対応するものもあります。英語をはじめ、お客様が使用する言語に合わせてメニューが自動翻訳されるため、インバウンド需要への対応手段として活用が可能です。
特に居酒屋では、料理名や食材、提供スタイルなどが外国人にはわかりづらく、言葉の壁が来店や注文のハードルになることも少なくありません。たとえば、「だし巻き」「お通し」など、和食文化に特有の表現は、スタッフによるその都度の説明が必要になることもあります。
こうした説明負担や、メニュー表を多言語で都度印刷・作成するコストは、モバイルオーダーの導入によって大幅に軽減することができます。さらに、写真付きでメニューを表示できるシステムを選べば、視覚的にも伝わりやすく、外国人観光客にとっても安心して注文できる環境が整います。
居酒屋でモバイルオーダーを導入するデメリット
居酒屋がモバイルオーダーを導入する際のデメリットは、以下のとおりです。
| ・導入コストがかかる ・業務オペレーションの見直しが必要になる ・システム障害やトラブルのリスクがある |
それぞれ詳しく解説します。
導入コストがかかる
サービス提供会社によって料金体系は異なりますが、モバイルオーダーの導入時は初期費用として導入設定料や端末購入費などが必要です。また、月額のシステム利用料や決済手数料などのランニングコストも発生するため、費用負担は無視できません。
既存レジシステムとの連携で追加費用が発生することもありますが、期間限定の特典で各種費用がお得になるケースもあります。例えば、『Airレジ オーダー』では2025年7月現在、特典条件を達成して申し込むことで、機器セットの無償提供と月額費用1年間無料の特典が受けられます※1※2※3※4※5※6。
導入前後のサポートも充実しているため、モバイルオーダーの新規導入を考えている方におすすめです。
※1 「Airレジ オーダー モバイルオーダー 店内版+キッチンモニター」が対象となります。特典は数に限りがあり、予告なく変更・終了の可能性があります。今後も同様の特典を実施する場合があり、特典内容が変更になる可能性があります。
※2 特典の適用には条件があります。特典をお申込みの際は、公式サイトの特典条件・注意事項を必ずご確認ください。
※3 「Airレジ オーダー モバイルオーダー 店内版+キッチンモニター」の月額費用が1年間無料
※4 各機器は、店舗のご状況に応じて必要台数を当社にて決定の上、ご提供します。なお、台数には上限がございます。
※5 対象機器を無償で譲渡します。月額費用・決済手数料は別途かかります。特典条件・注意事項を必ずご確認ください。
※6 在庫状況により、iPadやiPhone SEの仕様、プリンターやキャッシュドロアのメーカーや仕様が変更となる場合がございます。プリンターとキャッシュドロアは一体型(レシートプリンター内蔵キャッシュドロア)となる場合もございますので、ご了承ください。
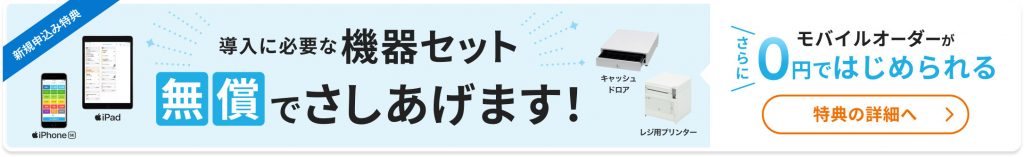
業務オペレーションの見直しが必要になる
モバイルオーダーの導入に伴い、店舗の業務オペレーション全体の見直しが求められます。従来の注文受付から調理、提供までの流れが変わるため、従業員の役割分担と新たな動線設計が必要です。
また、注文のタイミングが変わることで、キッチンへの負荷分散や調理における優先順位の判断基準も見直す必要があります。居酒屋は、特にドリンクや料理の追加注文が多いため、厨房やドリンクカウンターの対応体制も含めて見直すとよいでしょう。
なお、従業員全員がシステム操作に習熟するための教育時間や、移行期の二重業務による負担増加も考慮すべき点です。
そのため、導入するサービスは、導入時や運用後のサポート体制が充実しているものを選ぶと安心です。サポート体制が整ったサービスであれば、導入時の負担を軽減でき、スムーズな移行につながります。
システム障害やトラブルのリスクがある
モバイルオーダーはITシステムに依存するため、システム障害やネットワークトラブル発生時の影響が大きい点がデメリットです。サーバーダウン・通信障害・アプリのバグ・決済システムの不具合などが発生した場合、注文受付が完全に停止する可能性があります。
特に繁忙時間帯のシステム障害は、お客様の不満や機会損失に直結しかねません。そのため、紙の注文票を用意するなど、障害発生時の代替手段を準備しておくことが重要です。
なお、導入するシステムは、サポート体制が充実しているものを選ぶと万が一の場合でも安心です。『Airレジ オーダー』では、初期導入サポートや年中無休※のヘルプデスクが用意されており、初めての導入でも安心です。
※ 受付時間 9時30分~23時00分
居酒屋でモバイルオーダーを導入する際の流れ
居酒屋でモバイルオーダーを導入するまでの流れは、以下のとおりです。
| 1.利用サービスを選定し、契約手続きを行う 2.メニューを登録する 3.テーブルにQRコードを設置する 4.従業員とお客様への周知を図る |
以下では、計画から運用開始までのステップを詳しく解説します。
1 利用サービスを選定し、契約手続きを行う
まずは、自店に最適なサービスを選定します。料金体系・対応機能・操作性・サポート体制・必要機器などを比較検討することが大切です。
サービスの選定後、契約手続きを行います。導入にあたっては、ネットワーク環境とオーダー確認用のタブレット端末が必要なケースが一般的ですが、サービスによって専用プリンターや決済端末なども必要になります。
契約前に、契約内容や期間、解約要項について気になることはすべて確認しておきましょう。また、既存設備との互換性をチェックしておくことも重要です。
2 メニューを登録する
サービス契約後は、実際にメニュー情報の登録作業を行います。商品名・価格・商品画像・説明文・アレルギー情報などの基本情報に加え、カテゴリ分類やオプション設定(トッピングやサイズ変更など)も細かく設定しましょう。
メニューカスタマイズ時は、スマートフォン表示に適したメニュー構成や、写真映えする商品配置を意識することがポイントです。例えば、一品料理・揚げ物・〆(しめ)・ドリンクなど、ジャンルごとに分かりやすく分類しておくと、ユーザーが目的の商品に迷わずたどり着けます。
登録完了後は複数人で表示確認とテスト注文を実施し、間違いがないか確認しましょう。
3 テーブルにQRコードを設置する
次に、注文時に読み取るためのQRコードを店舗内の各テーブルに設置します。サイズやデザインを決めて印刷し、設置する際はポップスタンドなどに入れて設置するのがおすすめです。
特に居酒屋は、テーブルに調味料やお通し皿などが多く並ぶことがあるため、QRコードが隠れないような配置に工夫するとよいでしょう。
4 従業員とお客様への周知を図る
モバイルオーダーのスムーズな導入には、従業員とお客様双方への周知が不可欠です。
従業員には操作方法だけでなく、新しい業務フローや想定されるトラブル対応も含めた研修を実施します。注文確認方法や調理における優先順位の判断基準など、具体的な運用ルールを共有しましょう。
お客様に対しては、店頭ポスター・テーブル上の案内カード・SNSでの告知など複数の手段でモバイルオーダーの導入を周知します。飲み放題のオーダールールや、グループで利用する時の注意点など、居酒屋特有の案内がある場合は、併せて明記しておくと安心です。
導入後に見えてくる課題も多いため、運用しながら改善を重ねることが大切です。
居酒屋でモバイルオーダーを導入する際の注意点
モバイルオーダーを導入する際は、従業員全員が新システムを使いこなせるよう、十分な研修時間を確保しましょう。操作方法だけでなく、お客様からの質問対応やトラブルシューティングも含めたマニュアルを作成しておくと安心です。飲み放題の注文ルールや、お通しの案内方法など、業態特有の対応もマニュアルに盛り込んでおくとよいでしょう。
システム面では、Wi-Fi環境の安定性確保は欠かせません。電波の届きにくいエリアがないか事前に確認し、必要に応じてWi-Fi中継機を設置することをおすすめします。また、紙の注文票など代替手段を用意しておけば、システム障害時も業務への影響を最小限に抑えられます。
お客様観点での注意点として、初めて利用する方への配慮も大切です。QRコードの設置場所や案内表示を工夫し、操作に不安がある方などをサポートできる体制を整えておくとサービス満足度が向上します。
導入当初はお客様からのフィードバックを積極的に収集し、迅速な改善につなげることでさらに使いやすいシステムへと発展させられます。
【独自アンケート】実際に居酒屋でモバイルオーダーを使用した感想を紹介!
モバイルオーダーを導入する際に気になるのは、実際のお客様の声です。お客様が快適に利用できるオペレーションを組めるよう、リアルな意見を把握しておくことが大切です。
今回、居酒屋で実際にモバイルオーダーを利用したことがある方に向けて独自アンケートを実施しました。そこで回答のあった、ユーザーの声を紹介します。
<アンケート結果>
アンケートでは、「今後もモバイルオーダーを使いたい」という声が約7割に上った一方で、「登録や手続きが面倒」といった声が一定数あり、なかでも、複数人での利用シーンではさまざまな意見が寄せられました。以下は、「利用して良かった点」、「不便を感じた点」のTOP3です。
●利用して良かった点TOP3
| 1位:混雑時、従業員を待たずに注文ができた 2位:注文履歴や費用合計が見られて助かった 3位:注文内容を自分で確認できるのが良かった・注文内容をゆっくり選べた |
●不便を感じた点TOP3
| 1位:誰が何を注文したか把握しづらかった 2位:LINE登録が必須で面倒だった 3位:注文を共有できず、スマートフォンの回し合いが面倒だった |
アンケートでは「混雑時でもすぐ注文できる」「履歴や金額が見えて便利」など、スムーズな注文体験を評価する声が多く集まりました。
一方で、「誰が何を頼んだか分かりにくい」「LINE登録が面倒だった」など、グループ注文のしづらさや、注文に際する会員登録作業に不便を感じた人も多数いることがわかりました。
こうした傾向の背景には、実際のユーザーによる具体的な体験が反映されています。以下は、アンケートで集まった自由記述(コメント)の一部です。
自分のタイミングで注文できる
| ・「ガヤガヤしている店舗でも大きな声で店員さんを呼ばなくてよいのは助かります。大人数でもそれぞれが好きなタイミングで注文できるのも嬉しいです!」(20代・女性) ・「店員さんとの距離が離れている席は何度呼んでも気づいてもらえないことがあり、テンションが下がってしまうが、モバイルオーダーでは自分で注文できるため、その場の雰囲気が盛り下がってしまうことがなく、飲み会とかでもとてもありがたい」(20代・女性) |
LINE登録が面倒だった
| ・「LINEなどのアカウント登録はしたくないなと感じました」(20代・男性) ・「LINE登録が必要で面倒だった。その後LINEでお知らせやクーポンが届くようになったが、頻繁に利用する店ではないのでほぼ見ていない」(30代・女性) ・「LINE登録必須だと、その後の案内が不要な場合に都度解除が面倒だと感じる」(20代・男性) |
注文方法で手間取った
| ・「注文のたびにQRコードを読み込まないといけないタイプと、一度読み込めばいいものがあるが一度で済む方が、面倒が省けて嬉しい」(30代・女性) ・「リアルなメニューをみながらスマホから選択する機会が多いが、リアルとスマホでメニュー名やカテゴリが微妙に違うときは注文したいものを探し出すのに少々苦労する」(30代・女性) ・「売り切れが未反映で、料理は来ないのに注文したことになっていた」(30代・女性) ・「メニューが多いお店だと目当ての料理の表示を探すのに時間がかかった」(20代・女性) ・「後ろの席にいた高齢のグループは、スマホ操作がわからず、店員さんにメニュー表をもらっていました」(40代・女性) |
その他
| ・「スマホのバッテリー残量が気になるので、コンセントなど充電設備があるとうれしい」(40代・女性) |
ユーザーの声からは、モバイルオーダーの利便性と同時に、細かな導入面や利用環境における課題も浮かび上がりました。モバイルオーダーシステムを導入する際は、上記の課題を解決できるシステムの選定や、オペレーションの構築が重要です。
例えば、『Airレジ オーダー』では、LINE登録なしで利用できる他、メニュー画面も直感的に操作しやすい設計になっています。また、高齢のお客様などスマートフォンからの注文に抵抗感がある方には、ハンディを併用し、従業員が直接注文を受ける運用も可能です。
その他、注文履歴の共有など、グループでの注文にも柔軟に対応できます。そのため、自店に適した設計でモバイルオーダーを導入できる点が魅力です。
このように、単に「導入すること」が目的ではなく、「実際の運用シーンにフィットするか」「不安点を解消できるかどうか」を見定めることが、顧客満足度の向上とスタッフの負担軽減の両立につながります。
モバイルオーダー導入を検討するなら『Airレジ オーダー』がおすすめ
-1.jpg)
モバイルオーダーの導入を検討している方には、『Airレジ オーダー』がおすすめです。
『Airレジ オーダー』の注文画面は、「誰でも使いやすくわかりやすい」ことを意識した仕様で、難しい操作は必要なく、簡単に注文できます。独自アンケートで挙がっていた「LINE登録」も不要です。
また、「モバイルオーダー店内版」と「ハンディ」の注文方法を組み合わせられるため、デジタル操作が苦手なお客様には、従業員がハンディから注文対応するなど、お客様に合わせたサービス提供が可能です。
自動翻訳機能にも対応しており、お客さまのスマートフォンのブラウザ翻訳機能を活用すれば、外国人のお客様でも快適に注文できます。飲み放題・食べ放題メニューにも対応し、提供遅れを知らせるアラート機能も備わっているため、クレーム防止にも効果的です。
料金プランは初期費用無料・月額17,600円からが基本で、キッチンプリンターなどと連携可能なプランも用意されています。なお、2025年7月現在、特典条件を達成すると「導入費用・初期費用・月額費用1年分が無料」になるお得な特典が適用されます。さらに、見積もりや契約までにかかる費用も0円です※1※2※3※4※5※6。
特典を利用する場合は『Airレジ オーダー』の公式サイトで、対象プランや適用条件などの詳細を必ずご確認ください。お得な特典を活用して、『Airレジ オーダー』のモバイルオーダーシステムをぜひ体験してみてはいかがでしょうか。https://airregi.jp/order/campaign/initial_cost/?vos=otahdxototzzx00000277
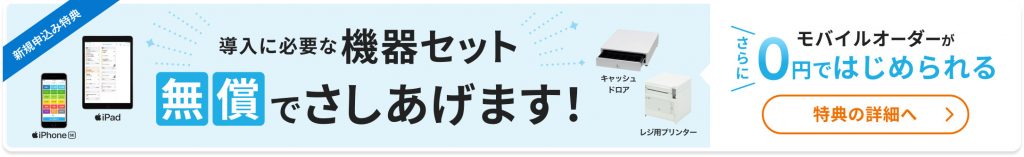
さらに、経営サポートサービス『Airメイト』と連携すれば売上分析も可能で、店舗の経営改善に活用できます。年中無休のヘルプデスクも完備されているため、急な不具合や導入したばかりで使い方がわからないときでも安心です。
※1 「Airレジ オーダー モバイルオーダー 店内版+キッチンモニター」が対象となります。特典は数に限りがあり、予告なく変更・終了の可能性があります。今後も同様の特典を実施する場合があり、特典内容が変更になる可能性があります。
※2 特典の適用には条件があります。特典をお申込みの際は、公式サイトの 特典条件・注意事項を必ずご確認ください。
※3 「Airレジ オーダー モバイルオーダー 店内版+キッチンモニター」の月額費用が1年間無料
※4 各機器は、店舗のご状況に応じて必要台数を当社にて決定の上、ご提供します。なお、台数には上限がございます。
※5 対象機器を無償で譲渡します。月額費用・決済手数料は別途かかります。特典条件・注意事項を必ずご確認ください。
※6 在庫状況により、iPadやiPhone SEの仕様、プリンターやキャッシュドロアのメーカーや仕様が変更となる場合がございます。プリンターとキャッシュドロアは一体型(レシートプリンター内蔵キャッシュドロア)となる場合もございますので、ご了承ください。
居酒屋で『Airレジ オーダー』を導入した事例
最後に、『Airレジ オーダー』を導入した店舗の事例を紹介します。
東京都・大井町にある「酒肴あおもん」は、新鮮な魚料理で人気を集める居酒屋です。
オーナーは、コロナ禍で焼肉店に勤務していた経験から、人手不足が続く中でも“お客様満足度を下げないための工夫”を求めており、『Airレジ オーダー』を導入しました。
『Airレジ オーダー』の導入によって、従業員が注文に付きっきりにならずに済むため、料理の魅力をしっかり伝える時間が取れるようになり、結果的に、「もっと話したくなる」「聞いてみたくなる」空気が生まれて接客の質も向上しました。
また、注文の時間が短縮されたことにより、注文回数や客単価が向上にもつながりました。さらに、少人数体制でも店舗全体がスムーズにまわるようになったことで、人件費率はおよそ10ポイント削減されました。
このように、『Airレジ オーダー』は、売上向上だけでなく、従業員の負担軽減やお客様との接点向上という多方面で効果を生み出します。
まとめ
モバイルオーダーはスマートフォンを活用した注文システムで、人手不足問題の解消や業務効率化に貢献します。種類は「店内版」と「店外版」があり、利便性の高さから「店内版」は特に普及が進んでいます。
居酒屋でモバイルオーダーを導入するメリットとして、業務負担軽減・客単価向上・データを活用した集客効果などが期待できる一方、導入コスト・システムトラブルなどのデメリットも考慮すべきです。本記事で紹介したような対策も、併せて準備しておくと安心でしょう。
導入を検討する際は、自店の課題に適したサービスを選定し、従業員やお客様へ丁寧な周知を行うことが大切です。『Airレジ オーダー』など、使いやすさと充実したサポート体制を兼ね備えたサービスを選ぶことで、スムーズな導入と運用が可能になります。

本記事は、2025年5月に実施したアンケートで得られた実際のコメント・回答内容をもとに構成しています。調査では、居酒屋でモバイルオーダーを利用した経験がある35人を対象に、使い勝手や満足度、導入時の課題などについて自由記述を含む形式で意見を収集しました。
提供:株式会社リクルート
本記事は、株式会社リクルートの提供により、同社サービス『Airレジ オーダー』に関する情報を取材・編集し掲載しています。


























