十五夜とは、旧暦8月15日に行われる「中秋の名月」を愛でる風習で、日本では古くから豊作祈願や、感謝の意味を込めてお月見が行われてきました。
その起源は、中国から伝わった月餅の風習にあり、日本では稲作文化と結びつき、里芋や団子などを供える独自の形に発展していったのです。
今回は、十五夜の由来とは?お月見にちなんだ料理について紹介していきます。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
十五夜の由来とは?

十五夜とは、旧暦8月15日の夜に月を鑑賞し、豊作や収穫に感謝する行事を指します。
現代の暦では、9月中旬から10月上旬にあたり、この時期は空気が澄み、月がもっとも美しく見えるとされることから「中秋の名月」と呼ばれてきました。
十五夜の起源は、古代中国にあります。中国では、唐の時代から「中秋節」として月を鑑賞し、月餅などを供えて祝う習慣がありました。
この文化が平安時代に日本へ伝わり、貴族たちの間で舟を浮かべて月を眺める「観月の宴」として楽しまれるようになりました。
やがて、月見の風習は庶民へと広がり、日本独自の農耕文化と結びつきます。
日本では、古来より稲作が生活の中心にあり、秋は収穫の季節です。そのため、十五夜は、単なる月の鑑賞だけではなく、五穀豊穣を祈る祭りとして根付きました。
特に、里芋やサツマイモを収穫する時期と重なることから、十五夜は「芋名月」とも呼ばれ、収穫した芋を月に供える習慣が生まれました。
また、米の粉で作った団子を供えるのも、稲作文化に由来するものです。
このように、十五夜は中国の月見文化を取り入れつつ、日本独自の農耕信仰と融合した行事として発展しました。
今日でも、すすきを飾り、月見団子や里芋を供えて月を眺める風習が受け継がれており、古来から人々が自然に感謝し、季節の恵みを大切にしてきた心を伝えています。
十五夜と食文化の関係性とは?
十五夜は、月を愛でるだけでなく、食文化と深く結びついた行事です。その背景には、農耕を中心とした日本の暮らしと、収穫への感謝の気持ちが強く反映されています。
十五夜は、「中秋の名月」と呼ばれ、秋の収穫期にあたることから、食べ物を供えたり分かち合ったりする習慣が生まれました。
まず、代表的なのが「月見団子」です。白い団子を丸めて積み上げるのは、月を模したものであり、清らかさや豊穣を願う意味があります。
団子を15個並べるのは、十五夜にちなんだもので、地域によっては12個(1年の満月の数)や十三夜に合わせた数を供える場合もあります。
団子は、収穫した米の粉で作られるため、稲作文化と直結した食べ物です。
また、「里芋」を供える風習もあり、十五夜が「芋名月」と呼ばれる由来となっています。
収穫されたばかりの里芋を蒸したり煮たりして供えるのは、自然の恵みに感謝する意味を持ちます。
さらに、栗や枝豆を供える地域もあり、旬の食材を取り入れることで、行事食はより豊かになっていきました。
一方で、観月を楽しむ貴族文化の影響から、酒や肴を用意して宴を開く習慣もありました。
そこから発展して「月見そば」や「月見うどん」といった料理が生まれ、卵黄を月に見立てる発想が庶民の食卓に広まったのです。
このように十五夜は、月を象徴する団子や、季節の収穫物を用いた料理を通じて、日本の食文化と強く結びついてきました。
月を眺めることと、食べ物を分かち合うことが一体となり、自然への感謝や家族・地域の絆を深める大切な行事として現代に受け継がれているのです。
お月見にちなんだ料理5選!

十五夜は、ただ月を眺めるだけでなく、季節の食材や縁起のよい料理を楽しむ日でもあります。
お供え物として用いられる食べ物はもちろん、現代では家庭でアレンジして楽しめる料理も人気です。
ここでは、お月見に欠かせない代表的な料理について紹介していきます。
主に以下の料理があげられます。
月見団子
お月見といえば、やはり月見団子が主役です。白く丸い団子は満月を表し、豊穣や健康を祈る意味があります。
一般的には、米粉を練って蒸した団子を15個積み上げ、月に供えたあとに家族で食べます。
地域によっては、あんこを絡めたり、きな粉をまぶしたりなど味付けも多彩で、行事をより身近に楽しめるでしょう。
里芋料理(芋煮・煮っころがしなど)
十五夜は、「芋名月」とも呼ばれ、里芋を供える習慣があります。蒸してそのまま味わうほか、煮物にして月に供えるのが一般的です。
東北地方では、秋の風物詩として「芋煮会」が開かれるなど、芋を囲んで季節を楽しむ文化が根付いています。
「ホクホク」した里芋の味わいは、まさに収穫の恵みを実感させてくれます。
栗ご飯
秋の味覚の代表である栗も、十五夜に欠かせない食材です。栗は、「勝ち栗」と呼ばれ、縁起のよい食べ物として古くから親しまれてきました。
炊き込みご飯にすれば、香ばしい栗の甘みと「もちもち」したご飯が調和し、お祝いの食卓にぴったりです。
里芋と並んで「栗名月」と呼ばれる十三夜と関連づけられることもあります。
月見そば・月見うどん
卵黄を月に見立てた「月見そば」や「月見うどん」は、十五夜を象徴する料理のひとつです。
温かい出汁の中に浮かぶ卵はまるで夜空に輝く月のようで、見た目も美しく、気軽に楽しめるお月見料理として人気です。
現代では、月見バーガーや月見ピザなど、アレンジメニューも豊富に登場しています。
枝豆・旬の豆料理
秋に収穫を迎える枝豆も、お月見のお供え物として親しまれています。枝豆は、豊作祈願の象徴であり、塩ゆでして月を眺めながら味わうと、素朴ながらも季節の風情を感じられます。
大豆を使った豆腐料理や煮豆なども、十五夜の食卓にふさわしい一品です。
十五夜の料理は、ただおいしいだけでなく「月に見立てる」「収穫を祝う」「縁起を担ぐ」といった意味が込められています。
こうした料理を囲みながら月を眺めることで、自然の恵みに感謝し、古来から続くお月見の心を現代の食卓でも楽しむことができるのです。
飲食店で使う調理器具や食器
テンポスで扱っている、飲食店で使う調理器具や、おすすめの食器をご紹介!
のぼり 「月見だんご」
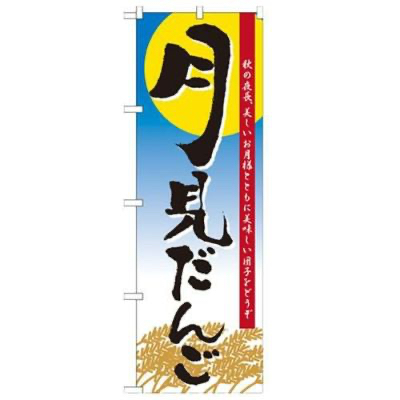
白粉引 六兵衛飯碗 小

まとめ
今回は、十五夜の由来とは?お月見にちなんだ料理について紹介してきました。
十五夜とは、旧暦8月15日の夜に月を鑑賞し、豊作や収穫に感謝する行事です。
現代の暦では、9月中旬から10月上旬にあたり、この時期は空気が澄み、月がもっとも美しく見えると言われています。
月見団子や里芋料理など、季節の食材や縁起のよい料理をぜひ楽しんでください。
#十五夜 #お月見 #縁起
テンポスドットコムでは、様々な視点から飲食店の開業成功を全力で応援します。
自分のお店の業態に合わせて必要なものは何があるのか、詳細を確認することができますので是非ご覧ください!

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。



























