飲食店を始めたいけれど、「テナントを借りるのはハードルが高い」「開業費用をなるべく抑えたい」と悩んでいませんか?そんな方に近年注目されているのが、“自宅での飲食店開業”です。
一見ハードルが低く見えるこのスタイルですが、実際にはさまざまな準備やルールを守る必要があります。
本記事では、自宅を使った飲食店開業のメリットや準備、費用・収益の目安、そして自宅営業ならではの働き方まで、わかりやすく解説します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
自宅開業はこんな人におすすめ!
まず、自宅での飲食店開業がどんな方に向いているのかを整理しておきましょう。
◦初期費用を抑えて始めたい
◦小さな規模で自分のペースで営業したい
◦育児や介護と両立できる働き方をしたい
◦地元や知り合いを対象に営業したい
◦趣味の延長で事業として収益化したい
特に、飲食業に興味があるけれど「店舗を構えるのは不安」「いきなり大きな借金をしたくない」という方にとって、自宅開業は非常に現実的な第一歩となります。
メリットとデメリットを比較

【メリット】
(1)開業コストが安い
テナント賃料や敷金・礼金が不要なので、開業費を大きく抑えられます。
(2)通勤不要、生活と両立しやすい
家庭と仕事の境目が近く、家事や子育てと両立できます。
(3)自分らしい店舗づくりができる
インテリアやメニュー、営業時間まで自分のスタイルを反映できます。
また、自宅ならではの温かみや個性を活かした店づくりができます。
(4)スモールスタートが可能
無理のない規模で始めて、経験を積みながら成長できます。
営業時間や営業日を自由に設定でき、マイペースで運営が可能です。
【デメリット】
(1)法規制・許認可がある
保健所の基準を満たさないと営業許可が下りない場合もあります。
家庭用キッチンでは営業できないこともあります。
(2)地域によって営業不可のケースも
用途地域によっては、住居用建物での営業が禁止されていたり商業活動が制限されていたりすることがあります。
(3)近隣トラブルのリスク
騒音やにおい、駐車場の使用でトラブルになることもあるため注意が必要です。
(4)設備改修に費用がかかることもある
飲食営業に必要な設備基準を満たすために、キッチンの改装が必要になる場合もあります。
関連記事:自宅でケーキ屋を開業!メリット・デメリットと注意点を解説!
自宅飲食店にかかる費用の目安

自宅での飲食店開業は、費用を抑えられる点が魅力ですが、それでも一定の設備投資や申請費用が必要です。
費用は営業スタイルや設備状況によって大きく変わりますが、以下は一般的な例です。
◦調理場の改修(手洗い場や作業台の増設など):20万~100万円
◦調理器具・備品(業務用冷蔵庫、作業台、什器など):10万~30万円
◦保健所への申請費(地域により異なる):数千円~2万円
◦衛生責任者講習費(1日の講習で取得可):約1万円
◦消耗品購入費(包装材・衛生用品など):数千円~月1万円
◦チラシ・メニュー制作(プリンターがあれば安価に可能):数千円~3万円
◦ネット広告費用(Instagram・LINE公式などSNS・Googleマップ登録):無料〜数万円
合計:30万円〜150万円程度が一般的な範囲ですが、既存の設備を活用すればさらに費用を抑えることも可能です。
想定される収益のモデルケース
ケース①:テイクアウト弁当販売
◦価格:700円/個
◦1日販売数:30個
◦営業日数:月20日
◦月商:約42万円
◦原価率:35% → 原価:約14.7万円
◦光熱費・包材費・雑費:約3万円
月利益:24万円程度
ケース②:週末限定カフェ(1日5組)
◦単価:1,500円(ドリンク+軽食)
◦1日:5組 × 2人 → 15,000円/日
◦月営業日:8日 → 月商12万円
原価・雑費差し引き → 月利益:約6〜8万円
大規模な利益は難しくても、「生活費の一部を補う」「子どもの学費に充てる」「将来の夢の土台を築く」といった目的には十分な収益が期待できます。
自宅でできる飲食ビジネス例
自宅を活用した飲食店といっても、スタイルはさまざまです。
無理に大規模な店舗を目指すのではなく、自宅だからこそできる「小さなビジネス」から始めるのが成功の秘訣です。
テイクアウト専門店
玄関先やガレージなどを販売スペースにして、簡単な弁当やお惣菜を販売。
玄関先で商品を渡す形なら、店内を整える必要がなく比較的始めやすい利点があります。
菓子・パン販売
菓子・パン業態は、固定ファンがつきやすいのが特徴です。
焼き菓子や手づくりパンを製造し、ECサイトやSNSを活用してテイクアウトや通販で販売するのがよいでしょう。
※「菓子製造業許可」が必要になる場合があります。
関連記事:パン屋を開業するなら自宅で始めよう!資金や注意点を解説
カフェ営業
来客対応のスペースが必要になりますが、個人の雰囲気を生かした店づくりが可能です。
1日数組限定でランチやカフェを提供したり、週末限定カフェとして予約制で1日3〜5組だけ対応したりすることで無理なく営業できます。
お弁当販売・デリバリー販売
オフィス街や住宅地で高い需要があります。オフィス街ではビジネスパーソン、住宅地では働く主婦層や高齢者にニーズがあります。
配達すれば来店スペースが不要で始めやすいです。
出張料理・ケータリング
自宅キッチンを拠点に外で提供します。
自宅だからこそ、小回りがきき、ニッチな需要に応えることができます。
料理教室との併用
料理の提供とともに「教える」ことも収入になります。自宅だからこそ実現可能な組み合わせです。
自宅で飲食店を始める5つのステップ
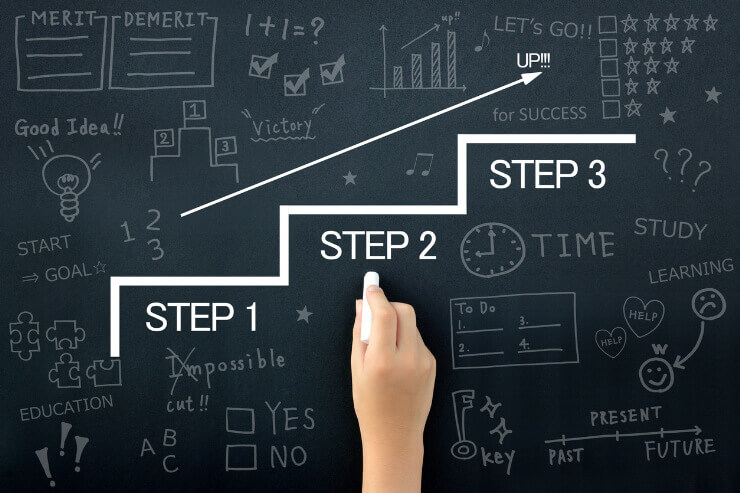
Step1:コンセプトを明確にする
「何を」「誰に」「どう提供するか」を整理して、「どんなお店にしたいか」を明確にします。
提供する料理や営業時間など、自分の生活スタイルや地域のニーズに合った形を考えることが大切です。
例えば、
◦高齢者向けの健康弁当
◦子連れOKの週末ランチカフェ
◦無添加スイーツのテイクアウト
など
Step2:自宅の設備を確認する
飲食店として営業するためには、調理場や洗い場などが一定の基準を満たしている必要があります。例えば、調理スペースと家庭用キッチンを分けることが求められる場合もあります。また、換気設備や手洗い場の設置も必要になることがあります。
【要チェック1:保健所に相談する】
自宅の構造で営業可能かどうかを、まず地元の保健所に相談しましょう。間取りや設備図を見せてアドバイスを受けるのがベストです。
【要チェック2:地域の用途地域確認(自治体)】
住んでいる場所が「営業可能な地域」かどうか、都市計画の「用途地域」も確認が必要です。住宅地によっては、そもそも飲食店の営業が禁止されている場合があります。
Step3:必要な改修を行う
保健所の許可を受けるためには、厨房の構造や設備が基準を満たしていなければなりません。
例えば、調理スペースと家庭スペースの分離、手洗い専用のシンク、ゴミの保管場所の確保などが求められます。場合によっては、リフォームが必要になることもあるでしょう。
例:
◦家庭キッチンと営業スペースの分離
◦手洗い場の設置
◦食材の保管場所の確保
◦ゴミの衛生的な処理スペースの確保
◦十分な換気設備
など
飲食店に必要なもの物がなんでも揃う!【新品】も【中古】もお任せください!
Step4:営業許可・資格を取得
【必須】飲食店営業許可(保健所)
営業開始前に保健所へ申請し、施設が基準に適合しているかの確認・検査を受ける必要があります。
【必須】食品衛生責任者
営業施設ごとに1名以上の配置が義務付けられています。調理師や栄養士などの資格がない方は、都道府県が実施する1日の講習(受講料1万円前後)を受けることで取得できます。
【必須】開業届(税務署)
開業から1ヶ月以内に税務署へ提出します。これを提出することで個人事業主として認定され、青色申告などの税制メリットが利用可能になります。
【条件付き】防火管理者選任届
飲食スペースの収容人員が30人以上になる場合や、建物の規模・用途によっては、消防署への届け出と防火管理者の選任が必要です。自宅営業では該当しないことが多いですが、事前確認を推奨します。
【必要な場合】菓子製造業許可
焼き菓子やパンを販売する場合は「菓子製造業許可」も必要になります。併用不可な地域もあるため、必ず保健所に確認しましょう。
その他、取り扱うメニューによって必要となる営業許可もありますので、事前に保健所に相談してください。
Step5:営業スタートの準備
どれだけ美味しい料理を作っても、お客さんに知ってもらえなければ意味がありません。
SNSを活用した情報発信や、Googleマップへの登録、近所へのチラシ配りなど、小規模でもできる集客手段を活用しましょう。
開業前にプレオープンをして、友人や家族にフィードバックをもらうのもおすすめです。
自宅営業の働き方と休み方
自宅での営業は自由度が高い反面、「いつでも働けてしまう」という落とし穴もあります。長く続けるためには、「働きすぎない工夫」も大切です。
【上手な働き方のコツ】
●営業時間は無理のない範囲で
1日3〜4時間だけ営業する、週に2日だけ営業するなど、長く続けるには「自分に合った働き方」が大切です。
●定休日をしっかり設定
「日曜と水曜は必ず休み」など、自分と家族の時間も大切にできるよう、あらかじめスケジュールを決めておくことが重要です。
●予約制にしてコントロール
来客の数をコントロールできれば、調理の無駄も減り、精神的にも楽になります。
●家族の協力もカギ
一人でやるには限界があります。家族に理解・協力してもらうことで、トラブルやストレスを回避しやすくなります。
●繁忙期を見越した準備
母の日、年末年始など繁忙期は早めに準備と告知をしましょう。
関連記事:自宅でパン屋を開業する方法:失敗しないための10のポイントと必要な厨房機器の選び方
よくある質問(Q&A)
Q. 家庭用キッチンでは営業できないの?
A. 原則として、家庭用と営業用のキッチンは区分されている必要があります。保健所の指導に従って、調理スペースの改修を行うケースが多いです。
Q. マンションや賃貸でも開業できる?
A. 管理規約や大家の許可が必要です。また、建物の用途地域や消防法にも注意が必要です。
Q. ネット販売だけでも許可が必要?
A. 菓子やパンなどの製造販売には「菓子製造業許可」が必要です。発送を行う場合も、製造設備の基準を満たさなければなりません。
まとめ
自宅で飲食店を開業するという選択肢は、初期費用を抑えつつ、自分のライフスタイルに合った働き方ができる魅力的なスタイルです。ただし、法的な許可や衛生基準など守るべきルールも多いため、しっかりとした準備が必要です。
コツコツと準備を進め、自分らしいお店を自宅から始めてみませんか?まずは一歩踏み出すことで、理想の働き方やビジネスが見えてくるはずです。
#飲食店開業 #飲食店自宅 #自宅で飲食店開業 #自宅飲食店 #自宅開業 #開業までの流れ #自宅開業費用 #小さく始める飲食店 #一人でできる飲食店


























