カフェや飲食店を開業する日って、ワクワクと同時に不安も大きいものです。
「いよいよオープン!」と思ったら、実はまだ準備不足だった……なんてことは避けたいですよね。
今回は、開業直前の準備とPR、そしてオープン後の経営管理の基本について、先輩と後輩の会話形式で紹介していきます。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
内装・家具・食器の最終調整 ― 開業直前の“抜け漏れ”チェック

座り心地と動線を確認しよう
後輩:「内装って、一度完成したらもう安心じゃないんですか?」
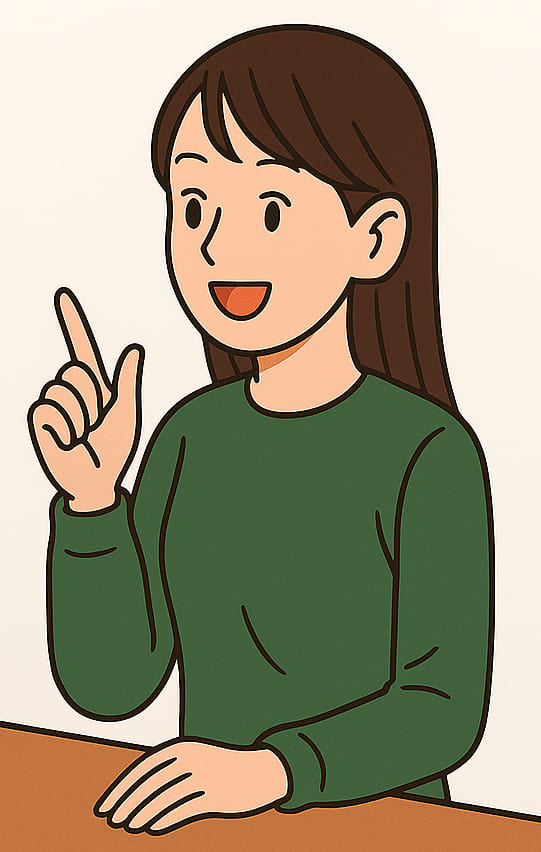
先輩:「そう思いがちだけど、実は“完成=ゴール”じゃないんだよ。たとえば椅子の高さ。テーブルと合わなくて座りにくいと、お客さんは食事どころじゃなくなる。」

後輩:「たしかに、自分が客として行ったら気になりますね。」
先輩:「あと、スタッフが料理を運ぶ動線も要チェック。テーブルの間が狭いとトレーを持って通れない、とかね。実際に歩いてみるのが一番だよ。」
照明やBGMも“体験の一部”
後輩:「家具は確認するとして、他に見落としやすいのってありますか?」
先輩:「照明の明るさやBGMの音量だね。昼と夜で雰囲気が変わるから、時間帯を分けて確認しておくといい。」
後輩:「あ、それは気づかなかったです!」
先輩:「居心地の良さは“ちょっとした快適さ”で決まる。照明が暗すぎると料理が美味しそうに見えないし、音楽が大きすぎると会話がしにくい。お客さん目線で体験してみることが大事なんだ。」
食器は“必要数+予備”を
後輩:「食器は揃えてあるので大丈夫だと思います!」
先輩:「ほんとに? 初日のランチで思ったよりお客さんが来て、皿が足りなくなるってパターンは多いよ。」
後輩:「えっ、そんなこともあるんですか?」
先輩:「あるある。特に人気が出やすいメニュー用のお皿は、余分に用意しておくと安心。グラスやカップも“洗浄が追いつかないとき”のために予備が必要だね。」
実際に使ってみるテストが大事
後輩:「なるほど……結構細かいチェックが必要なんですね。」
先輩:「そう。だからオープン前に、実際にスタッフや友人に座ってもらって料理を出す“テスト営業”をやるといい。そこで気づいた違和感を直すのが、最後の仕上げになるんだ。」
後輩:「オープン前にそこまでやるのかぁ。でもやった方が絶対安心ですね。」
先輩:「準備の段階で直せるミスは直しておく。これが“当日のバタバタを減らすコツ”なんだよ。」
宣伝・SNS活用方法 ― お店を知ってもらう仕掛けづくり

なぜSNSが大事なの?
後輩:「先輩、宣伝ってやっぱりチラシとかポスティングですか?」
先輩:「昔はそうだったけど、今はSNSが主流だね。無料で始められるし、写真や動画で“お店の雰囲気”を伝えられるのが強い。」
後輩:「確かに、自分もお店探すときはSNSで検索します!」
先輩:「そうだろ? だからオープン前から発信して“期待感”を高めておくのが大事なんだ。」
カウントダウン投稿でワクワク感を演出
後輩:「具体的にはどんな投稿をすればいいですか?」
先輩:「おすすめは“開業日までのカウントダウン”。『あと7日!今日は試作メニューのチェック中』とか、『あと3日!店内の仕上げをやってます』みたいに。」
後輩:「なるほど、日記っぽくて読みやすいですね!」
先輩:「そうそう。フォロワーが一緒に開業を待ってくれるから、初日に来店してくれる可能性も高まるんだよ。」
写真と動画の使い分け
後輩:「写真と動画って、どっちを使えばいいんですか?」
先輩:「両方使うのがベストだね。例えば料理の仕込みやラテアートは動画の方が臨場感が出る。一方で、完成した料理や内装は写真で“おしゃれさ”を切り取る。」
後輩:「確かに、動画だと雰囲気が伝わりやすいです。」
先輩:「スマホで十分だから、気負わずに撮ってみるといいよ。」
ハッシュタグは“地域密着”がカギ
後輩:「ハッシュタグって、どんなのをつければいいんですか?」
先輩:「大事なのは“場所”を入れること。例えば『#渋谷カフェ』『#〇〇駅ランチ』みたいにね。地域の人が検索したときにヒットしやすくなるんだ。」
後輩:「あぁ、それなら近所の人が見つけやすい!」
先輩:「そうそう。流行りのタグより、地元向けのタグが一番効果的なんだ。」
フォロワーとつながる工夫
後輩:「投稿するだけでいいんですか?」
先輩:「投稿だけじゃなくて“やり取り”も大事。コメントが来たら返信するし、いいねをくれた人の投稿を覗いてみるのもいい。」
後輩:「ちょっと面倒そうですけど、やっぱりやった方がいいんですね。」
先輩:「お店は“人”で覚えられるものだからね。フォロワーとの距離感が近いほど、実際に来てくれる確率が高くなるんだよ。」
オープン当日の告知も忘れずに
後輩:「オープン当日ってSNSでどうすればいいですか?」
先輩:「朝一番で『本日オープンです!』って投稿すること。さらに、最初のお客さんや料理の写真をその日のうちにアップすると“リアル感”が出て、後から見た人も行きたくなるんだ。」
後輩:「それなら無料でできるし、すぐ実行できますね!」
先輩:「そう。SNSは“お金をかけない宣伝”。初心者でもすぐ始められる最強ツールだよ。」
プレオープン・試運転の重要性 ― 本番前のリハーサル

プレオープンって必要?
後輩:「先輩、正直に言うと…プレオープンってやらなくてもいいんじゃないですか?お金も時間もかかりますし。」
先輩:「そう思う人は多いけど、プレオープンは“リハーサル”みたいなものなんだ。舞台もリハーサルなしで本番に出たら大事故になるだろ?」
後輩:「あぁ…確かに料理も接客も、本番ぶっつけは怖いですね。」
小さなミスに気づける場
後輩:「でも、そんなに大きな違いが出るんですか?」
先輩:「出る出る。例えば、提供に時間がかかりすぎて料理が冷めたとか、注文をメモする場所がわかりにくいとか。こういう“小さなミス”って、実際にやってみないと気づけないんだよ。」
後輩:「なるほど…机上の計画だけじゃわからないんですね。」
お客さん目線のリアルな感想
後輩:「プレオープンのお客さんは、知り合いを呼ぶ感じですか?」
先輩:「そう。家族や友人、応援してくれる知人を呼ぶといい。身近な人なら遠慮なく意見を言ってくれるからね。」
後輩:「おぉ、リアルな感想が聞けそう!」
先輩:「例えば“椅子が硬い”“メニューが見にくい”なんて指摘も、本番前ならすぐ直せる。これが大きな武器になるんだ。」
スタッフの動きも確認できる
後輩:「自分一人でやるならともかく、スタッフを雇う場合はどうですか?」
先輩:「プレオープンは特に必須だね。スタッフ同士の連携、オーダーから提供までの流れ…全部試せる。混乱しそうなところは、ここで改善しておけるんだ。」
後輩:「本番でバタバタしてたら、お客さんに悪いですもんね。」
先輩:「そう。スタッフにとっても安心材料になるんだよ。」
プレオープンをどうやってやる?
後輩:「でも、プレオープンって無料でやるんですか?それとも料金を取るんですか?」
先輩:「やり方は2つ。①完全無料にして率直な意見をもらう、②通常より安い価格で提供して“お試し営業”にする。どっちにしても“本番じゃない”ことを伝えて、感想をもらうのが目的だよ。」
後輩:「なるほど!単なるお披露目じゃなくて、改善のためなんですね。」
プレオープンは、
・小さなミスに気づける
・お客さんのリアルな声が聞ける
・スタッフの動きを確認できる
というメリットがあります。
時間もコストもかかりますが、グランドオープンで失敗するよりはずっとお得。
プレオープンを“保険”として取り入れることが、成功への近道です。
開業後の経営管理 ― 毎日の数字が未来をつくる
経営管理って具体的に何をする?
後輩:「先輩、オープンしてからが本番だってよく言いますけど…“経営管理”って具体的に何をすればいいんですか?」
先輩:「簡単に言うと、毎日の売上と在庫をちゃんと把握することだね。それができないと“勘”だけで経営してしまって、気づいたら赤字…なんてことになりやすい。」
後輩:「うっ…自分は数字に弱いから心配です。」
先輩:「だからこそ、シンプルにやればいい。難しい経理の知識は最初はいらないよ。」
売上管理は“毎日つける”が鉄則
後輩:「売上はレジに記録が残るから、そこまで気にしなくてもいいですよね?」
先輩:「それが落とし穴。レジに入った金額を“ただ見てるだけ”じゃ意味がないんだ。客数や客単価と一緒にメモしておくと、すぐに“今日はなぜ良かったか悪かったか”が見えてくる。」
後輩:「あぁ、日によって理由を考えられるようになるんですね。」
先輩:「そう。“雨の日は客数が減る”“ランチセットを始めたら単価が上がった”っていう因果関係をつかむのが目的なんだよ。」
在庫管理でムダを減らす
後輩:「在庫って、残ってたら次の日に使えばいいんですよね?」
先輩:「食材はそう簡単じゃない。鮮度が落ちたり、廃棄になったりしら丸損だろ?」
後輩:「たしかに…。特に野菜やパンは日持ちしないですね。」
先輩:「だから在庫は“仕入れ量と売上”を照らし合わせて、少しずつ調整していく。これができるかどうかで利益が全然変わるんだ。」
後輩:「つまり、売上管理と在庫管理はセットで考えるんですね。」
先輩:「その通り。売れてる数に合わせて仕入れを変える。これが経営管理の基本だよ。」
日報の習慣が未来を救う
後輩:「でも、毎日数字を見続けるのって大変そうです。」
先輩:「最初は面倒に感じるけど、慣れると5分で終わるよ。売上・客数・仕入れ・残った在庫をざっと書くだけ。それを“日報”として残すんだ。」
後輩:「日報かぁ…なんか会社みたいですね。」
先輩:「会社っぽくてもいいんだよ。日報を1ヶ月分まとめて見れば、“客数が伸びる曜日”“売れ筋メニュー”が一目でわかるから。」
改善のタネは“数字の中”にある
後輩:「数字を見るのって、ちょっと苦手だけど大事なんですね。」
先輩:「そう。数字はウソをつかないからね。どんなに“今日は忙しかった!”と思っても、売上を見たら意外と少ないこともあるし、逆に“暇だったのに売上は悪くない”って日もある。」
後輩:「そういうのを振り返ると、改善につながるんですね。」
先輩:「まさにそれ。経営管理って難しいイメージがあるけど、要は“お金と在庫の流れを毎日ちょっとだけ見直す”ことなんだよ。」
売上は“数字+理由”で記録する
・在庫は仕入れと売上を照らし合わせて調整
・日報の習慣で改善点が見える
開業後の経営は、豪華な戦略よりも毎日の小さな記録と改善が勝敗を分けます。
改善・成長のためにPDCAってどう使えばいい?
お店を続けていくと、「思ったより売れないメニュー」や「在庫ロスが多い」といった悩みが必ず出てきます。
そんな時に役立つのが PDCAサイクル。難しそうに聞こえるけど、実は飲食店にピッタリな考え方なんです。
そもそもPDCAってなに?
後輩:「先輩、PDCAってよく聞くんですけど、正直よく分からないんです…。」
先輩:「簡単に言うと、“計画 → 実行 → 振り返り → 改善”をぐるぐる回していく仕組みだよ。」
後輩:「計画って、メニューを決めるとかですか?」
先輩:「そうそう。例えば“新しいランチセットを出す”っていうのが計画(Plan)。それを実際に出してみるのが実行(Do)。売上やお客さんの反応をチェックするのが確認(Check)。で、改善(Act)して次につなげる。これがPDCAだね。」
「小さく試す」がコツ
後輩:「でも、全部をPDCAでやろうとすると大変じゃないですか?」
先輩:「だから“いきなり大きくやらない”のがコツ。まずは小さく試すんだ。」
後輩:「例えば?」
先輩:「新しいメニューを全日程で出すんじゃなく、週末だけに出してみるとか。お客さんの声を聞いて、いけそうなら本格導入。これならリスクも小さいし、改善もしやすいだろ?」
数字と感覚、両方を見る
後輩:「チェックって、売上だけ見ればいいんですか?」
先輩:「数字は大事。でもそれだけじゃ足りない。アンケートとか、店員へのお客さんの一言、SNSの反応も大事な材料だよ。」
後輩:「なるほど、数字とお客さんの声を両方集めるんですね。」
先輩:「そうそう。数字でトレンドを見て、声でリアルな反応を感じ取る。その両方があって初めて改善できるんだ。」
改善は“次に活かす”ことが大事
後輩:「改善って、ダメだったことをやめるって感じですか?」
先輩:「やめるのも一つだけど、“少し変えてもう一度試す”のが大事。例えば、売れなかったケーキを全部やめるんじゃなくて、甘さを控えて再挑戦するとかね。」
後輩:「なるほど!失敗じゃなくて、改善の材料なんですね。」
先輩:「その通り。飲食店ってトライ&エラーの連続だから、改善を次に活かす視点が超大事なんだ。」
まとめ
後輩:「要するに、計画して試して、振り返って直していく。これを繰り返すと自然にお店が良くなるってことですね。」
先輩:「そう!難しい理論じゃなくて、“小さく試して、振り返って、次に活かす”。これがPDCAの本質だよ。」
長期的な経営戦略ってどう考えればいい?
お店を長く続けるためには、日々のオペレーションに追われるだけじゃなく、将来を見据えた戦略も欠かせません。
この章では「長期的な経営戦略」について掘り下げてみます。
まずは「お店をどうしたいか」を描く
後輩:「長期的な経営戦略って、正直まだピンと来ないんです。とりあえず毎日お客さんに来てもらえればいいかなって…」
先輩:「気持ちは分かるよ。でも“どんなお店でありたいか”を言葉にしておかないと、日々の選択にブレが出ちゃうんだ。」
後輩:「たとえば?」
先輩:「『地域で一番リラックスできるカフェになりたい』とか『ランチの回転を重視して稼働率を上げたい』とか。ゴールを決めることで、内装やメニュー、SNSの方向性まで一貫性が出てくるんだ。」
数字を積み重ねて未来を考える
後輩:「でも、ビジョンって抽象的で…。実際には何をしたらいいんですか?」
先輩:「数字だよ。売上、客単価、回転率…これを毎月まとめて“次にどう動くか”を考えるんだ。」
後輩:「将来の戦略って数字から逆算する感じですか?」
先輩:「そう。例えば『1日30人に来てもらえたら黒字』なら、それを1年で50人にするにはどうするか、を考える。数字を積み上げると現実的な戦略が見えてくるんだよ。」
成長のカギは「固定客」と「変化」
後輩:「長く続けるには、やっぱり常連さんを増やすのが大事ですか?」
先輩:「その通り!固定客は経営の土台だよ。でも同時に、新しいメニューやイベントで“変化”を入れることも必要。」
後輩:「安定と変化、両方いるんですね。」
先輩:「そう。『変わらない安心感』と『新しい楽しみ』のバランスをどう取るかが、長期戦略のポイントなんだ。」
周囲の環境も戦略の一部
後輩:「お店の中のことだけ考えればいいんですか?」
先輩:「いや、むしろ外を見るのも大事。周囲に競合が増えるとか、街の客層が変わるとか、環境は常に動いてる。」
後輩:「じゃあ戦略も変えていく必要がある?」
先輩:「その通り。『最初に決めた方向性』を大事にしつつ、変化に合わせて柔軟にアップデートするのが経営者の仕事だよ。」
まとめ
後輩:「なんだか難しそうですけど、要するに“目標を決めて、数字を見ながら、環境に合わせて柔軟に”ってことですね。」
先輩:「そうそう!毎日お客さんと向き合いながらも、長い目でお店の未来を考える。それが長期的な経営戦略ってことさ。」
成功と失敗の分かれ道は? ― 準備と継続がカギ
“準備不足”が一番の落とし穴
後輩:「先輩、正直言って…カフェの開業って、成功する人と失敗する人の違いって何なんですか?」
先輩:「一番大きいのは“準備不足”。内装や資金だけじゃなくて、オープン前に“どう経営するか”を具体的に考えているかどうかで差が出るんだ。」
後輩:「なるほど…勢いだけで始めると危ないんですね。」
先輩:「そう。開業までは誰でも走り切れるけど、“オープンしてからどう続けるか”が本当の勝負だからね。」
数字を見ないと“赤字スパイラル”に
後輩:「でも毎日お客さんに喜んでもらえてれば、それでうまくいくんじゃないですか?」
先輩:「気持ちはわかるけど、それだけじゃ危ない。数字を見ないと、気づいたら赤字が積み重なってた…なんてことになる。」
後輩:「うっ…数字、苦手なんですよね。」
先輩:「売上や原価、在庫。最低限の管理だけでもやれば、“今どこで改善すべきか”が見える。これを放置すると、失敗への道まっしぐらなんだ。」
継続力と改善力の差
後輩:「じゃあ、準備と数字管理ができてれば成功ですか?」
先輩:「それだけじゃなくて、“改善を続けられるか”がポイントだよ。」
後輩:「改善って、例えば?」
先輩:「メニューが思ったより売れないならレシピを変える、仕入れが無駄なら数量を調整する。小さな修正を続けていくことで、お店が強くなる。」
後輩:「毎日走りながら直していく感じですね。」
先輩:「そう。これができる人は長く続くし、放置する人は短期間で疲れてしまうんだ。」
“やりたいこと”と“お客さんが求めること”のバランス
後輩:「自分がやりたいお店を貫くのはダメですか?」
先輩:「やりたいことは大事。でも、お客さんが求めてないと続かないんだ。例えば、超こだわりの高級コーヒーだけ出したい!って思っても、その街に“手軽なカフェ”を求める人が多ければ苦戦する。」
後輩:「じゃあ妥協しないといけないんですか?」
先輩:「妥協じゃなくてバランス。自分のこだわりを出しつつ、お客さんが求める形に寄せていく。それが“成功と失敗の分かれ道”なんだよ。」
まとめ
・成功する人は 準備を怠らず、数字を見て改善を続ける
・失敗する人は 勢いだけで始めて、改善せずに疲弊してしまう
・大事なのは、 自分のこだわりとお客さんのニーズを両立させること
第5回のまとめ ― 開業前と開業後に大事なことって?
開業前の準備は「仕上げ」と「発信」
後輩:「先輩、今日の話で一番印象に残ったのは“開業当日は準備で決まる”って言葉です。」
先輩:「うん。内装・家具・食器の最終チェックとか、SNSでのお知らせとか、当日を迎える前にどれだけ仕上げておけるかで流れが全然違うからね。」
後輩:「プレオープンでお客さんに見てもらうのも大事なんですよね?」
先輩:「そう。試運転で気づいたことを直せば、本番はずっと安心できるよ。」
開業後は「数字」と「改善」で成長
後輩:「開業してからは、やっぱり売上を見て一喜一憂しそうです…。」
先輩:「最初はみんなそう。でも大事なのは“数字を記録すること”。売上、客数、在庫、これを毎月ちゃんと見れば次の行動が考えやすい。」
後輩:「それをPDCAで回すんですね?」
先輩:「その通り!小さく試して、振り返って、直して、次につなげる。これを繰り返すと自然にお店が強くなっていくんだ。」
長期戦略は「ぶれない軸」と「柔軟さ」
後輩:「長期的な経営戦略っていうのは、まだ難しく感じますけど…」
先輩:「簡単に言うと、“お店をどうしたいか”を決めることだね。常連さんに愛されたいのか、売上をどんどん伸ばしたいのか。それを決めておけばブレなくなる。」
後輩:「でも、周りの環境も変わりますよね?」
先輩:「だから柔軟さも必要。ぶれない軸を持ちつつ、状況に合わせてアップデートできるのが、長く続くお店の特徴だよ。」
まとめのまとめ
後輩:「準備、記録、改善、そして長期的な方向性…なんだか全部大事ですね。」
先輩:「そう。要するに“開業はゴールじゃなくスタート”。準備を丁寧にして、日々を改善しながら、未来を見据える。それが続けるコツだよ。」
後輩:「よし、少しずつでも積み重ねて、長く愛されるお店を目指します!」
▶開業は大きな一歩。しかし、本当の勝負はその先にあります。
今回のシリーズを通じて、あなたのカフェ開業が少しでもスムーズで楽しい挑戦になりますように。

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。
テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。
是非ご活用ください。
業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。
是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
#飲食店 #厨房 #開業 #カフェ #開業までの道のり #開業豆知識 #自分のお店を持つ #仕上げ #発信 #成功と失敗 #プレオープン #数字 #改善 #PDCA #ぶれない軸 #柔軟さ #お店をどうしたいか


























