ラーメン店を開業する際、麺やスープの開発には多くの時間をかける一方で、「ラーメン丼」の選定は後回しにされがちです。
しかし実際には、ラーメン丼のデザイン・形状・サイズ・素材は、提供する一杯の印象を大きく左右する重要な要素です。本記事では、飲食店の開業やラーメン店経営を考えている方に向けて、ラーメン丼の選び方を徹底解説します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
ラーメン丼とは?その基本と文化

ラーメン丼は、ラーメンを盛り付けるための専用の食器です。一般的な丼よりも口が広く、深さがあるのが特徴で、これは、ラーメンのスープ、麺、具材をバランス良く盛り付け、美味しく食べるために計算された形状です。
ラーメン丼の歴史と文化的背景
ラーメンの歴史と共に、ラーメン丼の形状やデザインも変化してきました。
明治時代に中国から伝わった当初は、シンプルな形状の丼が使われていましたが、ラーメンが日本独自の食文化として発展するにつれて、様々な形状やデザインの丼が生まれました。
例えば、高台(こうだい)と呼ばれる底の部分が高くなっている丼は、熱いスープが直接テーブルに伝わるのを防ぐための工夫です。また、内側に模様が描かれた丼は、ラーメンを食べる際の視覚的な楽しみを提供します。
ラーメン丼は、日本の食文化と深く結びついた、美しさを追求した食器と言えるでしょう。
ラーメンの種類と丼の関係
ラーメンは、スープの種類(醤油、味噌、豚骨など)、麺の種類(太麺、細麺、縮れ麺など)、具材など、様々な要素で構成され、その組み合わせは無限大です。そして、ラーメンの種類によって、最適な丼の形状や素材、サイズが異なります。
例えば、あっさりとした醤油ラーメンには、スープの色と香りを引き立てるために、内側が白いシンプルな丼が適しています。一方、濃厚な豚骨ラーメンには、スープが冷めにくく、麺と具材がバランス良く収まる深めの丼が好まれます。
このように、ラーメンの種類と丼の相性を考慮することで、ラーメンの美味しさをさらに引き立てることができるのです。
なぜラーメン丼選びが重要なのか
客様の印象を左右する器の力
ラーメンを提供した瞬間に目に入るのが、丼のデザインや形です。
第一印象は器で決まると言っても過言ではありません。見た目の美しさはもちろん、料理全体の世界観を伝えるツールにもなります。
スープや麺との相性が売上に直結する理由
丼の深さや広がりによって、スープの保温性・香りの立ち方・麺の見え方が変わります。これにより、味わいだけでなく「美味しそうに見えるかどうか」も変化します。
リピート率にも影響?丼とブランディングの関係
ユニークな丼や、店のロゴが入ったオリジナル丼は、SNSや口コミでの拡散にも効果的です。記憶にも残りやすく、リピーターの獲得や店舗ブランディングに貢献します。
ラーメン丼の主な種類と特徴

ラーメン丼にはさまざまな形状があり、それぞれに盛り付けの美しさ・食べやすさ・スープの温度保持といった機能的な違いがあります。以下に、業務用として流通している主な丼の種類を紹介します。
ラーメン丼の代表的な形状・名称と特徴
高台丼(こうだいどん)

底部にしっかりとした高台(脚部)があり、持ちやすく、見た目にも重厚感がある丼です。
定番で、和風やクラシカルな印象を与えやすいです。
反高台丼(そりこうだいどん)

高台丼よりも口縁が外側に反って広がっているタイプです。
底が高くなっており、持ちやすく、熱いスープが手に伝わりにくいのが特徴です。
高台の形状によって、安定感やデザイン性が変化します。
見た目に広がりがあり、香りを立てやすく、盛り付けが美しく見えるため、写真映えも◎。
切立丼(きったちどん)

側面が真っ直ぐになった丼です。高さが低いものが多く、片手で持ちやすく重ねがしやすいのが特徴です。
口が広く、麺や具材が取り出しやすい、定番の形状です。
開放感があり、盛り付けの美しさが際立ちます。
玉丼・玉渕丼(たまどん・たまぶちどん)

丸みのあるフォルムで、やわらかい印象です。
玉渕丼は、口元に「玉縁」と呼ばれる膨らみがあり欠けにくい作りとなっています。持ちやすさとデザイン性を兼ね備えた丼です。
多用丼(たようどん)

様々な種類のラーメンに対応できます。汎用性が高く、つけ麺にも使用できます。
また、うどんや丼物の提供にも向いており、業態を広げたい飲食店におすすめです。
形状によって変わる「機能性と演出力」
形状が異なれば、見た目・香り・スープの冷めにくさ・食べやすさすべてに影響が出ます。
例えば、寸胴タイプは保温性が高い一方で、浅めの反り型は冷めやすいが見映えに優れています。
提供するラーメンのスタイルに合わせて、丼の形状を選ぶことが非常に重要です。
このように、丼の形状一つで「味の感じ方」や「ブランディング」さえ変わってくるのがラーメンの奥深さです。
関連記事:ラーメン屋開業の機器・什器・備品の選びかた ラーメン丼と箸、レンゲ編
サイズの選び方と目安
ラーメン丼のサイズは、見た目のバランス・食べやすさ・提供する量感を決定づける重要な要素です。丼の選定を誤ると、「量が少なく見える」「食べにくい」「スープが冷めやすい」といった問題が発生します。以下では、サイズ選びの基本とラーメンの種類別のおすすめサイズを紹介します。
定番サイズとその理由
一般的なラーメン丼のサイズは7.0寸(約21cm)前後が主流です。これは、スープ・麺・具材をバランスよく収められる容量(約1,200ml前後)であり、ほとんどのラーメンに対応できる汎用性があるからです。
主な丼サイズ
6.3寸
- 直径目安:約19cm
- 容量目安:約800ml
- 用途の一例:博多ラーメン、小ラーメン、女性・子供向け
7.0寸
- 直径目安:約21cm
- 容量目安:約1,200ml
- 用途の一例:標準サイズのラーメン全般
7.5寸
- 直径目安:約22.5cm
- 容量目安:約1,400ml
- 用途の一例:大盛り・具だくさん系
8.0寸
- 直径目安:約24cm
- 容量目安:約1,600ml以上
- 用途の一例:二郎系・特盛・味噌ラーメン系
提供するラーメンの種類別おすすめサイズ
醤油・塩ラーメン
- 丼のサイズ目安:7.0寸(約21cm)
- 形状のおすすめ:高台丼、反高台丼、腰張丼、切立丼
- 理由:スープの色や具材を美しく見せるため。香りが立ちやすい形状が◎
味噌ラーメン
- 丼のサイズ目安:7.5寸~8.0寸
- 形状のおすすめ:高台丼、反高台丼、玉丼
- 理由:具材が多く、濃厚スープで熱々を提供するため深さが必要
豚骨ラーメン
- 丼のサイズ目安:6.3寸~7.0寸
- 形状のおすすめ:高台丼、反高台丼、切立丼
- 理由:細麺・替え玉文化の影響でやや小ぶりが主流。熱を逃がさずスープを濃厚に感じやすい。
二郎系・家系ラーメン
- 丼のサイズ目安:7.5寸~8.0寸以上
- 形状のおすすめ:高台丼、反高台丼、切立丼
- 理由:トッピングが多く麺量も多いため、容量の大きい丼が必須
淡麗系・創作系ラーメン
- 丼のサイズ目安:7.0寸前後
- 形状のおすすめ:多用丼、腰張丼、深口の切立丼
- 理由:ビジュアルや香り重視のスタイルに。浅めの丼で美しさを演出
テーブル・厨房設備とのバランス
丼のサイズが大きすぎると、カウンターの奥行きに干渉したり、洗浄機に入らなかったりすることがあります。
特に、厨房内でのスタッキング性や洗いやすさ、収納スペースも考慮して、実店舗でのシミュレーションを行ってから導入するのが望ましいです。
ラーメンのジャンルや店舗のオペレーションに応じてサイズと形状を最適化することで、見た目・味・効率のすべてが向上します。
デザインと色で差別化するコツ

ラーメンの見た目は、味の印象・店の個性・SNSでの拡散力に大きく影響します。丼のデザインや色選びを工夫することで、他店と差別化し、「記憶に残る一杯」を演出することが可能です。
店のコンセプトに合ったデザインとは?
丼のデザインは、店舗のブランドイメージや客層にマッチさせることが重要です。
昔ながらのラーメン店
赤や青の雷紋柄、唐草模様などのクラシックデザインがおすすめです。
モダンでおしゃれな店
無地、マット調、黒や藍色などシンプル系がおすすめです。
ファミリー層を狙う店
明るめの色調、親しみやすい柔らかいフォルムの丼がおすすめです。
高価格帯の専門店
重厚感ある釉薬仕上げ、手仕事感ある一点ものがおすすめです。
写真映え・SNS映えを狙うなら
SNSでの「拡散」や「バズり」を狙うなら、盛り付け+器の相性が極めて重要です。
- 器のフチが黒や濃い色:スープの白濁感や具材の色が際立つ(例:豚骨ラーメン)
- 浅めで広がりのある形状:俯瞰撮影(上からの撮影)で立体感が出やすい
- 柄やロゴが見える配置:丼の内側に店舗ロゴを入れることで、ブランドアピールにも効果大
- 和モダンやヴィンテージ感のある質感:若年層に人気
◇ポイント◇
SNSを意識するなら、実際に料理を盛って何枚か写真を撮ってみることを推奨します。
プラスアルファの工夫で個性を演出
オリジナルのロゴや模様を入れる
お店のロゴや模様を丼に入れることで、特別感を演出できます。
オリジナル丼は初期費用がかかりますが、ブランディング効果やSNS上での拡散性を考えると費用対効果は高いといえます。
このように、丼の色やデザインは単なる器選びではなく、店舗の世界観と売上に直結する戦略的要素です。
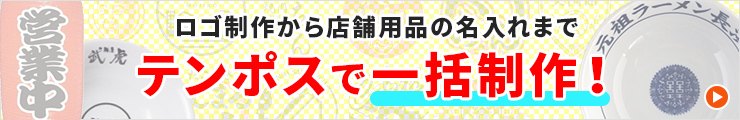
コストと耐久性のバランス
飲食店においてラーメン丼は、見た目や機能性だけでなく、「コスト」と「耐久性」も重要な判断基準です。特に開業時や複数店舗展開を見据える場合は、長期的なコストパフォーマンスを考えた器選びが求められます。
飲食店におけるコスパの良い素材とは
主な素材ごとの特徴とコスト目安を比較してみましょう
磁器
- 特徴:見た目が美しく、吸水性が低く清潔
- コスト:中〜高
- 耐久性:高
- 備考:飲食店の定番。デザイン種類も豊富
陶器
- 特徴:土の風合いがあり個性的
- コスト:中
- 耐久性:中
- 備考:割れやすい。温かみのある印象に◎
メラミン樹脂
- 特徴:軽くて割れにくい、扱いやすい
- コスト:低〜中
- 耐久性:非常に高
- 備考:高回転店舗や配膳頻度の高い店に最適
強化磁器(ストーンウェア)
- 特徴:見た目と耐久性のバランスが良い
- コスト:中
- 耐久性:高
- 備考:重量はあるが長期使用可能
◇ポイント◇
開業初期は磁器やメラミンを併用し、オリジナル陶器は段階的に導入するのが現実的です。
破損リスクとその対策
業務用丼は毎日の洗浄や運搬でどうしても破損リスクが生じます。
破損対策のポイント
- 高台がしっかりしている形状を選ぶ(持ちやすく落としにくい)
- 洗浄時に他の食器とぶつからない工夫(仕切りやラックの使用)
- メラミン丼や強化磁器を混在させる(混雑時のリスク軽減)
- 予備の在庫を5~10%多めに確保しておく
大量仕入れ時の注意点
丼を一括で導入する際は、コスト交渉・品質確認・納期管理が重要になります。
チェックすべきポイント
- ロット数による単価の変動:数量によって大幅な値引きが可能なケースも
- サンプル提供の有無:実際に盛り付けて確認できるか
- 納品後の追加発注が可能か:モデル廃番や在庫切れリスクに備える
- サイズや色の個体差(特に陶器):手作業のものはロットで微差が出ることもある
コストと耐久性は、「見た目重視」だけでは成り立たない現場のリアルな条件です。開業前には必ず、試用・見積もり・現場シミュレーションを行うことが成功のカギになります。
おすすめのラーメン丼

牡丹 切立6.8寸丼 10個入
\☆人気の定番型☆/
- 容量:1000cc
- 寸法:高さ7.5×口径20.3cm
- お届け数(合計):10
- 材質・素材:磁器
- 特記事項:美濃焼
ラーメン丼 白 丸反7寸丼 10個入
\シンプルで安いから売れています!/
- 寸法:高さ8.5×口径21cm
- お届け数(合計):10
- 材質・素材:磁器
- 特記事項:美濃焼
赤巻切立6.3深丼 φ18.8×10.2cm (5個入)
\普通の切立より深めのおしゃれ形状/
- 入り数:5
- サイズ:φ18.8×10.2cm
- 材質:磁器
ラーメン丼 支那絵 丸反7寸丼 10個入
\定番の雷紋&鳳凰模様をカラフルに/
- 容量:1350cc
- 寸法:高さ8.5×口径21.2cm
- お届け数(合計):10
- 材質・素材:磁器
- 特記事項:美濃焼
藍唐草めん丼 φ18.8×7.7cm (10個入)
\藍色は醤油系と相性バッチリ!/
- 入り数:10
- サイズ:φ18.8×7.7cm
- 材質:磁器
まとめ ~理想の一杯は理想の丼から~
ラーメン丼は、ただ料理を盛るだけの器ではありません。
味の印象、店の世界観、オペレーションの効率、そしてお客様の記憶に残るかどうか、それらすべてに関わる、非常に重要な「戦略アイテム」です。
ラーメンの種類に合った形状・サイズを選び、
店舗の雰囲気を引き立てるデザイン・カラーを意識し、
長く安心して使える耐久性とコストのバランスを考慮すること。
さらに、信頼できる仕入れ先と連携することで、開業後のトラブルも防げます。
丼ひとつにもこだわることで、
お客様に「また食べたい」と思わせる一杯が完成します。
「理想のラーメンは、理想の丼から」
──この視点を持つことで、あなたの店は一段と強く、印象深くなるはずです。
#ラーメン丼 #らーめん丼 #選び方 #種類 #素材 #デザイン #サイズ #おしゃれ #こだわり #業務用


























