「お通しなんて、原価が安ければいい」
「とりあえず小鉢に何か入れて出せばOK」
そんなふうに考えてはいませんか?
確かに、お通しは居酒屋業態ではごく当たり前の存在で、単なる“席料代わり”と思われがちです。
しかし、実はこの小さな一皿が、お客様の第一印象を左右し、売上やリピート率に大きく影響することもあるのです。
お通しには、お店の「味の個性」や「もてなしの姿勢」が凝縮されており、場合によっては料理よりも強く印象に残ることさえあります。
実際、「あのお通しがおいしいから、また行きたい」といった声も少なくありません。
本記事では、そんな“お通し”の可能性に着目し、原価・仕込みの手間・見た目・味の工夫・SNS映えといった観点から、売上アップに貢献するミニメニューの設計術をご紹介します。
「なんとなく」で出すのは、今日で終わりにしませんか?
今回は、原価・手間・印象・SNS映えといった観点から、お通しの設計ポイントや成功例・失敗例を交えながら、“地味に重要なお通し”を見直すヒントをご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
お通しは「ただの席料」ではない
お通しは、単に席料代わりとして設定されていると思われがちですが、実はそれ以上の大きな意味と役割を持っています。
まず、お客様にとってお通しは、その日最初に口にする料理であり、言わば「お店の自己紹介」のようなものです。
たとえば、料理の温度、味つけのバランス、盛り付けのセンスなど、わずか一皿からでも店の“空気感”や“方向性”が伝わります。
もしお通しが「スーパーで買った総菜のような味」や「家庭で出てくるような煮物」だった場合、お客様は無意識に「このお店の料理もこんな感じかな」と思ってしまうかもしれません。
それがきっかけで、料理の注文数が減ったり、早めの退店につながったりすることもあります。
反対に、「見た目がきれい」「味にひと工夫ある」「意外性がある」など、小さな感動を与えられるお通しは、お客様の気持ちをグッとつかみます。
料理への期待感が高まり、追加注文や滞在時間の延長、再来店のきっかけにもなりやすくなります。
また、最近では「お通しがおしゃれ」「前菜からワクワクした」といったコメントがSNSに投稿されることで、自然な宣伝効果を生むケースも増えています。
こうした「想定外の広がり」は、ただの席料では得られない価値と言えるでしょう。
つまり、お通しは「仕方なく出すもの」ではなく、小さな一皿でお店の印象を大きく左右できる“戦略的な料理”なのです。
限られた予算と手間の中でも、こだわりや個性を感じてもらえるよう、ぜひ改めて見直してみてはいかがでしょうか。
原価と手間のバランスが“お通しの価値”を決める
お通しは、一人あたり数百円で提供されることが一般的です。
そのため、原価を抑えることは大前提となります。
しかし、安く仕上げることだけを意識してしまうと、見た目や味がチープになり、お客様の満足度を下げてしまうおそれもあります。
目安としては、原価は100円以内に抑えることをおすすめします。
これは、お通し価格が300円〜400円の場合、原価率30%程度にあたるためです。
ただし、原価が安い=手抜き、と思われないよう、下処理や味付け、盛り付けに一工夫加えることが重要です。
また、もう一つの大切な要素が「仕込みの手間」です。
ピークタイムにバタバタしないよう、前日までに仕込めて、提供時は盛るだけで出せるものが理想的です。
冷菜や和え物、ゼリー寄せなどはその点でも使い勝手が良いです。
例えば、同じ食材を使っても、
「そのまま出すだけのミニサラダ」よりも、
「だしゼリーと合わせた小鉢」や「彩り野菜のピクルス」などのほうが、
見た目にも味にも工夫を感じさせ、コストをかけなくても満足感を演出することができます。
原価と手間、この二つのバランスをうまく取ることが、コストパフォーマンスに優れた“印象に残るお通し”への第一歩です。
器選びの工夫で「なんとなく美味しそう」に見せる
お通しは量が少ないからこそ、「器の選び方」が料理全体の印象を大きく左右します。
お通し専用に、小ぶりで個性的な器を数種類用意しておくだけで、ぐっと印象が良くなります。
例えば、
・和風の煮物には、風合いのある信楽焼の小鉢
・洋風の前菜には、ガラスや透明な器で軽やかに
・彩り豊かな和え物には、黒や藍色など引き立て色の器
といったように、料理の色味やテイストに合わせて器を選ぶことで、味の印象まで引き上げる効果があります。
また、最近は木製トレイに3種盛りにするなど、ビジュアル面を重視したお通しスタイルも人気です。
これにより「お通しなのにワクワクする」「ちょっとした前菜コースみたい」とお客様の感動ポイントが増え、SNSでも拡散されやすくなります。
器は「味を引き立てる舞台装置」です。どんなに安価な食材でも、器の演出次第で「いいお通しだな」と思わせることは十分可能です。
料理と器の相乗効果を意識して、見た目の価値を高めましょう。
テンポスでお買い求めいただけるお通しにピッタリな食器をご紹介!
小鉢 いぶし黒 六兵衛四つ山小鉢(小)/業務用/新品

見た目にも美しい小鉢。
焼き物の風合いが和の雰囲気によく合います。
アクリル小付 φ80鉢 亀甲カット ブルー (全面塗)/業務用/新品/小物送料対象商品

透明なブルーが綺麗な一品。
涼やかで軽やかな雰囲気になります。
豆鉢 黒銀市松/業務用/新品/小物送料対象商品

オシャレな色合いの豆鉢。
鮮やかな色合いのお通しを盛り付けて色味を引き立てましょう。
木製くりぬきトレー スリム ナチュラル/業務用/新品/小物送料対象商品

盛り合わせにぴったり!
数種類を一緒に出してお得感を演出◎
テレサシリーズ/ラベンダー/小鉢/業務用/新品/小物送料対象商品

ラベンダー柄がかわいい一品。
和洋中に合う小鉢です。
お通しづくりの4大ポイントとは?
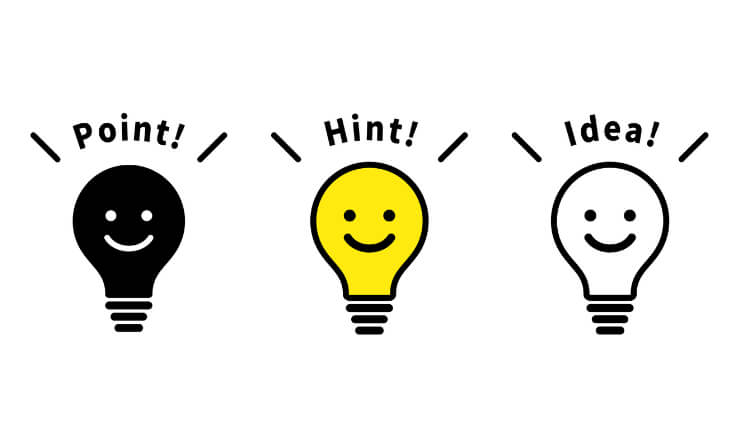
お通しは、お店の第一印象を左右する大事なひと皿です。
そのためには「なんとなく作る」ではなく、明確な意図をもって設計することが重要です。
ここでは、実際にお通しを考える際に押さえておきたい「4つの視点」をご紹介します。
ポイント1. 原価と利益率を意識する
お通しは一人につき自動的に出るメニューであり、数百円の単価とはいえ売上全体に与えるインパクトは意外に大きいです。
その分、原価率をしっかり抑えて利益を確保することが求められます。
・原価は 1人前あたり80〜100円以下が目安
・同じ食材を他メニューと共用して ロスを防ぐ
・仕込みの効率を考えて 作り置きや冷製中心に構成
たとえば、旬の野菜を使ったナムルや、切り落とし肉を使った煮凝りなどは、コストを抑えながらも「手づくり感」が伝わるお通しになります。
ポイント2. “ひと手間感”をプラスして印象づける
お通しは「すぐに出てくる=雑」と思われがちなメニューです。
ですが、逆に小さなひと工夫があると、それだけで印象が大きく変わります。
・ピクルスに香草を加えて香りを演出
・定番のおひたしをゼリー寄せに変える
・同じ食材でも、ソースやドレッシングで変化をつける
たったそれだけで、「お、手がかかっているな」「意外と凝っている」と感じてもらえることが多いです。
食材ではなく“工夫”に価値を乗せる発想がポイントです。
ポイント3. 見た目で惹きつける工夫をする
ボリュームよりも見た目の美しさや彩りの良さで印象に残すことが、お通しには求められます。
・季節感を色で表現(春は淡い緑とピンク、夏は涼しげなブルーや白など)
・赤・黄・緑などの信号色を意識してコントラストを作る
・トッピングやあしらい(ハーブ、ゴマ、柚子皮など)で立体感を出す
たとえば、「小さな和え物を木のスプーンにのせて出す」「ガラスの器にジュレを重ねて見せる」など、写真に撮りたくなるような盛り付けを意識すると、SNSでの拡散にもつながります。
ポイント4. 店舗のコンセプトとつなげる
お通しのスタイルが、お店の世界観やコンセプトと一貫しているかも大切なポイントです。
・ナチュラル系のカフェ風居酒屋なら「野菜中心・彩り重視」
・大衆酒場風なら「味の濃い家庭料理系で親しみやすさ」
・和モダン居酒屋なら「だしの効いた冷製前菜や、器づかいで高級感」
このように、店の空気感と料理がブレないことで、お通しから「期待どおり」の体験を提供でき、結果的に満足度や再来店率が高まります。
お通しは小さな料理ですが、経営における存在感は決して小さくありません。
「原価」「ひと手間」「見た目」「コンセプト」の4つを軸に、利益と満足を両立する“戦略的ミニメニュー”として見直してみてはいかがでしょうか?
成功例と失敗例:現場の声から学ぶ「お通し改革」
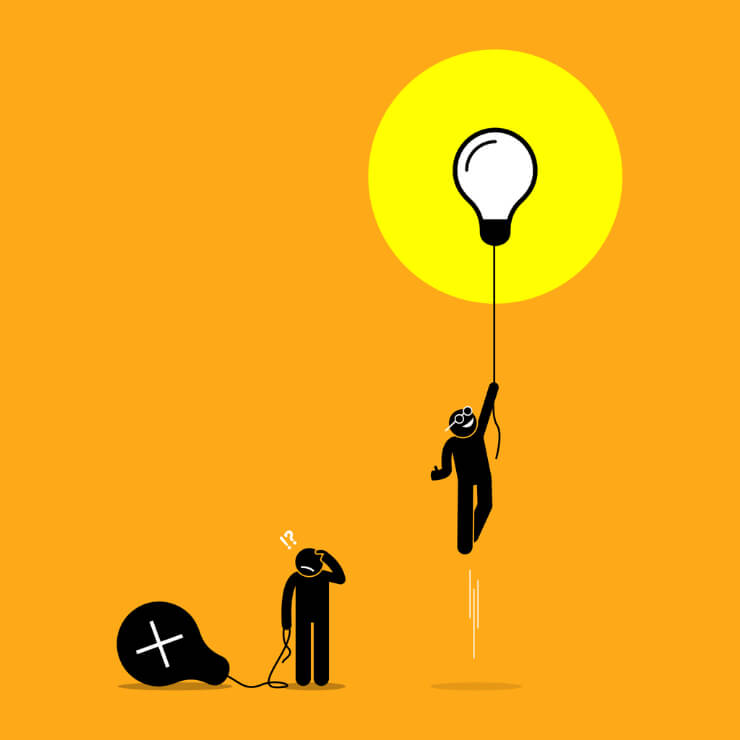
お通しのクオリティは、お客様の第一印象を左右し、時にはリピーターの獲得やSNS拡散にもつながる重要なポイントです。
ここでは、実際の飲食店の現場から聞こえてきた、成功例と失敗例をいくつかご紹介します。
成功例①:彩り野菜のマリネで女性客の心をつかむ
東京都内の創作居酒屋では、以前は定番の「きんぴらごぼう」や「煮物」をお通しとして提供していましたが、「味は良いけど地味」「見た目が家庭的すぎる」といった声がちらほらありました。
そこで、思い切ってお通しを「彩り野菜のマリネ」に変更。
パプリカ・ズッキーニ・紫キャベツなどを使い、見た目の鮮やかさと酸味のさっぱり感を演出しました。すると、
・「最初の一皿からテンションが上がる!」
・「写真に撮りたくなる」とSNS投稿が増加
・さらに、料理全体の注文数も上昇。
原価を抑えながらも印象に残るお通しとなり、集客・売上にプラス効果が出たとのことです。
成功例②:季節の小鉢三種盛りで“お通しが名物”に
関西のある和風居酒屋では、「お通しを名物にしてしまおう」という発想から、季節の小鉢を3種、木製のミニトレイで提供するスタイルを導入しました。
内容はシンプルながらも、
・旬の素材を使った冷製おひたし
・ひと手間かけただし巻き卵の煮浸し
・甘酢で和えた野菜のピクルス風
といった、季節感・彩り・やさしい味を意識した構成。
見た目のバリエーションと器づかいが評判となり、「あの三種盛りが楽しみでまた来たよ」というリピーターも増加したそうです。
また、SNSでも「お通しでテンションが上がる居酒屋」として話題になり、広告費ゼロで集客効果を発揮しました。
失敗例①:既製品を盛っただけで「手抜き感」が伝わる
ある中規模の居酒屋では、お通しとして「枝豆」や「ポテトサラダ(既製品)」をそのまま小鉢に盛って出していました。
コスト的には非常に効率的でしたが、結果としては
・「コンビニ感がある」
・「これで300円は高い」
・「2回目以降、最初から“お通しいらない”と断られる」
という事態に。
結果としてお通しの売上が下がるだけでなく、お店全体の印象ダウンにもつながってしまいました。
料理そのものは悪くないとしても、「手抜き感」「愛情のなさ」が伝わってしまうと、お客様の心は離れていきやすくなります。
失敗例②:手がかかりすぎて現場がパンク
一方で、お通しにこだわりすぎた結果、現場の負担が大きくなってしまったというケースもあります。
ある創作系ダイニングでは、「一口サイズの前菜を4品+スープを添えて提供」という非常に凝ったお通しを出していました。
しかし、
・毎日内容を変える必要がある
・提供に手間がかかりすぎてピーク時に回らない
・廃棄ロスも増える
といった問題が重なり、スタッフが疲弊し、逆に品質も不安定になってしまったのです。
結果、導入から数か月で元のスタイルに戻さざるを得なくなったそうです。
お通しは確かに「最初の感動」を生む料理ですが、現場に無理のない仕組みで運用することが成功のカギとなります。
成功と失敗の分かれ目は?
これらの例からわかるのは、以下のようなポイントです。
・「コスト」「手間」「印象」の3軸をバランスよく設計できているか?
・店舗コンセプトに合った演出になっているか?
・お客様が“わくわくする”要素をどこかに入れられているか?
この3つが揃っているお通しは、たとえシンプルでも「記憶に残る」「また来たい」と思ってもらえる可能性が高まります。
お通しは“ファンをつくるための投資”

飲食店にとって「お通し」は、単なる席料の名目や、経費回収の手段ではありません。
むしろ、最初のひと皿こそが“店の姿勢を伝える名刺代わり”であり、ファンづくりの第一歩となる大切な要素です。
「えっ、これが300円?」と思わせる価値を価格以上の満足感を提供できたとき、お客様の中でお通しの印象は一気にポジティブになります。
例えば、「少量でも手が込んでいて美味しい」「彩りがきれいで写真映えする」「季節を感じられる」といった要素は、ちょっとした驚きや感動を与えます。
実際に、「お通しがおいしくて、その時点でまた来ようと思った」という声は多くの飲食店で聞かれます。
それはつまり、お通しがリピーターを生むきっかけになるということです。
小さな感動が“信頼”に変わる
お客様は、お通しに「真心がこもっているかどうか」を直感的に感じ取ります。
たとえ1〜2口の料理でも、丁寧な仕込みや盛り付けが施されていれば、「この店はちゃんとしている」「メイン料理にも期待できる」と思ってもらえます。
逆に、ありきたりで味も印象も弱いお通しでは、お店全体に対する期待値も下がってしまいます。
つまり、お通しにはお店とお客様の最初の“信頼関係”を築く力があるのです。
長期的に見れば“コスパ最強の広告”
多くの店舗では、集客のために広告費やキャンペーンにコストをかけています。
しかし、SNS時代においては、「思わず撮ってシェアしたくなる」ようなお通しを出すことで、無料で高精度な“クチコミ型広告”が広がっていきます。
たとえば、「今日はこのお通しが出てきた」「月替わりで楽しめるから毎月行っている」といった投稿があれば、フォロワーの興味を惹き、新たな来店へとつながります。
つまり、お通しは広告費をかけずに店の魅力を発信し、“ファン化”を促進できる存在でもあるのです。
目先の原価より、信頼と期待の積み重ねを
もちろん、お通しの原価や手間は意識すべきです。
ただしそれだけにとらわれず、「ここに来てよかった」と思ってもらえる体験のひとつとして考えることが、お通しの価値を最大限に引き出すポイントです。
原価率を下げながらも、「見た目」「香り」「意外性」「季節感」などの演出で満足度を高める方法はいくらでもあります。
短期的な利益だけでなく、“また来たい”“誰かにすすめたい”と思わせる余白を、お通しに込めていくことが大切です。
お通しは、単なる小鉢料理ではありません。
お客様の心に残る、最初のサプライズと信頼の入口です。
「このお店、ちょっといいな」と思わせるひと皿を届けることで、利益以上の“ファン”という財産が生まれていきます。
お通しを、目先の数字ではなく、“未来のリピーターづくり”への投資として捉えてみませんか?
まとめ:お通しを「仕方なく」から「楽しみ」に
「お通しって、正直いらないんだけど……」
「席料を取るための名目でしょ?」
お客様からこのような声をいただいた経験はありませんか?
実際、飲食店に慣れていない方や、コスト意識の強いお客様にとっては、お通しは「頼んでいないのに出てくるもの」という印象が根強くあります。
しかし、それを逆手に取り、「お通しなのにこんなに良いの?」と良い意味で裏切る工夫ができれば、お通しは「仕方なく受け取るもの」から、「ちょっと楽しみなひと皿」へと大きく変わります。
お通しで“空気”をつくる
お通しは、お客様が席に座り、最初に料理として口にするものです。
つまり、その店の“空気感”を味わう第一歩なのです。
ここで温かみや驚き、季節感が伝われば、お客様の気分も自然と高まり、「このお店、センスがあるな」と感じてもらえるきっかけになります。
会話のきっかけにもなる
見た目にインパクトがあるお通しは、同席しているお客様同士の会話を弾ませたり、スタッフとのコミュニケーションの糸口になったりすることもあります。
「これ何ですか?」「どうやって作っているんですか?」と聞かれた時に、料理のストーリーを伝えられれば、食体験そのものが深まり、記憶にも残ります。
お通しは、小さくても“体験価値のあるメニュー”
トレンドに左右されずとも、「今日はこの一皿で、季節を感じられた」「素材の組み合わせが面白かった」「普段食べない料理を知れた」など、小さな感動や発見を与えることができます。
その積み重ねが、お店への信頼や愛着へとつながり、「また来たい」「次は誰かを連れて来たい」と思ってもらえる店づくりにつながります。
「お通し」にこそ、店の真心を込めて
これからの時代、お客様は“価格”よりも“価値”を見ています。
そして、その価値はメイン料理だけでなく、最初の一皿からじっくりと評価されているのです。
「なんとなく出しているお通し」から一歩踏み出して、「この一皿にうちの店の魅力が詰まっています」と言えるような、小さくて、強い料理を届けてみませんか?
ほんの少しの工夫で、お通しは「印象を残す武器」にも、「ファンを生む種」にもなります。
ぜひ、お通しの可能性を見直してみてください。
テンポスでは、記事中で紹介したもの以外にも、さまざまな小鉢を取り揃えております。
是非ご覧になってください。
また、テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。
是非ご活用ください。
業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。
是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
#飲食店 #厨房 #メニュー開発 #お通し #小鉢 #印象UP #コストと美味しさのバランス #成功例 #失敗談 #売上UP #最初の一品


























