飲食店の経営において「食材ロス」は避けて通れない課題です。
ただ、ロスをゼロにするのは現実的ではありません。
重要なのは「ロスがどれだけ出ていて、何が原因なのか」を見える化すること。
たった1週間の記録でも、驚くほどの気づきと改善が得られます。
この記事では、初心者でも取り組める「ロス記録」のやり方と、それによって得られる効果をご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
食材ロスの主な3パターンとは?

飲食店で発生する食材ロスには、いくつかの典型的なパターンがあります。
それぞれの原因を知っておくことで、どこに無駄が発生しているのかを明確にでき、改善への第一歩になります。
ここでは特に多い3つのパターンをご紹介します。
パターン1. 仕入れミス型ロス
こちらは「食材を過剰に仕入れてしまったことで起きるロス」です。
たとえば、週末に多くのお客様が来ると予想して多めに仕入れたものの、天候やイベントなどの影響で来店数が伸びず、結果として使い切れずに廃棄するケースです。
また、単純な発注ミスや、数量の見誤りによるロスも含まれます。
特に生鮮品や消費期限の短い食材(野菜、魚介、乳製品など)は、余らせるとロスになりやすいため注意が必要です。
仕入れミスは“売れ残り=利益の損失”に直結しますので、事前に売上予測を立てておくことが大切です。
パターン2. 仕込み過多型ロス
こちらは「仕込みを多くしすぎてしまったことによるロス」です。
たとえば、ランチタイムに向けてパスタソースを大量に仕込んだものの、注文が思ったほど入らず、翌日には使えなくなってしまったというようなケースです。
また、逆に仕込みを忘れたり、タイミングを誤ったりすることで食材の使用期限を逃してしまい、結果としてロスになる場合もあります。
このタイプのロスは、調理時間を短縮しようとする“善意”の行動が裏目に出ることも多いため、毎日の注文傾向を見ながら適切な量を見極めることが大切です。
パターン3. 在庫過多・劣化型ロス
これは「仕入れや仕込み後、使い切れずに食材が古くなってしまうことで発生するロス」です。
たとえば、冷蔵庫の奥にあった葉物野菜が気づかないうちに変色していたり、ストッカーの隅で賞味期限が過ぎていた調味料が見つかったりするケースです。
また、乾物や冷凍食材でも、パッケージを開封して放置していたことで品質が落ち、使えなくなってしまう場合もあります。
こうしたロスは、在庫の“見える化”と回転率の管理をしないと、気づかないうちに積み重なっていきます。
特に小規模店では、在庫の置き場が限られるため、「仕入れたら使い切る」「定期的に棚卸しを行う」などのルールづくりが有効です。
見える化に最適な商品をご紹介!
【即納可】TB ホワイトボードL(金具・紐のみ)/テンポスオリジナル/業務用/新品

【業務用/新品】【テンポスオリジナル】冷蔵ショーケース TBCR-845LX 幅750×奥行450×高さ1410(mm) 単相100V【送料無料】

イージーフラップ 6Pセット/業務用/新品/小物送料対象商品

ロスの“複合型”にも注意しましょう
なお、これらのロスは単独で起きるとは限らず、複合的に発生することもあります。
たとえば、過剰に仕入れた→多めに仕込んだ→結局使い切れず廃棄、というように、1つのミスが連鎖してロスを拡大させるケースです。
だからこそ、ロスを「ただの廃棄物」としてではなく、「原因と流れをたどれる情報」として記録・分析することが、改善への第一歩となるのです。
以上が、食材ロスの主なパターンです。
次にご紹介する「ロス記録の方法」を取り入れることで、これらのロスがどこから発生しているのかが見えるようになります。
「もったいない」を「次の改善」に変えるための仕組みづくりを、一緒に考えていきましょう。
「記録するだけ」でロスは減ります

「食材ロスを減らすには、なにか特別な設備や仕組みが必要なのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、ただ“記録するだけ”でロスは着実に減らすことができます。
その理由は、食材ロスの多くが「見えていないこと」から起きているからです。
● 無意識のうちにロスを見過ごしている
毎日の営業の中で、「ちょっと余った」「今日は余った分をまかないに使おう」といった判断はごく自然なことです。
ですが、そうした“なんとなくの廃棄”が日々積み重なると、月に数千円~数万円ものロスになっていることも少なくありません。
にもかかわらず、それが「どれだけ」「なぜ」ロスになったのかを把握していないと、同じミスや判断が繰り返されてしまいます。
● 記録によって意識と判断が変わる
ロスを記録することは、単に“事実を残す”ためだけではありません。
「今日は何が余ったか?」「なぜ余ったのか?」を意識することで、スタッフ自身の判断や仕入れ、仕込みの感覚が磨かれていきます。
たとえば、「この食材は週に2回余るな」と気づけば、次からは発注量を減らしたり、別の料理に使えないかと工夫したりといった改善行動につながります。
記録によって、経営者やスタッフの“食材に対する責任感”が自然と高まるのです。
● 記録は数字でなくても構いません
「記録」と聞くと、グラム単位での詳細な数字や、エクセルの複雑な表を想像する方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、最初からそこまで正確な記録を目指す必要はありません。
「キャベツ半玉余った」「冷凍えびを仕込んだけど使わなかった」「ソースが傷んでいた」など、ざっくりとしたメモで十分です。
慣れてきたら、曜日ごとの傾向や食材ごとのロス量も記録していくと、さらに精度が高まります。
● 続けることが何より大切です
記録の精度よりも、まずは「続けること」が大切です。
たとえ1週間でも記録を続けてみれば、「いつも金曜に野菜が余りがち」「パスタの仕込みは火曜が多い」など、店舗特有の“リズム”や“傾向”が見えてきます。
そうなれば、あとはそれに合わせて仕入れや仕込みの調整をするだけで、ロスは自然と減っていきます。
このように、ロスの“記録”はお金をかけず、すぐにでも始められる改善策です。
小さなひと手間が、大きなムダを防ぎ、利益につながっていきます。
次の章では、具体的な記録方法を3ステップでご紹介します。
ぜひ、できるところから始めてみてください。
実際の記録方法はこうする!簡単3ステップ
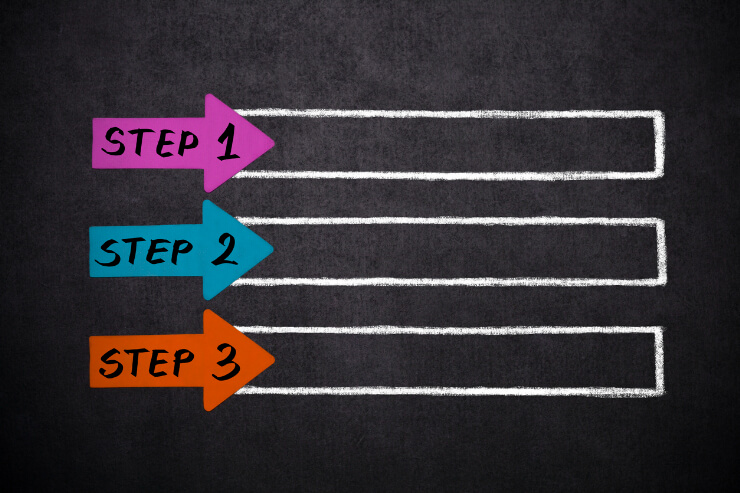
ロスの見える化は、難しい作業ではありません。
特別なシステムやアプリを使わなくても、紙とペンだけで始められるシンプルな方法です。
ここでは、初めての方でも取り組みやすい「3ステップの記録法」をご紹介します。
ステップ1:「その日のロス食材」を書き出す
営業終了後、またはその日の厨房作業の終わりに、使いきれずに余ってしまった食材や廃棄した食材を一覧で書き出します。
ポイントは、細かく正確に書こうとしすぎないことです。最初はおおよその内容で十分です。
記録例
・キャベツ 1/2玉(使いきれなかった)
・冷やしトマトの仕込み分 2食分(注文が入らず)
・バジルソース 30g程度(酸化して変色)
このように、「何が」「どのくらい」余ったかを記録するだけで、次第にロスの傾向が見えてきます。
余裕があれば、調味料やドレッシングなどの“サブ食材”も書き加えていくと、より効果的です。
ステップ2:「なぜロスになったのか?」一言メモを添える
書き出した食材ごとに、そのロスがどうして発生したのかの“原因”を一言で記録します。
この一言があることで、単なる廃棄リストが「改善へのヒント」に変わります。
メモ例
キャベツ
発注数を多く見積もりすぎた
冷やしトマト
天気が悪くて注文が少なかった
バジルソース
作り置きしてから3日経って変質した
こうしたメモは、翌週以降の仕入れ調整や仕込み量の見直しに役立ちます。
「なんとなく」で捨てるのではなく、「どうすれば次に活かせるか?」という視点が自然と生まれてきます。
ステップ3:1週間分をまとめて振り返る
1日ごとの記録がたまったら、週末や定休日などのタイミングで、1週間分のロス記録を見返してみましょう。
この“振り返り”こそが、ロス改善のカギです。
振り返りの視点
・よくロスになる食材は何か?(例:キャベツ、パセリなど)
・ロスの出やすい曜日や時間帯は?(例:平日の夜は注文が少ない)
・特定の料理だけ余りがちではないか?(例:日替わりメニュー)
たとえば、「毎週水曜は野菜のロスが多い」「金曜はパスタソースが余りがち」といった店舗ごとの傾向が見えてきます。
この傾向をもとに、次週の仕入れや仕込みを調整することで、ムダのない営業が可能になります。
継続のコツ:完璧を目指さないこと
初めのうちは、記録が抜けてしまったり、原因がよくわからなかったりすることもあると思います。
しかし、それでも構いません。
大切なのは「毎日少しずつでも続けること」です。
忙しい日には、「今日はキャベツが余った」だけでも十分な記録です。
数週間続けていくうちに、自然と精度が上がり、改善点が見えるようになります。
この3ステップを習慣化できれば、高価な管理システムがなくても、立派なロス管理が実現できます。
次章では、手書き・スマホ・PCなど、記録方法のスタイル別におすすめのツールやフォーマットをご紹介いたします。
手書き・LINE・Excel…あなたに合った方法でOK
ロスの記録を始める際、「どんな方法で残せばよいのか?」と悩まれる方も多いかと思います。
ですが、実際には特別なツールやアプリを使わなくても、身近な方法で十分対応できます。
大切なのは、「あなたやスタッフが無理なく続けられる形式を選ぶこと」です。
ここでは、3つのおすすめ記録方法を、それぞれの特徴やメリットとあわせてご紹介します。
● 手書き派におすすめ:厨房内に貼る「ロス記録シート」
「まずは簡単に始めたい」「アナログで管理するのが好き」という方には、紙の記録シートがぴったりです。
あらかじめ表形式で記入欄を作っておき、厨房の壁や冷蔵庫の扉など、スタッフの目に入りやすい場所に貼り付けておくのがポイントです。
メリット
・すぐに書き込めるので、記録の習慣がつきやすい
・書いた内容が現場全員で共有できる
・電源もネット環境も不要で、誰でも使える
活用例
・「食材名」「ロス理由」「日付」の3項目だけのシンプルな構成にする
・スタッフ交代制の店舗でも、引き継ぎしやすくなる
● スマホ派におすすめ:LINEグループや共有メモの活用
スマートフォンを使い慣れている方や、スタッフとの情報共有が多い店舗では、LINEの活用がおすすめです。
LINEのグループ機能や「ノート」「オープンチャット」を使えば、ロス記録をリアルタイムで共有することができます。
メリット
・スタッフが出勤していなくても内容を確認できる
・スマホ1つで記録・閲覧・コメントが可能
・写真付きの記録も簡単に残せる(例:傷んだ食材の写真)
活用例
・毎日営業終了後に「今日のロス」をLINEノートにまとめて投稿
・写真を添付すれば原因の把握もスムーズに
・店主が週末にまとめてロス内容を確認&フィードバック
LINEに限らず、iPhoneの「共有メモ」や、Google Keepなどの無料アプリでも代用可能です。
● デジタル管理派におすすめ:Excelやスプレッドシートでの記録
「数字や傾向をしっかり把握したい」「週ごと・月ごとに集計したい」という方には、ExcelやGoogleスプレッドシートでの記録がおすすめです。
特にロスが多い業態や、仕入れコストが高い食材を扱う店舗では、より細かな管理が利益向上につながります。
メリット
・食材別・曜日別のロス傾向をグラフ化できる
・複数店舗のデータも一元管理できる
・月次の改善報告や経営資料にも活用できる
活用例:
・食材名・数量・原因・曜日を記録し、週ごとに集計
・「よくロスになる食材ランキング」を自動表示
・Googleスプレッドシートを使えば、他スタッフとリアルタイム共有も可能
続けるためのポイント:「現場に合った方法を選ぶこと」
どの方法を使うにしても、重要なのは「無理なく続けられるか」という点です。
高機能でも難しすぎる方法は、スタッフの負担となり、長続きしません。
「まずは紙で簡単に記録→慣れたらスマホやExcelに移行」といったステップアップ方式もおすすめです。
店舗の規模、スタッフ数、ITリテラシーなどに応じて、あなたの現場に合ったやり方で始めてみましょう。
見える化で得られる4つの改善効果
1週間でもロスを記録して「見える化」するだけで、飲食店の現場ではさまざまな前向きな変化が生まれます。
ここでは、実際にロス記録を取り入れた店舗でよく見られる、4つの代表的な改善効果をご紹介いたします。
その1. 仕入れ精度の向上につながります
ロス記録を続けることで、「どの食材が、いつ、どのくらい余りがちか」が明確になります。
すると、これまで感覚や勘に頼っていた発注が、具体的な数値や傾向に基づいた判断へと変わっていきます。
たとえば
・月曜日は来客数が少ないため、葉物野菜の仕入れ量を減らす
・デザート用の果物は週末だけ多めに仕入れるようにする
このように、食材ごと・曜日ごとの仕入れの微調整が可能になり、過剰在庫による廃棄リスクが大幅に減ります。
結果として、仕入れ原価の最適化にもつながります。
その2. メニューや仕込み量の見直しができます
ロスの内容を振り返ると、「注文が少ない料理」「仕込みすぎて残る料理」が浮かび上がってきます。
これをもとに、メニューや仕込みの内容・量を見直すことができるようになります。
たとえば
・週に1~2回しか注文が入らない料理を縮小・改良する
・毎日作っていた副菜を週3回の仕込みに切り替える
・ロスの多い食材を別の料理に転用できるか検討する
このような見直しは、食材ロスだけでなく作業時間の短縮や、調理工程の簡略化にもつながります。
つまり、ロス記録は現場の“負担”を減らすヒントの宝庫でもあるのです。
その3. 作業効率やオペレーションが改善されます
ロスの記録をとることで、「いつ・どの作業でムダが発生しやすいか」も見えてきます。
特に仕込みや盛り付け作業に関するロスは、調理オペレーションそのものを見直す良い機会になります。
たとえば
・盛り付け時に余りがちなソースの量を調整する
・1人前ずつの小分け仕込みに変更して使い切りを徹底する
・ロスの多い時間帯にだけスタッフの動線を変更する
こうした改善により、作業のムダが減るだけでなく、厨房内の“やり直し”や“探し物”といったロスタイムの削減にもつながります。
結果的に、スタッフのストレスも減り、職場環境の改善にも効果があります。
その4. スタッフ全体の意識が高まります
ロスの記録をチームで共有するようにすると、自然とスタッフ一人ひとりの意識が変わってきます。
これまで「なんとなく捨てていたもの」が、「これはもったいない」「次はこうしよう」という前向きな気づきと行動に変わります。
よくある変化
・「この食材、明日なら使い切れそうです」とスタッフから提案が出る
・「この工程で無駄が出やすい」と現場から意見が出るようになる
・ロスが少なかった日をスタッフ同士で共有し、モチベーションアップにつながる
このように、ロスの見える化は経営者だけでなく、現場のスタッフ全員を巻き込んだ改善活動に発展していきます。
小さな意識の変化が、結果としてお店全体の品質向上やコスト削減につながっていくのです。
小さな記録が、大きな成果を生み出します
このように、食材ロスの記録と見える化には、仕入れ・メニュー・作業・人の意識といった幅広い面に好影響を与える力があります。
すべてを一度に完璧に行う必要はありません。
まずは1週間、記録してみるだけでも十分な効果が感じられるはずです。
次の章では、こうした改善効果が実際に出た店舗の具体的な事例をご紹介いたします。
自店にも活かせるヒントが見つかるかもしれませんので、ぜひご覧ください。
成功事例:小さなイタリアンの例
今回は、東京都内で営業されている客席12席の小さなイタリアンレストランの実例をご紹介します。
オーナーシェフが1人で厨房を切り盛りし、ホールはアルバイト1名で回しているという、典型的な少人数営業の個人店です。
「食材ロスは気になっていたけれど、記録なんて忙しくて無理」と感じていたそうですが、たった1枚の手書きシートから始めた取り組みが、大きな改善につながりました。
◆ 導入前の課題
導入前、オーナーシェフが抱えていた悩みは次のようなものでした。
・「週末に備えて仕込んだのに、雨で来客が減って食材が余ってしまう」
・「ワインのおつまみとして用意した前菜があまり出ない」
・「週に1度は、捨てる食材が出るのが当たり前になっていた」
この状態が何カ月も続いていたため、「このままでは利益が出にくい」と危機感を持ち、ロスの見える化に踏み切られたそうです。
◆ 実際の取り組み内容
はじめに行ったのは、「ロス記録シート」を1枚用意し、厨房の冷蔵庫横に貼ることでした。
使い方はとてもシンプルで、以下の3つの情報を毎日営業後に手書きで記入するだけです。
・使い切れずに残った食材の名前
・廃棄した理由(例:仕込みすぎ・傷み・注文が入らなかった など)
・その食材を使ったメニュー名
スタッフにも「全部書かなくていいから、気づいた時にだけでも記録してね」と声をかけ、記録のハードルを下げる工夫をされていました。
◆ たった2週間で見えた“傾向”
この記録を2週間続けたところ、いくつかのロス傾向が明らかになりました。
・平日の来客数は少なく、前菜の仕込み量が多すぎる
・仕込みに使うズッキーニとモッツァレラの使用頻度がメニューによって偏っている
・ワインのおつまみ系の注文が、曜日によってばらつきがある
それまで「なんとなく」感じていた感覚が、「記録」という形で可視化されることで、具体的にどこでムダが出ているのかが明確になったのです。
◆ 取り組み後の改善ポイント
ロス傾向が見えた後、オーナーシェフは以下のような改善を実行しました。
・平日の仕込み量を7割に減らし、週末だけ多めに仕込むように変更
・注文が少なかった前菜メニューを一部改良して、パスタやメイン料理の副菜としても使えるように設計
・在庫になりがちなチーズや野菜を使った“まかない活用レシピ”をスタッフと共有し、廃棄をゼロへ
特に、仕込みの柔軟な調整と“まかない活用”の定着は、オーナーも「やってよかった」と実感されたポイントだったそうです。
◆ 結果として得られた効果
こうした取り組みを約1カ月続けた結果、次のような明確な成果が出ました。
・食材廃棄額が月平均で約30%減少
・食材ロスを意識することで、仕入れ総額も約10%カット
・スタッフからの「この食材、こう使ったらどうですか?」という前向きな提案が増えた
また、ロスの削減により原価率が安定し、売上が急増しなくても利益がしっかり残るようになったため、精神的にも余裕が生まれたとのことです。
小さな工夫で、大きな変化が生まれる
この事例のように、「1枚の手書きシート」という小さなアクションが、ロスの削減だけでなく、仕入れ・仕込み・チームの雰囲気・利益率といった店舗運営全体に良い影響を与えることがあります。
「難しそう」「時間がない」と思っている方こそ、まずは気軽な方法で始めてみてください。
小さな飲食店だからこそ、気づきの一つひとつがダイレクトに数字に表れるという強みがあります。
まとめ:1週間だけでも、やってみる価値ありです
食材ロスの管理というと、つい「面倒そう」「続かなさそう」と感じてしまう方も多いかもしれません。
ですが、今回ご紹介した方法のように、手書きでもスマホでもOKなシンプルな記録から始めれば、思っているよりもずっと気軽に取り組むことができます。
特に、たった1週間だけでもロスを記録して「見える化」することで、現場で何が無駄になっているのか、どこに改善の余地があるのかが自然と見えてきます。
なぜ1週間で効果を実感できるのか?
毎日の営業の中で「余ってしまったもの」や「もったいないと感じた瞬間」を書き出すことで、自分の仕入れ・仕込み・メニューの癖が見えてくるからです。
意識するだけでも「ロスを出さないようにしよう」という気持ちが芽生え、スタッフにも自然とその意識が伝わっていきます。
記録を取っておけば、あとで「この日はなぜロスが多かったのか?」と原因を振り返る材料にもなります。
つまり、たとえ1週間という短期間でも、未来のロス削減や利益改善につながる“きっかけ”が得られるのです。
完璧でなくていい。まずは「続けやすい方法」で、大切なのは、「続けること」ではなく「始めてみること」です。
紙とペンでも、LINEでも、Excelでも、あなたのお店に合った方法でOKです。
そして記録は、すべてを毎日漏れなく書かなくても構いません。
「気づいたときだけ」「余ったときだけ」で十分です。
それでも、徐々に“見えてくるもの”が変わってきます。
小さな一歩が、お店を変える第一歩に
飲食店にとって、食材ロスは“見えにくい赤字”とも言えます。
このロスに気づき、減らしていくことは、お店の利益を守るだけでなく、食品を無駄にしない社会的な価値にもつながります。
「まずは1週間だけやってみよう」そんな軽い気持ちでも大丈夫です。
きっとその1週間が、お店の未来を変えるきっかけになります。
テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。
是非ご活用ください。
業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。
是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
#飲食店 #厨房 #オペレーション改善 #食品ロス #メモ #厨房環境改善 #現場改善 #仕込み #食材見える化 #食材レイアウト #コスト削減


























