食器の数、なんとなくで決めていませんか?
飲食店の開業準備でよくある悩みのひとつが、「食器はどれくらい必要なの?」というものです。
「多めに買っておけば安心」と思って揃えすぎた結果、保管場所が足りなかったり、予算を無駄に使ってしまったりというケースは少なくありません。
逆に、最低限しか用意しなかったことで、ピーク時に洗浄が間に合わず、サービスが回らなくなったという声もよく聞きます。
業務用食器の数は、「見積もって、回して、足りるだけ」が基本です。
この記事では、無駄な出費やオペレーションの混乱を防ぐための考え方と、実際に使える計算方法をご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
業務用食器の「最適数」はどうやって決まるのか?

業務用の食器をどれくらい用意すれば良いかは、店舗の規模や業態によって変わってきます。
しかし、どんなお店であっても、以下のような基本的な要素をもとに考えることで、ある程度の「必要な食器の目安」を導き出すことができます。
席数(店舗の収容人数)
まず基本となるのが、お店に何席あるかという「席数」です。
これは同時にお客様が何人まで入れるかを示す指標であり、食器の使用数のベースになります。
例えば20席の店であれば、最大20人分の食器が必要になるという考え方です。
想定される回転率(1日に何組のお客様が来るか)
次に重要なのが「回転率」です。
回転率とは、1日のうちに同じ席が何回使われるかという数字です。
たとえばランチとディナーでそれぞれ1.5回転、合計で3回転するお店であれば、20席 × 3回転 = 60人分の提供が想定されます。
この回転率は業態や営業時間によって変わってきます。
カフェやラーメン店のように回転が速いお店では1日4~5回転することもありますし、フレンチやコース料理を出す店では1回転または2回転程度になることもあります。
一人あたりの食器使用点数(料理に使う皿やグラスの数)
さらに、お客様一人が利用する食器の「点数」も考慮に入れましょう。
例えば、定食スタイルならプレート1枚・ご飯茶碗・汁椀・箸・グラスで5点程度。
コース料理を提供するお店では、前菜・メイン・デザートで3枚の皿に加え、スプーン・フォーク・ナイフ・ワイングラスなど、7〜9点以上になることも珍しくありません。
洗浄にかかる時間と食器の“回転”効率
意外と見落とされがちですが、「洗浄サイクル」も食器数を決めるうえで非常に重要です。
業務用食洗機の性能や、洗浄・乾燥・片付けまでのスピードによって、1時間に何セットの食器が再利用できるかが変わってきます。
例えば、洗浄に15分かかるなら、1時間で4回、同じ食器を使い回せるということになります。
これを考慮に入れると、すべてのお客様分の食器を用意しなくても、ある程度少ない数でまかなえる可能性があるのです。
このように、業務用食器の「最適数」は単純に「席数 × 人数」だけではなく、
・一日あたりの来客数(回転率)
・一人あたりに必要な食器の点数
・洗浄のサイクル効率(どれくらいの頻度で再利用できるか)
といった複数の要素を掛け合わせて考えることが大切です。
特に開業前は、余裕を見て少し多めに準備しておくのが安心ですが、「数を根拠なく揃える」のではなく、「想定に基づいた必要数」をベースに、少しずつ調整していく考え方が理想的です。
計算式で考える!必要な食器数の目安
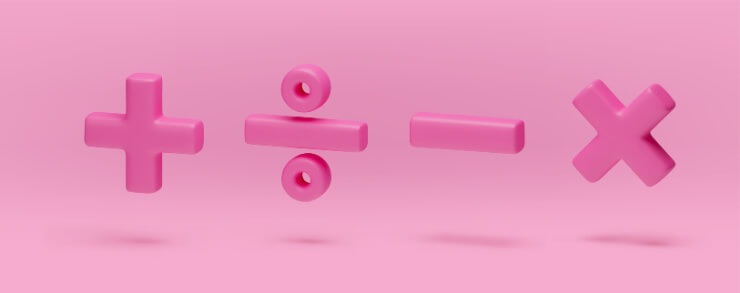
業務用食器の準備において、「なんとなく」で数を決めてしまうと、在庫過多や洗浄の負担、保管スペースの不足など、思わぬ問題を招いてしまいます。
そのため、数値に基づいた目安を持っておくことはとても重要です。
ここでは、業務用食器の必要数をシンプルな計算式で導き出す方法をご紹介します。
店舗の席数や営業スタイルに合わせて応用できる、実用的な考え方です。
~席数と回転率、洗浄時間をもとにした必要数の目安と実践的な計算式~
基本の計算式はこちら
「必要な食器数 = 席数 × 1日の回転数 × 一人あたりの使用食器点数 ÷ 洗浄サイクル効率」
それぞれの項目について、詳しく解説します。
■ 席数(同時にサービスできるお客様の人数)
店舗に設置されている座席数をそのまま使用します。
たとえば20席あれば、同時に20人分の食器が必要となります。
■ 回転数(1日に何組のお客様が入れ替わるか)
昼・夜営業や業態により異なりますが、たとえばランチとディナーでそれぞれ1.5回転、合計で3回転する場合、20席 × 3回転 = 1日60人分の来客を想定します。
■ 一人あたりの使用食器点数(料理ごとに使う皿やカトラリーの数)
提供するメニュー内容によって大きく変わります。
以下は一例です
定食スタイル:プレート、ごはん茶碗、汁椀、箸、グラス → 約5点
カフェ:ケーキ皿、マグカップ、フォーク、スプーン → 約4点
フルコース料理:前菜皿、メイン皿、デザート皿、カトラリー各種、グラス → 7~9点
このように、メニューに合わせて「一人あたり何点使うか」をあらかじめ把握しておくことが大切です。
■ 洗浄サイクル効率(同じ食器を1日何回使いまわせるか)
こちらは、洗浄機の性能や厨房のオペレーションによって異なります。
たとえば、業務用食洗機で1回15分の洗浄ができる場合、1時間で4回転可能となります。
つまり、1日を通して同じ食器を 4回程度使いまわせる可能性があるということです。
■ 計算の具体例
では、実際の店舗を想定して、計算してみましょう。
【想定条件】
席数:20席
回転数:3回(ランチ2回転、ディナー1回転)
一人あたりの食器点数:5点(定食スタイル)
洗浄サイクル効率:1時間に4回(15分で1回転)
【計算式】
20席 × 3回転 × 5点 ÷ 4(洗浄サイクル) = 75点
この場合、75点の食器があれば、営業をスムーズに回せるということになります。
もちろん、予備分や破損・汚れによるロスを見込んで、実際には10~15%程度多めに準備しておくのがおすすめです。
■ カテゴリごとに分けて考えるのもおすすめ
さらに現実的な運用を考えるなら、「プレート」「グラス」「カトラリー」など、カテゴリ別に必要数を計算するのも有効です。
たとえば以下のように分けておくと、管理や買い足しの判断がしやすくなります。
プレート:75枚
グラス:75個
箸・スプーン・フォークなど:それぞれ75本以上
カテゴリごとの使用頻度や破損リスクに応じて、数を調整することで、より無駄のない準備が可能になります。
■ 数値で把握することで見えてくる“適正な備品管理”
食器の数を数字で可視化することで、初期費用の抑制だけでなく、営業中のストレス軽減や洗浄スタッフの負担軽減にもつながります。
特に開業準備中は「なんとなく」で数を決めがちですが、このような実践的な計算式を活用することで、失敗のリスクをぐっと減らすことができます。
業態別の目安:どれくらい必要?

食器の必要数は、店舗の席数や回転率だけでなく、「どんな料理を出すか」「どのような提供スタイルか」といった業態ごとの特徴によっても大きく変わってきます。
ここでは、よくある飲食店のタイプ別に、一人あたりの食器使用点数の目安と、必要数を見積もる際のポイントをご紹介します。
■ 定食屋・食堂スタイル
想定される使用食器:5~6点/人
・ご飯茶碗
・汁椀
・メイン用の皿(またはトレー)
・小鉢1~2皿
・箸
・グラスまたは湯呑み
飯椀 3.3寸飯碗/直径11×H5.3cm/業務用/新品/小物送料対象商品

TW-01 木目スープボウル 小 五客 茶色/業務用/新品/小物送料対象商品

メラミン給食用食器 丸 ランチ皿 3ツ切 新型 No.56 白/業務用/新品/小物送料対象商品

【ポイント】
回転率が比較的高く、ランチタイムに集中する傾向があるため、洗浄サイクルとのバランスを重視しましょう。
忙しい時間帯に備えて、少し多めに準備しておくと安心です。
また、セットメニューが基本なので、「食器をまとめて準備・回収しやすい形」にすることで、運用もスムーズになります。
■ カフェ・軽食スタイル
想定される使用食器:3~5点/人
・ケーキ皿またはサンドイッチ皿
・マグカップ or グラス
・スプーン・フォーク
・(ドリンクが複数の場合は追加のグラスも)
マーブル 16.5ケーキプレートLuzerneNewBone/業務用/新品/小物送料対象商品

VIRGINIACASA いし えん マグカップ /業務用/小物送料対象商品

【ポイント】
食事よりもドリンクやデザート中心となるため、小皿やカップ類の消耗が早い傾向があります。
また、お客様が長時間滞在することも多いため、席数の割に食器の回転が遅くなることも考慮しましょう。
カップやグラスは割れやすいため、予備も多めに準備するのが安心です。
■ ラーメン・麺類専門店
想定される使用食器:3~4点/人
・丼
・レンゲ
・箸
・コップ
中華食器 ラーメン丼 6寸ABSラーメン丼グリーンかすみ /業務用/新品/小物送料対象商品

中華食器(レンゲ) レンゲ(大)/16cm/業務用食器/新品

【ポイント】
非常に回転率が高い業態のため、洗浄スピードの速さが鍵になります。
その分、食器の回転も早く、数を多くそろえなくてもまかなえることが多いですが、ピーク時に備えて1.5~2回転分を確保しておくと、洗浄のタイミングに左右されず安心です。
■ 洋食・ファミリーレストラン
想定される使用食器:6~8点/人
・メインプレート
・スープ皿
・サラダ皿
・ライス皿
・カトラリー(ナイフ・フォーク・スプーン)
・グラス
【ポイント】
品数が多く、さまざまなサイズや形状の皿が必要になります。
料理内容ごとに使う食器を整理して、カテゴリ別に数量を把握しておくと効率的です。
ランチ・ディナーともに利用されるため、1日トータルの食器消費量は多めになります。
アミューズホワイト 23cmプレート/ビュッフェ取皿/業務用/新品/小物送料対象商品

アンセスターホワイト 13深皿/業務用/新品/小物送料対象商品

■ フレンチ・イタリアン(コース料理)
想定される使用食器:9~12点以上/人
・前菜用皿
・パン皿
・メイン用プレート
・デザート皿
・カトラリー一式
・ワイングラス/ウォーターグラス
スパダ 19cm プレート スカンジナビアンブルー /業務用食器/新品

ワイングラス(リゼルバ ボルドー)ボルミオリロッコ 6個入【業務用食器】【飲食店】
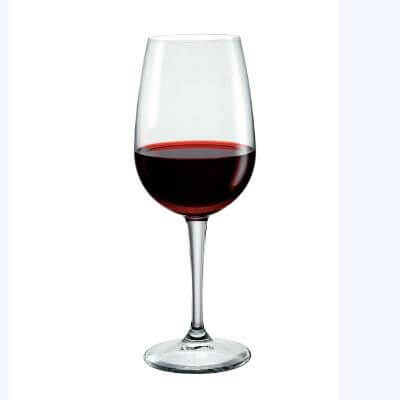
【ポイント】
一人のお客様に対して、多数の食器を使用します。
さらに、同じ種類の皿を違う料理で繰り返し使わないことが多いため、十分な枚数を確保する必要があります。
このような業態では、席数×フルセット分の食器が必要になることも珍しくありません。
また、料理によって異なる演出が求められるため、デザイン性や高級感も重視されます。
■ 居酒屋・小皿料理系
想定される使用食器:5~8点/人
・小鉢・取り皿(複数)
・箸
・グラス(ビール・サワー・水など複数)
・刺身皿、焼き物皿、鍋用食器など
備前金彩 小鉢/M0710/業務用/新品/小物送料対象商品

角渕サビ焼き物皿 19.4×14×2cm 145-028/業務用/新品/小物送料対象商品

【ポイント】
料理をシェアするスタイルが多く、小皿の数が増える傾向があります。
また、お酒に合わせてグラスの種類が多くなるため、ドリンク用の器は多めに用意しておくと回転がスムーズです。
酔ったお客様による破損リスクも高いため、予備を多く持つことが大切です。
実態に合わせて“微調整”するのが理想
上記はあくまで目安ですが、実際の営業スタイルやお客様の行動パターンによって必要数は変動します。
開業前や新メニュー導入時などは、まず最低限の数でスタートし、営業しながら「足りなかった」「これは多すぎた」という感覚を記録しておくと、次回の仕入れや買い替えの参考になります。
必要以上に用意すればコストがかさみ、逆に少なすぎれば現場が混乱します。
業態に合ったバランスの良い食器数の見極めが、スムーズな店舗運営のカギになります。
気になる方は、自店舗の営業スタイルに合わせて、一度シミュレーションしてみることをおすすめします。
買いすぎ・洗いすぎを防ぐポイント
業務用食器は、一度に大量に購入するとコストがかさみますし、過剰に揃えても使いきれず、保管場所を圧迫したり、在庫管理の手間が増えたりする原因になります。
一方で、数が足りなければ、営業中に「洗い待ち」が発生してしまい、厨房スタッフに負担がかかるほか、提供スピードの低下やオペレーションミスにもつながりかねません。
ここでは、こうした「買いすぎ」「洗いすぎ」のムダを防ぐための、実践的なポイントを詳しくご紹介します。
■ 最初は“最小構成”+αでスタートする
開業や新メニュー導入時には、最初から完璧を目指そうとせず、最低限必要な構成でスタートすることをおすすめします。
特に初期は来客数や注文傾向が予想とズレることも多いため、必要最低限に加え、10〜20%程度の予備を持っておく程度が理想的です。
運用を始めたあとに、「〇曜日のランチはこれが足りなくなりがち」など、実際の使用状況を把握してから、段階的に買い足すとムダがありません。
■ 「洗浄サイクル」を前提に考える
一度使った食器をどれくらいのペースで再利用できるか(=洗浄サイクル)を把握しておくことで、少ない枚数でも効率よく回す工夫ができます。
たとえば、業務用食洗機が1回15分で回る場合、ピーク時に1時間で4回洗えるとすれば、1セットの食器を最大4回活用できることになります。
これを前提に必要数を逆算すれば、最初に揃える数を抑えることができます。
洗浄担当の人数や、機器の能力・配置によっても実働は変わるため、現場のオペレーションと合わせて試算することが重要です。
■ 汎用性のある食器を優先する
メニューごとに個別の食器を揃えたくなる気持ちはありますが、実際の現場では、1枚で複数用途に使える食器が重宝されます。
たとえば、少し大きめの丸皿であれば、「前菜」「パスタ」「サンドイッチ」など、メニューをまたいで使用できます。
特定の料理専用の器は、出数が限られると出番が少なく、結果としてスペースを圧迫する原因になりがちです。
多用途に使える形・サイズ・デザインを優先して選ぶことで、品数を減らしても運用に支障が出にくくなります。
■ 破損・紛失のリスクを見込んでおく
飲食店では、どんなに丁寧に扱っていても、落下・ヒビ・欠けなどによる破損は避けられないものです。
特にピーク時の慌ただしい場面では、うっかり事故も起こりやすくなります。
そのため、実運用では「必要数+10~15%」を目安に、あらかじめロス分を含めて準備しておくと安心です。
また、カトラリーやグラスは、お客様の持ち帰りや紛失が起こることもあるため、こまめに数をチェックし、定期的に補充する体制を整えておくと、安定した営業が可能になります。
■ 定期的に“使っていない食器”を見直す
店舗運営を続けていると、メニューの変更や出数の変化に伴い、「使わなくなったけどなんとなく残っている食器」が出てくることがあります。
このような食器は、収納スペースを圧迫し、日々の作業効率を低下させる原因にもなります。
定期的に棚卸しを行い、「直近1カ月間に使用した食器」「まったく使っていない食器」を棚単位で分けて、必要ないものは保管庫に移す・処分する・リサイクルに出すなどの対応を検討しましょう。
「数」だけでなく「使いやすさ」「管理しやすさ」も重視を
食器の数を管理するうえで大切なのは、単に「多すぎない・少なすぎない」というだけでなく、いかに運用しやすい状態を作れるかです。
数を絞る場合も、スタッフが迷わずに配置・使用・回収できるか、予備の場所はすぐに取り出せるかなど、現場の動線・管理体制を意識した選定が欠かせません。
初期費用のムダを抑えつつ、洗浄や配膳の負担も減らせるように、ぜひこうしたポイントを参考にしながら、食器の準備を進めてみてください。
保管スペースと動線も一緒に考えよう
業務用食器を選ぶ際、どうしても「デザイン」や「数」の話に意識が向きがちになります。
しかし、実際の店舗運営で見落とされやすいのが、「収納スペース」と「動線」の設計」です。
どれだけ適正な数の食器を用意していても、保管場所が不便だったり、取り出しにくかったりすれば、現場でのオペレーションが滞り、作業効率が落ちてしまう原因になります。
以下のポイントをおさえて、使いやすい環境を整えましょう。
■ 食器の「使用頻度」に応じて収納場所を分ける
食器を収納する際は、よく使うものほど「出しやすい・戻しやすい場所」に保管することが基本です。
たとえば
毎日使う食器
スタッフの腰〜胸の高さの位置(最も出し入れしやすい)
週に数回しか使わないもの
棚の上段や下段
季節メニュー専用の器
別の倉庫やバックヤードに保管
といったように、使用頻度に応じたゾーニングを意識すると、作業時間のロスを最小限に抑えることができます。
■ 配膳と洗浄の動線に沿った配置にする
食器は、「出す」と「しまう」を繰り返すものです。
したがって、配膳(キッチン→ホール)と回収・洗浄(ホール→洗い場)の動線がスムーズであることが重要です。
たとえば
盛り付け直前に必要な皿
キッチン内の手元に配置
ドリンク用のグラス
ドリンクサーバーのすぐ横
回収した食器
洗浄エリアの近くにまとめて保管
このように、作業の流れに沿った配置を意識することで、移動距離を減らし、スタッフの負担も軽減されます。
また、動線を邪魔しない収納棚の高さや開閉のしやすさなども、実際の作業環境に合わせて工夫することが大切です。
■ 数が多くなる場合は「専用ラック」や「仕切り」を活用
食器の種類が多くなると、棚の中がごちゃつきやすく、目的の皿がすぐに見つからない・取り出しにくいという問題が発生します。
これを防ぐためには、以下のような対策が有効です。
・仕切り付きの専用ラックやバットで、種類ごとに区分け
・食器の縦置き収納(プレートスタンド)で省スペース化
・カトラリーやグラス類は、カゴやトレーでグループ管理
とくにピークタイムは一秒の遅れがストレスになるため、「どこに何があるかがひと目でわかる」「片手でも取り出せる」工夫が求められます。
■ 「ストック分」の収納場所もあらかじめ確保しておく
開業時は気がつかないことも多いですが、営業が進むにつれて食器の破損や摩耗が起こり、買い足しや予備品の保管スペースが必要になります。
その際に収納場所が確保されていないと、バックヤードに積み上げることになり、衛生面や安全性のリスクが高まることも。
あらかじめ「予備を保管しておくスペース」や、「季節商品用の器をしまう棚」などを想定しておくことで、長期的に見て効率の良い食器管理が可能になります。
オペレーションの快適さは収納設計で決まる
飲食店においては、「いかに料理を早く・正確に提供できるか」が満足度を左右する重要な要素です。
そのため、食器の“数”以上に“配置”や“取り回しやすさ”が、現場のスムーズな運営に大きく影響します。
ぜひ、厨房やホールの動きに合わせて、「最小の労力で、最大限に回せる食器の収納と動線」を考えてみてください。
将来のメニュー変更や繁忙期にも柔軟に対応できるよう、定期的に見直すことも忘れずに行いましょう。
まとめ:最適な数で“効率”と“清潔”を両立
業務用食器の数を決める際に大切なのは、「多ければ安心」「少なければ節約」という単純な考え方ではなく、実際の営業スタイルやオペレーションとのバランスを見極めることです。
たとえば、ランチとディナーのどちらが中心か、1時間あたりの席の回転数はどれくらいか、食洗機は何分で回せるのか——といった情報をもとに、洗浄サイクルや必要数を具体的に計算することで、ムダのない数を導き出すことが可能です。
また、適切な食器数を維持することで、洗い物の山に追われることが減り、スタッフのストレスや労力を軽減できます。さらに、常に清潔な食器をお客様に提供し続けるための余裕も生まれますので、「効率」と「衛生」の両立という大きなメリットが得られるのです。
ただし、食器は数だけでなく、使い勝手・汎用性・収納性・管理のしやすさといった点も非常に重要です。
形状やサイズをそろえておけば、収納もしやすく、忙しい時間帯の配膳ミスも減らせます。
逆に、特殊な器や管理しにくい形状ばかり揃えると、効率が落ちてしまいます。
さらに、破損や紛失といった「予期せぬロス」も前提にしておくことで、いざという時に慌てずに済みます。
つまり、業務用食器の数は「今、足りているかどうか」ではなく、「どれだけスムーズに回せるか」「現場が無理なく使い続けられるか」を基準に考えるのがポイントです。
店舗の運営状況に応じて、定期的に見直しを行いながら、必要最小限で最大の効果を生む食器運用を心がけていきましょう。
それが結果として、お客様の満足度や店舗全体の生産性を高めることにもつながります。
テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。
是非ご活用ください。
業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。
是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
#飲食店 #厨房 #食器 #食器の数 #最適数 #計算式 #業態別の目安 #保管スペース #効率 #清潔 #使いやすさ #管理しやすさ


























