飲食店経営において、今や「人が辞めないこと」は最重要課題のひとつとなっています。
とくに厨房スタッフの離職は、営業への影響が大きく、現場の負担も一気に増えてしまいます。
「人間関係が悪かったのかな?」「給料が低すぎたのか?」といった理由も確かにあるでしょう。
しかし実際には、“暑すぎる厨房”や“毎日バタバタするオペレーション”など、設備と仕組みのストレスが原因で辞めてしまうケースも少なくありません。
裏を返せば、「働きやすい厨房の仕組み」を整えることで、スタッフが長く定着する環境をつくることができるのです。
本記事では、見落とされがちな厨房の“地味だけど効く”改善ポイントを、「設備」と「オペレーション」の視点から紹介していきます。
人材に悩む飲食店経営者の方や、開業前に準備しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
厨房スタッフの離職、実は「仕組み」で防げる?
飲食店の現場では、「スタッフがなかなか定着しない」という悩みを抱える方が多いのではないでしょうか。
特に厨房スタッフは、ホールと違って外から見えにくいぶん、負担や不満が表に出づらく、気がついたら突然辞めてしまうというケースも少なくありません。
一般的に、離職の原因としてよく挙げられるのは「給与が安い」「人間関係が悪い」「労働時間が長すぎる」などですが、実際に現場を見ていると、それ以外にも見落とされがちな理由がいくつも存在します。
たとえば、以下のような“日常の小さなストレス”が蓄積しているケースです。
・毎日、厨房内が蒸し風呂のように暑い
・仕込み作業の負担が大きく、いつも1人だけ残業している
・必要な調理道具がすぐ見つからず、探すたびにイライラする
・誰にも相談できず、声をかけづらい雰囲気になっている
こうした問題は、一見すると「人の性格ややる気」のせいのようにも見えますが、実は“仕組み”で解決できるものばかりです。
たとえば、厨房の換気設備や道具の収納場所、オペレーション手順の見直し、スタッフ同士の声かけのタイミングづくりなど、少しの工夫で環境は大きく変わります。
しかも、こうした改善は一度やってしまえば効果が長く続くため、離職防止だけでなく、新人教育の負担軽減や、職場の雰囲気向上にもつながっていきます。
「人がすぐ辞めるのは仕方ない」と諦める前に、まずは厨房内の“仕組み”に目を向けてみることが、これからの飲食店経営にとってとても重要なのです。
「夏が地獄」な厨房を改善する換気と導線の工夫

厨房スタッフの離職理由として、実は見逃されがちなのが「暑さとムレ」です。
特に真夏のピークタイムになると、厨房内の温度は簡単に30度を超え、場合によっては35度以上になることもあります。
汗をかきながら火の前に立ち続けるのは、体力的にも精神的にも相当な負担で、「もう限界…」と退職を決断する大きな要因になります。
▷ 換気・送風設備の見直しが第一歩
まず見直したいのは、厨房内の換気と空気の流れです。
業務用の換気フードがあっても、うまく排熱されていない場合は、熱がこもってしまいます。
フードのフィルターが汚れている、吸気と排気のバランスが悪いなど、見落とされがちなポイントを定期的に点検することが大切です。
また、スポットクーラーやサーキュレーターを活用して、「火の前で作業する場所だけでも風が当たる」ようにする工夫も有効です。
意外と低コストで導入できるので、設備投資が難しい場合でも試しやすい対策です。
▷ 導線の工夫で“暑さの滞留”を防ぐ
もう一つ見逃せないのが、人と熱の「流れ」を意識した導線の見直しです。
調理中に何度も同じ場所を行き来したり、狭いスペースにスタッフが密集したりしてしまうと、体感温度はさらに上がります。
可能であれば、「作業ステップごとにポジションを分ける」導線設計や、「一方通行の流れ」にすることで、厨房内の温度ムラや人の滞留を減らすことができます。
特に調理場と洗い場の動線が重なるようなレイアウトは、スタッフのストレスにも直結します。
▷ 小さな対策でも“辞めにくい職場”へ
「冷房が効かない厨房は仕方ない」とあきらめている店舗もありますが、実際にはちょっとした改善で「ここは働きやすい」と感じてもらえる環境はつくれます。
スタッフが少しでも快適に働けるようにすることは、離職を防ぐだけでなく、集中力やパフォーマンス向上にもつながります。
結果としてミスやロスが減り、店舗全体の利益にも貢献するのです。
「厨房が暑すぎる」は、放っておくと確実に“辞めたくなる職場”につながってしまいます。
今こそ、空気と人の流れを見直すことから始めてみませんか?
「1人でも回せる」仕込みの工程を整える
飲食店の厨房業務の中で、もっとも時間と手間がかかるのが「仕込み」です。
開店前や営業終了後に行われることが多く、場合によってはスタッフが1人で黙々と作業することもあります。
その結果、毎日のように残業が発生したり、「自分ばかり負担が大きい」と感じたりして辞めてしまうケースも少なくありません。
ですが実は、「1人でもスムーズに仕込みができる工程設計」をしておくことで、そうした負担を大幅に減らすことが可能です。
▷ 工程の「分解」と「順序立て」がカギ
まず取り組みたいのは、仕込み作業の分解と見える化です。
たとえば、
・野菜のカット
・タレやソースの仕込み
・肉や魚の下処理
・デザートの仕込み
といった工程をそれぞれ棚卸しし、「どの作業を、誰が、どのタイミングでやるのが効率的か」を整理します。
また、作業ごとの所要時間や保存可能時間も記録しておくと、「前日にここまで終わらせておける」「冷蔵庫にストックできる」など、効率的な分担がしやすくなります。
▷ “同時進行できる流れ”をつくる
1人で作業する前提であれば、「作業を待たせない流れ」を意識して構成することがポイントです。
たとえば、スープを煮込んでいる間に野菜を切る、冷却中に洗い物を進める、など“空き時間をムダにしない配置”を意識すると、作業効率がぐっと上がります。
作業台や冷蔵庫の配置も重要で、「毎回2〜3歩で届く」「取り出しやすく戻しやすい」といったレイアウトにすることで、1人での仕込みが格段にラクになります。
▷ マニュアル化と“見える化”で属人化を防ぐ
また、仕込みの工程は「ベテランしか分からない」「〇〇さんがいないと回らない」といった属人化が起こりがちです。
これを防ぐためには、「誰でもできるようにマニュアル化すること」が重要です。
手順を写真つきでまとめる、動画で残すなど、視覚的なツールがあると新人でも安心です。
さらに、ホワイトボードや共有シートなどを活用して、「今日やるべき仕込みリスト」を見えるところに掲示することで、作業漏れや伝達ミスを防ぐこともできます。
仕込み作業がスムーズに進むだけで、厨房スタッフの気持ちはぐっと軽くなります。
「自分ばかり大変」と感じる場面が減り、「この職場なら続けられる」と思ってもらえる第一歩になります。
厨房における「1人で回せる仕組み」は、離職率を下げるだけでなく、人手不足の時代を乗り切る大きな武器にもなるのです。
フードプロセッサーがあれば、切ったり混ぜたりさまざまな作業が一台で可能なので、食材の下準備が簡単になります。
「道具の置き場」こそ離職率に効く改善ポイント
厨房の中で「辞めたくなる原因」は、実は大きな出来事よりも、日々の小さなストレスの積み重ねによって生まれることが多いです。
その中でも意外に多いのが、「あの道具どこ?」「いつも物がゴチャゴチャしている」といった道具の収納ストレスです。
調理中に必要な器具や調味料がすぐ見つからず、イライラした経験はありませんか?
これは、作業効率を下げるだけでなく、スタッフの精神的な負担を増やし、結果的に「働きにくい職場」という印象につながってしまいます。
▷ すぐ取れる、すぐ戻せる配置をつくる
まず目指したいのは、「定位置管理」の徹底です。
「まな板はここ」「フライパンはこのフックに」「ラップや計量器具はこの引き出しに」と、使う頻度や場所に応じて道具の“あるべき場所”を明確にすることが大切です。
さらに、「すぐに取れて、使い終わったらサッと戻せる」位置にあることも重要です。
高さ、距離、動線に無理があると、どうしても片付けが後回しになり、散らかっていきます。
たとえば、調理台の下に小型のツールワゴンを設置したり、磁石付きのラックを冷蔵庫横に取り付けたりするだけでも、使いやすさは格段にアップします。
▷ “見せる収納”で作業効率と美観を両立
最近では、あえて道具を“見せる収納”にして、どこに何があるか一目で分かるスタイルも注目されています。
壁掛けフックやツールスタンドを使えば、省スペースで整理整頓ができ、探す時間も減ります。
特に新人スタッフにとっては、道具の場所を聞かずに分かることで、自信を持って作業に入れるというメリットもあります。
▷ 収納改善は「新人が辞めない厨房」への第一歩
道具の置き場が毎日バラバラだったり、「〇〇さんしか知らない配置」になっていたりすると、どうしても職場に属人性が生まれます。
新人スタッフが入っても、道具のありかが分からずオドオドしてしまったり、先輩に叱られて自信を失ってしまったりすることがあります。
逆に言えば、「道具が整っていて分かりやすい厨房」は、それだけで「居心地が良い」「自分にもできる」と思ってもらえるきっかけになります。
小さなことのように思えますが、道具の置き場を整えることは、毎日の働きやすさをつくる“土台”になります。
片付けやすく、探さなくていい厨房は、自然にチームワークも良くなり、離職率を下げる大きな支えとなるのです。
オペレーションに「会話」を仕込むと人は辞めにくくなる
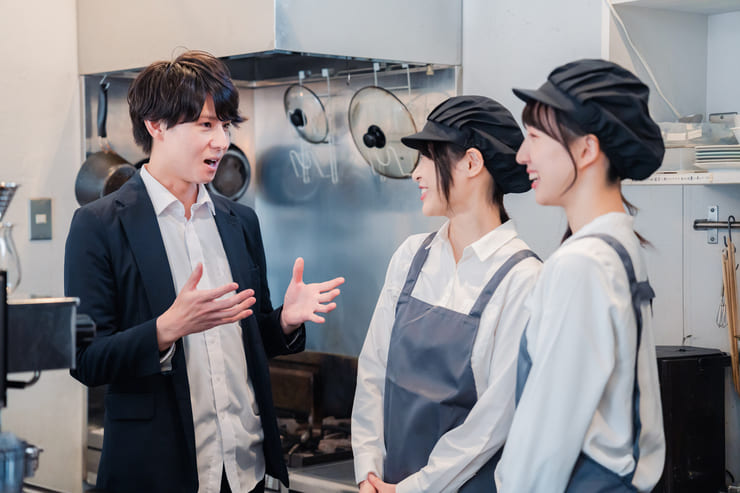
飲食店の厨房では、「いかに無駄なくスムーズに作業を進めるか」が日々の課題です。
そのため、オペレーションの設計は“効率重視”になりがちですが、実はそこに「ちょっとした会話」の余白を意識的に組み込むことで、スタッフの定着率が大きく変わることがあります。
仕事中の雑談は、必ずしも無駄ではありません。
むしろ、“ちょっと話せる空気”がある厨房は、孤立や緊張が生まれにくくなり、人が辞めにくくなる職場へと変わっていきます。
▷ 厨房は「黙々と働く場所」になりやすい
厨房はスペースも限られており、機械音や熱気などもあって、自然と無言で作業しがちです。
とくにピークタイムは、声をかける余裕がなくなるため、新人や不慣れなスタッフが孤立しやすくなる環境でもあります。
「誰とも話さずに数時間が過ぎた」「質問したくてもタイミングがない」という状態が続くと、スタッフは精神的に疲弊し、「自分はここにいていいのか」と不安を抱くようになります。
▷ 会話を“業務に組み込む”という発想
そこで有効なのが、“雑談”ではなく“軽い会話”をあらかじめオペレーションに組み込む”という考え方です。
たとえば以下のような声がけです
「今日のスープ、味見してくれる?」
「あと5分でピーク来そうだね、がんばろう」
「この切り方、前より早くなっているね」
こうした短いやりとりが、スタッフ間の距離を縮める大きなきっかけになります。
特に新人にとっては、「話しかけてくれた」というだけで安心感が生まれ、「この職場は冷たくない」と感じられるのです。
▷ コミュニケーションがオペを円滑にする
実は、オペレーション上のミスや非効率の多くは、情報共有不足や思い込みによる勘違いから起こります。
そのため、軽い会話がある厨房は、「伝え忘れ」や「気まずい空気」が減り、結果的にトラブルの少ない、滑らかな現場になります。
また、スタッフ同士の信頼関係ができてくると、「次どう動くか」が自然と読める空気感が育ち、全体のオペレーションも向上します。
▷ 「ありがとう」「ナイス!」が空気を変える
そして何より大切なのが、感謝や評価の一言です。
「ありがとう」「助かったよ」「今の対応、ナイスだったね」などの言葉は、どんなマニュアルやマシンよりも、モチベーションを生みます。
厨房内でのこうした小さな承認が、「自分はここで必要とされている」と感じる力となり、離職を防ぐ大きな要因になります。
オペレーションに効率だけでなく「会話の余白」を意識して取り入れることで、働く人の気持ちは格段にラクになります。
厨房をただの作業場にせず、人が育ち、人が残るチームの場へと変えていく――その第一歩は、ほんの一言の声がけから始まるのです。
スタッフが「言える」職場にするミーティング文化の作り方

厨房スタッフの定着率を上げるためには、設備やオペレーションの整備も重要ですが、それと同じくらい大切なのが「心理的な安心感」です。
中でも、スタッフが安心して「意見を言える」「困っていると伝えられる」環境をつくるには、日常的なミーティング文化の構築が非常に効果的です。
▷ 言いにくい雰囲気が“辞めたくなる”気持ちに
飲食店の現場では、「忙しすぎて話せない」「上の人が怖くて言えない」といった空気が当たり前になっているケースも少なくありません。
こうした環境では、ミスや不安を抱えても言い出せず、ストレスを抱えたまま働き続けることになります。
やがて「もう無理かも…」という気持ちが限界を迎え、離職につながってしまうことは珍しくありません。
▷ 雑談レベルでいい、ゆるい“ミーティング習慣”を
ここで重要なのは、「毎週しっかり会議を開く」ような堅いものではなく、ちょっとした“声かけミーティング”を日常に溶け込ませることです。
たとえば、
・営業終了後に5分だけ、「今日どうだった?」と感想を聞く
・仕込み前に、「今、何か困ってることある?」と尋ねる
・週に1回、厨房ホワイトボードに「ひとこと掲示板」を設けて、気になることを自由に書いてもらう
こうした“軽い対話の場”を定期的に持つことが、スタッフにとっては「聞いてもらえる」「言っても大丈夫」という安心感につながります。
▷ 否定しない姿勢が「発言する勇気」を育てる
せっかく意見を出しても、「そんなのムリだよ」「前にもやったけどダメだったから」といった言葉で否定されてしまうと、スタッフは次第に口を閉ざすようになります。
まずは、「言ってくれてありがとう」と受け止めること。
その上で、「それはどうやったら実現できるか一緒に考えよう」と建設的な姿勢を見せることで、スタッフは安心して発言できるようになります。
▷ 「一緒に考える」がチームの文化になる
ミーティングの場で全てを即決する必要はありません。
むしろ「そのアイデア、ちょっとみんなにも聞いてみようか」とチーム全体で考える雰囲気をつくることで、スタッフ同士の関係も良くなり、「自分も店づくりに参加している」という実感が生まれます。
これは、単なる労働者ではなく、“メンバー”としての意識を育てる大きな要素になります。
▷ 声が届く職場に、人は残ります
スタッフが自分の考えを言える環境には、以下のような効果があります
・小さなストレスの早期発見と改善
・モチベーションの向上
・チームへの帰属意識の強化
・リーダー層の育成(発言の練習機会)
そして何よりも、「この店は、自分の声が届く」と感じられることが、離職を防ぎ、長く働きたいと思える理由になります。
厨房という忙しくストレスの多い現場だからこそ、意図的に“話せる場”を仕込む工夫が求められます。
ミーティングというと構えてしまいがちですが、あくまで日々の雑談に近いスタイルで、“対話の習慣”を作っていくことがポイントです。
離職しにくい厨房の共通点とは?
「なかなか人が定着しない」「入ってもすぐ辞めてしまう」
このような悩みを抱える飲食店経営者の方は少なくありません。
しかし、全国には同じような人材難の時代にあっても、離職が極端に少ない厨房が確かに存在します。
その違いは、「給料」や「シフトの柔軟さ」だけではなく、現場の“仕組み”や“空気感”にあります。
▷ 離職しにくい厨房は「整って」いる
まず大きな共通点は、厨房の中が物理的にも、精神的にも「整っている」ということです。
・導線がシンプルで、無駄な移動や待機が少ない
・道具の配置が分かりやすく、片付けやすい
・仕事の手順が明文化され、誰でも迷わず作業できる
・知らないことを聞きやすい雰囲気がある
このような「小さな整備」の積み重ねが、働きやすさと心理的安全性を高め、結果として定着率につながっているのです。
▷ 「属人化」を防いでいる
離職率が低い厨房は、特定の人しか分からないオペレーションや感覚的な指示に頼らず、仕組みによる運営がされています。
・「〇〇さんじゃないとできない作業」がない
・手順書やチェックリストがある
・誰がいても一定レベルで回る
こうした体制を整えることで、新人でも迷わず働けるようになり、現場の「ギスギス感」が生まれにくくなります。
▷「相談できる」文化がある
離職が少ない厨房には、共通して「小さな不満や困りごとを話せる空気感」があります。
たとえば…
・シフトの相談がしやすい
・「こうしたらやりやすいかも」といった意見を言える
・体調不良のときに休みを言いやすい
このような「言いやすさ」は、スタッフ同士の関係性や、経営者・店長の姿勢から生まれるものです。
特に忙しい厨房ほど、「声をかける時間」が後回しになりがちですが、意識してコミュニケーションの機会をつくることで、大きな違いが生まれます。
▷「育成に投資」している
スタッフが成長を実感できる環境も、離職を防ぐ重要な要素です。
離職しにくい厨房は…
・一つずつ仕事を覚えられる育成フローがある
・できるようになったことを認めてもらえる
・新しいポジションや役割への挑戦ができる
など、「ここにいれば、自分は成長できる」と思える場づくりが意識されています。
育成には時間がかかりますが、その分“次の人を何度も採用・教育し直す”という手間とコストを防げるのです。
▷ 「辞めにくい」ではなく「続けたくなる」職場へ
最後に強調したいのは、「辞めにくさ」ではなく「続けたくなる理由」を増やすことが、真の意味での離職対策になるということです。
続けたくなる厨房は、以下のような要素を持っています。
・清潔で整った物理環境
・無理のないオペレーション
・声をかけやすい人間関係
・自分の意見が受け入れられる余地
・少しずつ成長を感じられるしくみ
こうした要素を、意識的に少しずつ積み上げていくことが、結果的に「人が辞めない厨房」を実現します。
離職率を下げる特効薬はありませんが、「現場を見直すこと」からスタートすれば、確実に変化は起こります。
毎日の積み重ねが、スタッフにとっての“居心地の良い場所”をつくっていくのです。
まとめ:離職対策は、派手な改革より“地味な仕組み”にこそ効果あり
離職対策において重要なのは、大きな制度変更や目を引く改革だけではありません。
実際には、毎日の現場で少しずつ改善を重ねる“地味な仕組み”のほうが、長期的に見て大きな効果を生み出します。
例えば、スタッフ同士のコミュニケーションを促進する仕組みや、仕事の負担を均等に分けるルールづくり、そして働きやすい環境づくりといった細かな取り組みは、スタッフの満足度を高め、離職の防止につながります。
こうした日々の積み重ねが、スタッフの信頼関係を強化し、安心して働ける職場環境を作り出します。
結果として、スタッフは仕事に対して前向きな気持ちを持ちやすくなり、離職率の低下へとつながるのです。
つまり、スタッフの気持ちに寄り添った継続的な改善こそが、最も効果的な離職対策だと言えます。
ですから、派手な改革にこだわらず、小さな仕組みづくりを丁寧に行うことが、結果的にスタッフの定着率を高め、安定した店舗運営を支える大きな力になるのです。
テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。
是非ご活用ください。
業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。
是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
#飲食店 #厨房 #オペレーション #離職を防ぐ #定着率UP #スピードと効率
#冷房 #会話 #効率的な導線 #道具の配置 #モチベーション向上


























