「銀杏(ぎんなん)」は、秋の味覚として親しまれている食材ですが、果物なのか野菜なのか迷う方も多いのではないでしょうか。
銀杏は、イチョウの木になる「種子」であり、果物ではありません。
独特のほろ苦さと香りを持ち、炒め物や茶碗蒸しなど和食に欠かせない存在です。
他にも、銀杏を活用した料理はどのようなものがあげられるのでしょうか。
今回は、銀杏は果物なのか?特徴やおすすめ料理について紹介していきます。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
銀杏を食べる習慣はいつから始まった?

銀杏を食べる習慣は、中国から日本へと伝わった歴史の中で根付いていったと考えられています。
イチョウ自体は、約2億年前から存在するとされる「生きた化石」ですが、人がその種子を食用に利用し始めたのは古代中国からです。
中国では、少なくとも宋の時代(10〜13世紀)には薬用や、食材として銀杏が記録に残っており、滋養強壮や咳止めとして珍重されていました。
日本には、室町時代に伝わったとされ、当初は寺院や大名庭園などで観賞用に植えられ、その実である銀杏も次第に食べられるようになりました。
江戸時代に入ると、銀杏は庶民の食文化にも広がり、焼き銀杏や茶碗蒸しの具材として親しまれるようになりました。
秋になると、街路樹として色づくイチョウの木から実を拾い、旬の味覚として楽しむ習慣もこの頃に定着したと言われています。
独特の苦味や、香りを持ちながらも、塩で炒ったり蒸したりすると「ホクホク」した食感と甘みが引き立ち、日本人にとって秋を象徴する味の一つとなりました。
こうした歴史を経て、銀杏は今もなお、四季の移ろいを感じさせる伝統的な食材として食卓に欠かせない存在となっているのです。
銀杏の特徴
独特のほろ苦さと香りを持っている銀杏ですが、いったいどのような特徴を持っているのでしょうか。
ここでは、銀杏の特徴について紹介していきます。
主に以下の特徴があげられます。
種子であって果物ではない
銀杏は、「果物」と思われがちですが、実際にはイチョウの木になる「種子」です。
イチョウは、裸子植物であり、果実をつける被子植物とは異なります。そのため、銀杏は果実ではなく、硬い殻に包まれた種にあたります。
外側の果肉状の部分は、強い臭いを放つため食用にはせず、中の種子を調理して食べます。
このユニークな分類が、銀杏をほかの木の実やナッツ類とは一線を画す特徴となっているのです。
独特の風味と食感
銀杏の最大の魅力は、他の食材にはないほろ苦さと、「ホクホク」しながらも「ねっとり」とした食感です。
炒るとほのかな甘みが引き立ち、加熱するほど香ばしさも増していきます。苦みは、大人向けの味覚として酒の肴に好まれる一方、茶碗蒸しや炊き込みご飯に加えると、料理全体に深みを与えます。
この独特の風味こそが、秋の味覚として古くから愛されてきた理由です。
栄養価と薬膳的効果
銀杏は、ビタミンC、カリウム、鉄分などを含み、滋養強壮や疲労回復に効果があると言われています。
また、古くから漢方や薬膳料理に用いられ、咳止めや呼吸器系の改善によいと伝えられています。
ただし、アミグダリンという成分が分解されると青酸を発生するため、大量に食べると中毒症状を起こす恐れがあります。
適量を守って楽しむことが、銀杏を安心して食べるための大切なポイントです。
季節感と文化的価値
銀杏は、秋の風物詩として、日本の食文化や景観に深く根付いています。街路樹のイチョウ並木が黄色に色づく頃、銀杏拾いを楽しむ人々の姿は秋の風景の一部です。
さらに、茶の湯や懐石料理では、秋らしさを表現する食材として欠かせない存在となっています。
銀杏の鮮やかな緑色は料理に彩りを添え、食材としてだけでなく、季節を感じさせる「文化的なシンボル」としての役割も果たしています。
このように、銀杏は単なる食材にとどまらず、植物学的な特異性、独自の風味、栄養効果、そして文化的価値を併せ持つ、非常に多面的な特徴を持った秋の味覚なのです。
銀杏を活用したおすすめ料理

銀杏は、炒め物や茶碗蒸しといった料理に使われています。
ここでは、銀杏を活用したおすすめ料理について紹介していきます。
主に以下のおすすめ料理があげられます。
焼き銀杏
もっともシンプルでありながら、銀杏本来の風味を存分に味わえるのが「焼き銀杏」です。
殻付きのままフライパンや、専用の銀杏焼き器で炒ると、「パチパチ」とはじけて殻が割れ、中から鮮やかな黄緑色の実が顔を出します。
殻をむいて軽く塩を振ると、「ホクホク」とした食感とほろ苦さ、そして香ばしい香りが口いっぱいに広がります。
ビールや、日本酒との相性が抜群で、居酒屋では定番の秋のつまみとして人気です。
調理法がシンプルな分、素材の質が味に直結し、銀杏の持つ独特のうまみをダイレクトに堪能できます。
茶碗蒸し
和食における銀杏の代表的な使い方が「茶碗蒸し」です。なめらかな卵液の中に、忍ばせた銀杏は、口に運んだ瞬間に「ほっくり」とした食感と独特の苦みが広がり、優しい味わいの出汁と調和します。
しいたけや鶏肉、かまぼこなどと並び、銀杏は茶碗蒸しに欠かせない具材のひとつとされています。
特に、秋から冬にかけての季節感を表現する食材として重宝され、懐石料理や家庭の食卓でも喜ばれる存在です。
見た目にも彩りを添え、料理全体の完成度を高めてくれる点が魅力です。
銀杏ご飯
「銀杏ご飯」は、銀杏の香りと味を存分に楽しめる家庭料理の代表です。下処理した銀杏を炊き込みご飯に加えるだけで、「ホクホク」とした食感がご飯にアクセントを与え、噛むほどに独特のうまみと甘みが広がります。
塩や薄口しょうゆで、シンプルに味付けすれば、銀杏の個性が引き立ち、秋らしい滋味深い一品に仕上がります。
また、きのこや鶏肉と組み合わせることで、さらに風味豊かな炊き込みご飯となり、食卓を豪華に彩ります。
冷めてもおいしいため、お弁当にも活用できるのが魅力です。
このように、焼いてそのまま味わうもよし、茶碗蒸しや炊き込みご飯に加えて料理に深みを持たせるもよし、銀杏は秋の食材として多彩に活用できます。
シンプルながらも存在感のある味わいで、季節感を演出するのに最適な一品です。
銀杏の料理に使う調理器具や食器
テンポスで扱っている、銀杏の料理を作る際に使う調理器具や、おすすめの食器をご紹介!
茶碗蒸しスプーン
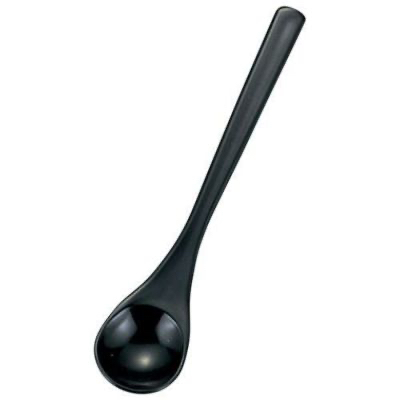
電気卓上蒸し器

まとめ
今回は、銀杏は果物なのか?特徴やおすすめ料理について紹介してきました。
銀杏は、「果物」と思われがちですが、実際にはイチョウの木になる「種子」です。
焼き銀杏や銀杏ご飯など、シンプルに作れる上、秋の食材として活用できる一品です。
#銀杏 #秋 #イチョウ
テンポスドットコムでは、様々な視点から飲食店の開業成功を全力で応援します。
自分のお店の業態に合わせて必要なものは何があるのか、詳細を確認することができますので是非ご覧ください!

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。



























