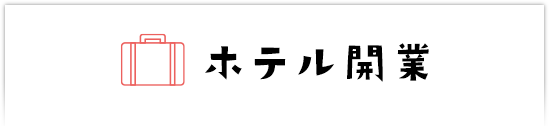資格・許認可
開業するために必須の保健所、消防署、警察署での手続き、節税のための税務署での手続き、従業員を雇用する時に必要な諸手続きや、申請のために必要な資格などの説明をします。
資格・許認可は、自治体によって多少違う場合がありますので、物件探しと同時に確認しておくと良いでしょう。 資格は、講習日がひと月に1回であったり、予約が1か月以上先までとれない場合もありますので、早めに取得するようにしてください。
開業スケジュール
| 前準備 | 物件申し込みから引き渡し 約1〜2か月 | 内装・外装工事期間 約2、3週間〜2か月 | 工事引き渡し後 約1週間 | オープン後 | |
| 許認可・資格取得 | 食品衛生責任者の資格取得 | 前相談(消防・保健所) | 検査(消防・保健所) | 開業届提出(税務署) |
民泊・ゲストハウスの運営に関わる法
宿泊施設を開業する際には保健所、消防署、税務署などへ届け出なければならないことがいろいろとあります。事前に計画を立てておくことがスムーズに開業するためのポイントとなります。
手続きに抜けやもれがないように、保健所や消防署、内装工事業者など関係各所に前もって相談して進めるようにしましょう。
1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)
一定の要件を満たした一般の家屋やマンションなど宿泊室面積の小さな住宅でも開業が可能です。
届出制のため比較的容易にはじめることができます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく規制
住居専用地域での営業が可能
- 営業日数は年間180日以内
- 宿泊者名簿の作成・保存義務有り
- 最低床面積は3.3㎡/人
- 衛生措置:換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等
- 非常用照明等の安全確保措置義務あり
- 消防用設備等の設置の必要あり
など
設備要件
以下の4つの設備が揃っていれば設備追加工事は原則しなくてよい。
- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 洗面設備
注意点
- 家主不在型の場合、物件の管理運営は『住宅宿泊管理業者』の登録を受けた業者でなければできません。
『住宅宿泊管理業者』は、国土交通大臣へ申請し、5年ごとに登録の更新が必要です。 - 民泊新法とは別に、各自治体で定められている条例があるので注意しましょう。
2. 旅館業法(簡易宿所)
旅館業法に基づく営業許可の区分は、『ホテル』『旅館』『簡易宿所』『下宿』があります。
民泊やゲストハウスを始める場合、『簡易宿所』の営業許可を取得するケースが多いです。
旅館業法(簡易宿所)に基づく規制
- 住居専用専用地域での営業は不可
- 客室数の規制なし
- 営業日数の制限なし
- 宿泊者名簿の作成・保存義務あり
- 客室全体の床面積は33㎡以上(宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人以上)
- 換気、採光、照明、防湿、排水等の設備を有する
など
設備要件
- 宿泊者数に応じた規模の入浴設備を有する
- フロントの設置の規制はなし
- 各自治体が条例で定める構造設備基準に適合していること
など
注意点
- 用途地域によっては営業が認められない場合がある。
- 建築基準法、消防法など関連する法規が複数あります。
- 建築基準法上の建物の用途変更が必要です。
- 旅館業法(簡易宿所)とは別に、各自治体で定められている条例があるので注意しましょう。
3. 国家戦略特区法(特区民泊)
東京圏、関西圏、秋田県、宮城県、愛知県、新潟県、広島県、愛媛県、福岡県、沖縄県などの都道府県内の一部の地域で、旅館業法が除外される国家戦略特区を政府が設けています。
国家戦略特区法に基づく規制
- 住居専用地域での営業可能
- 最低滞在日数の制限あり:2泊3日以上
- 宿泊者名簿の作成・保存が必要
- 最低床面積は25㎡以上/室(自治体によって相違の可能性あり)
- 換気、採光、照明、防湿、等の措置
- 非常用照明等の安全確保措置義務
- 消防用設備等の設置を要する
- 施設周辺地域の住民に対する説明及び苦情や問合せへの適切な対応が必要
など
注意点
- 国家戦略特区に指定された地域のみが対象です。
- 建築基準法、消防法など関連する法規が複数あります。
- 各自治体ごとに制限があったり、国家戦略特区法以外に定められている条例があります。
建築基準法
具体的な設備などについては、建築基準法による制限があります。
建物が安全かどうかの基準が定められています。
もともと宿泊施設ではなかった場合は用途変更の手続きが必要です。
詳しくは各自治体などの建築基準法窓口にご確認ください。
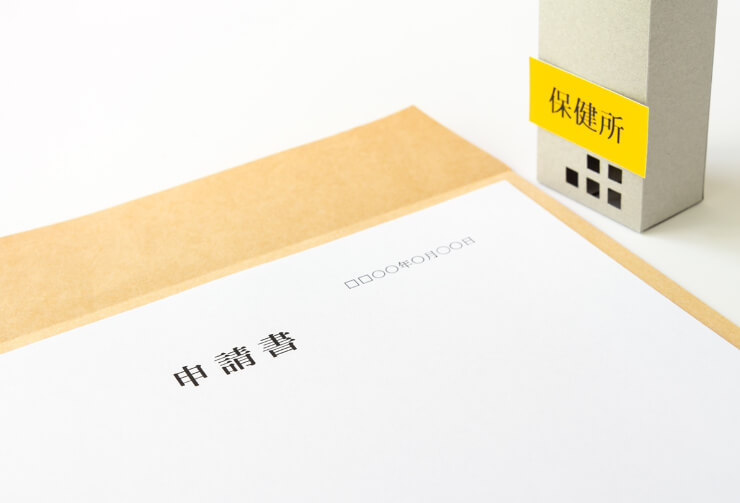
関連する許認可
■建築基準法について
建築基準法は、該当する建物が安全かどうかの基準を定めた法律です。
建築物を旅館業の用途で使用する場合、建築確認申請が必要な場合があります。
用途変更申請
もともと宿泊用ではない物件を宿泊施設として使う場合は、「用途変更」の手続きが必要となる場合があります。
申請先:自治体が指定する検査機関など
建築検査済証
100坪を超える物件の場合は、建築検査済証を申請する必要が生じます。
書類と合わせて監査が行われるので、スケジュールにゆとりを持つ必要があります。
申請先:自治体が指定する検査機関など
詳しくは各都道府県の建築基準法担当窓口にてご確認ください。
■消防法についての手続き
消防法では、火災発生時に備えた構造や設備などが定められています。
消防法令適合通知書交付申請
簡易宿泊所を開業するためには、「消防法令適合通知書」の申請をし、交付を受ける必要があります。
検査に合格すると、交付を受けることができます。まずは事前相談をしましょう。
申請先:管轄の消防署
要する期間:問題が無ければ約1週間
注意点
建物によっては自動火災報知設備の大規模な工事が必要になり大きな費用がかかったり、工事そのものが不可能な場合もありますのでご注意ください。
消防庁: 民泊における消防法令上の取り扱い等
■旅館業法について
旅館業営業許可申請
宿泊料を受け取り人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
申請先:管轄の保健所
要する期間:約1カ月
■その他の許認可
開業届(所得税法)
個人事業主として開業する場合、開業届を提出する必要があります。
届け先:税務署
提出時期:開業後1カ月以内に提出
青色申告承認申請書
開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しておきましょう。青色申告しておくと節税にもなります。
届け先:税務署
提出時期:開業届と一緒
飲食店営業許可(食品衛生法)
宿泊客へ食事を提供する場合、飲食店営業許可を取得しておかなければなりません。
許可を得るためには、【人に関する要件】と【店舗に関する要件】の2つの要件があります。
人に関する要件、申請者が資格取得に影響する要件に該当していないかどうかになります。
店舗に関する要件は、
①食品衛生責任者を配置しているか②店舗の構造や設備に対して要件を満たしているかを、保健所の担当者が訪問し検査して確認を行います。
申請先:管轄の保健所
要する期間:1~2週間
食品衛生責任者(資格)
飲食店営業許可の取得には、食品を扱う責任者である食品衛生責任者を施設に1人置く必要があります。
※調理師、栄養士、製菓衛生師などの免許を持っている方は食品衛生責任者養成講習会を受講することなく、申請することで資格の取得が可能です。
問合先:地域の保健所
公衆浴場営業許可(公衆浴場法)
大衆浴場・銭湯・サウナなどのように、一浴室に同時に多人数が利用できる大浴場を設置するには公衆浴場許可が必要です。
申請先:管轄の保健所
期間:1~2か月ほど