飲食店開業を考えている方で、気に入った場所にお店を借りて飲食店経営を始めたいという方がいるはずです。
その際、用途地域について注意が必要です。
その場所が飲食店経営に適した場所だといっても、用途地域によっては出店の制限が設けられている場合があります。
いったい、開業できない場所とはどの地域になるのでしょうか。
今回は、飲食店開業ができない場所ってあるの?条件が定められている「用途地域」について紹介していきます。
飲食店開業を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
飲食店開業ができない場所とは?

飲食店を開業する際、どこでも自由に出店できるわけではありません。法律や地域の条例によって、開業が制限されている場所がいくつか存在します。
まず、「用途地域」が関係してきます。都市計画法に基づき、土地は住宅専用地域、商業地域、工業地域などに分かれており、特に「第一種低層住居専用地域」では、原則として飲食店の開業が認められていません。
これは、静かな住環境を守るためで、騒音や匂い、人の出入りが多くなる飲食店は不適切とされるためです。
また、建物の用途や構造も制限要因になります。たとえば、集合住宅の一室や住居専用の建物では、管理規約や所有者の許可が必要な場合があり、それが得られないと営業許可が下りません。
さらに、消防法や建築基準法に適合しない建物では、安全面から保健所の営業許可を受けられないこともあります。
衛生上の観点からも、上下水道が未整備な地域、害虫や動物の侵入リスクが高い場所、十分な換気設備が確保できない場所などは不適とされます。
その他、文化財保護地域や学校周辺など、一部の条例で飲食店の出店が制限されているエリアもあります。
飲食店を開業する前には、物件のある地域の用途地域や建築条件を確認し、保健所や自治体に相談することが重要です。
計画段階から慎重に調査し、開業可能な場所かどうかを見極めることが成功への第一歩となるでしょう。
店舗開業時の用途地域に関する注意点とは?
飲食店を開業する際、「用途地域」の確認は非常に重要です。用途地域とは、都市計画法に基づいて土地の利用目的を制限するものです。
また、建物の種類や規模、使い方に一定の制限を設けることで、良好な住環境や都市機能の維持を目的としています。
用途地域には13種類あり、それぞれに適した建築物や業種が定められています。
ここでは、飲食店を開業する際に注意すべきポイントについて紹介していきます。
主に以下のことがあげられます。
「住居専用地域」では出店が制限される
「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」は、静かな住宅環境を守ることが目的のエリアで、飲食店の開業は原則として認められていません。
仮に、小規模なカフェやテイクアウト店であっても、営業許可が下りない可能性があります。
住民の反対に遭いやすい点もリスクです。住宅街での開業を検討している場合は、まずその地域が「住居専用地域」ではないかを確認することが必須です。
「住居地域」では規模や業態に制限がある
「第一種住居地域」や「第二種住居地域」は、住居と一部の商業施設の混在が許されている地域ですが、飲食店に対しては一定の制限があります。
たとえば、床面積が制限されていたり、深夜営業やアルコール提供が近隣トラブルの原因になっていたりする場合があります。
また、パチンコ店やカラオケボックスなどの風俗営業に類する業態は制限されているため、業種によっては要注意です。
「商業地域」は出店に適しているが競争が激しい
「商業地域」は、百貨店、映画館、飲食店などの商業施設が集まる地域で、飲食店の開業にもっとも適しています。
用途上の制限が少なく、営業時間も比較的自由ですが、その分競争も非常に激しいです。
家賃相場も高く、出店コストがかさむため、資金計画やコンセプトが明確でないと生き残るのは難しいでしょう。
立地の与さだけで決めるのではなく、周辺環境やターゲット層の分析が重要です。
「工業地域・工業専用地域」は注意が必要
「工業地域」では、飲食店の開業は可能ですが、工場や倉庫が立ち並ぶエリアのため、一般の集客には不向きなケースが多いです。
また「工業専用地域」になると、飲食店の開業は認められていません。社員食堂や関係者向けの小規模な施設であれば、可能なこともありますが、一般営業を目的とする場合は対象外です。
物件が安いからと安易に決めず、営業が可能かどうかの確認を必ず行いましょう。
このように、用途地域によって飲食店の開業可能性や条件は大きく異なります。出店候補地が見つかったら、まずそのエリアがどの用途地域に属しているかを自治体の都市計画課やインターネットの都市計画図で確認し、適切な出店判断を行うことが重要です。
用途地域にはどんなものがある?13種類の用途地域一覧
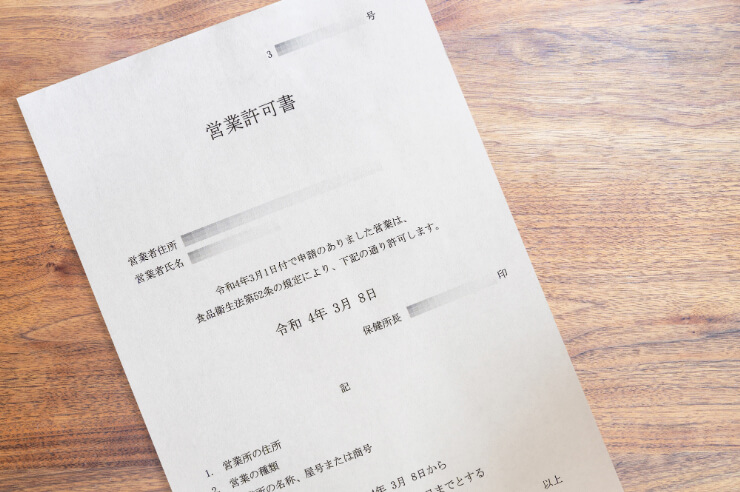
用途地域は、都市計画法に基づいて土地の利用を制限・誘導するための制度で、全部で13種類に分類されています。それぞれの地域で建てられる建物や用途が異なり、住宅地、商業地、工業地など、街の性格づけに重要な役割を果たしています。以下に、13種類の用途地域を住宅系・商業系・工業系に分けて紹介します。
住宅系
1:第一種低層住居専用地域:低層住宅のための静かな住宅地。
2:第二種低層住居専用地域:小規模店舗など一部の非住宅施設が可能
3:第一種中高層住居専用地域:中高層マンションなども建築可能。
4:第二種中高層住居専用地域:教育施設や病院、小規模店舗も許可。
5:第一種住居地域:住宅中心だが中規模店舗や事務所も可。
6:第二種住居地域:パチンコ店やカラオケ店なども可能。
7:準住居地域:道路沿いなどでドライブインやガソリンスタンドも可。
8:田園住居地域:農業と共存する低層住宅地。
商業系
9:近隣商業地域:住宅地に近接する小規模商業エリア。
10:商業地域:百貨店や飲食店、オフィスビルなどが集まる地域。
工業系
11: 準工業地域:工場や住宅が混在可能な地域。
12:工業地域:住宅も可能だが、主に工場向け。
13:工業専用地域:工場のみ。住宅や商業施設の建設は不可。
それぞれの地域で建築可能な施設や制限内容が異なるため、店舗出店や建築の際は必ず確認が必要です。
飲食店で使う調理器具や食器
テンポスで扱っている、飲食店で使う調理器具や、おすすめの食器をご紹介!
三島 土鍋 S-503 8号

和卓 室町(折足型)メラミン黒木目タイプ

まとめ
今回は、飲食店開業ができない場所ってあるの?条件が定められている「用途地域」について紹介していきました。
飲食店開業ができない場所として、「第一種低層住居専用地域」(低層住宅のための静かな住宅地)では、原則として飲食店の開業が認められていません。
用途地域とは、都市計画法に基づいて土地の利用目的を制限するもので、13種類もの制度があり、それぞれに適した建築物や業種が定められています。
開業時は、用途地域を把握しておきスムーズな開業を心掛けましょう。
#飲食店 #開業 #用途地域
テンポスドットコムでは、様々な視点から飲食店の開業成功を全力で応援します。
自分のお店の業態に合わせて必要なものは何があるのか、詳細を確認することができますので是非ご覧ください!

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。



























