パン屋を開業する際、避けて通れないのが「保健所の許可」です。
スムーズに営業許可を取得するためには、事前準備が欠かせません。
今回は、パン屋を開業する際に押さえておきたい「保健所対策」のポイントを10個にまとめてご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
事前相談は必須

パン屋を開業するうえで、保健所への「事前相談」は非常に重要です。
営業許可をスムーズに取得するためには、書類の提出や施設完成の前に、保健所に対して十分な確認と相談をしておくことが欠かせません。
なぜ事前相談が必要なのか?
保健所は、営業許可を出すにあたって、施設の構造や設備、動線、衛生管理の仕組みなどが法令に適合しているかを確認します。
事前に相談せず工事を進めてしまうと、「手洗い場の数が足りない」「作業スペースの動線が不適切」といった理由で、改修工事が必要になるケースがあります。
これにより開業時期が遅れるリスクが高まるのです。
事前相談に持参すべきもの
事前相談では、以下の資料を持参すると具体的な指導が受けられやすくなります。
・店舗の平面図(図面)
・厨房機器の配置案
・手洗い場・シンク・冷蔵庫などの位置情報
・使用予定の設備や什器のカタログや仕様書
・パンの製造工程の流れ(簡単なフローチャート)
これらの情報があれば、保健所の担当者が「どの工程で衛生リスクがあるか」「どの場所を改善すべきか」など、具体的な指摘やアドバイスをしてくれます。
相談はいつ行くべき?
基本的には、店舗のレイアウトがある程度固まった段階で、内装工事を始める前に行くのが理想です。
早めに相談することで、必要な設備やレイアウト変更にも柔軟に対応でき、余計な費用や手間を省くことができます。
担当者との関係づくりも大切
保健所の職員との信頼関係を築いておくことも大切です。
丁寧な対応を心がけ、指摘された点には誠実に対応しましょう。
そうすることで、許可申請時にもスムーズなやり取りができ、審査の過程も円滑になります。
このように、事前相談は「確認のため」というよりも、「成功するパン屋づくりの第一歩」として、積極的に活用したいステップです。
確実な準備が、安心・安全な営業の土台を築いてくれます。
設備要件を確認

パン屋を開業する際、店舗のレイアウトや厨房機器の選定に先立って確認しておきたいのが、保健所が定める「設備要件」です。
これを満たしていないと、営業許可が下りないだけでなく、再工事や設備の買い直しが発生し、コストと時間のロスにつながります。
厨房・製造エリアの基本的な要件
パン屋は「製造業」としての側面が強く、調理設備の衛生基準が重視されます。具体的には以下のような要件があります。
シンクは二槽以上が基本
食材洗浄用と器具洗浄用で用途を分ける必要があります。
一槽しかない場合は、用途が混在すると衛生上問題とされることがあります。
手洗い場の設置
作業場の近くに専用の手洗い場を設置することが求められます。
ハンドソープ・ペーパータオル・手指消毒剤の常備が必要です。
床・壁・天井の材質
掃除がしやすく、汚れが残りにくい素材(防水性、耐薬品性のあるもの)が推奨されます。
タイル、ステンレス、塩ビシートなどが一般的です。
厨房と販売エリアの区分け
製造エリアと販売エリアが物理的に仕切られていることが望ましいです。
扉やパーティションを設けて、外気やお客様からの飛沫を遮断できる構造にします。
冷蔵・冷凍庫の設置
材料や製品を適切な温度で保管するために、冷蔵庫・冷凍庫を必要台数設置する必要があります。
保管内容によって、温度管理の記録が求められることもあります。
排水・換気・給湯にも注意
排水設備
排水口には必ず「防虫・防臭フタ」が必要です。
配管からの逆流や臭気の漏れ、害虫の侵入を防ぎます。
換気設備
パンの焼成時には多くの蒸気・熱気が発生します。
厨房内の空気がこもらないよう、換気扇やフードを適切に設置し、外部への排気が十分であるかを確認しましょう。
給湯設備
手洗いや器具洗浄に使用するため、40℃以上の温水が出る給湯設備が必要です。
場所によっては洗浄用と手洗い用で別々の設置が求められます。
検査でチェックされやすいポイント
保健所の立ち入り検査では、次の点がよくチェックされます。
・作業動線に無駄がないか(クロスコンタミネーションの防止)
・ゴミの保管場所が適切か(密閉されているか、作業場に近すぎないか)
・製造エリアに私物がないか
・設備の使用目的と実際の運用が一致しているか
設備導入前のポイント
新しく設備を導入する際は、カタログや仕様書を持って保健所に事前確認を取るのが安全です。
要件を満たしていると思っていても、地域ごとに基準や細かな運用指針が異なる場合があります。
このように、設備要件は「一度整えたら終わり」ではなく、運用面まで見越して整備することが重要です。
工事前・購入前に保健所としっかり連携を取ることで、無駄のない開業準備ができます。
材料の保管場所を明確に

パン屋における「材料の保管場所」は、衛生面・品質保持の両面で非常に重要なポイントです。
保健所の立ち入り検査でも必ずチェックされる項目であり、計画段階からしっかりと設計しておく必要があります。
なぜ保管場所が重要なのか?
パンの主原料である小麦粉、イースト、砂糖、バター、牛乳などは、温度や湿度によって品質が劣化しやすく、また虫やカビの温床にもなりかねません。
さらに、生地や具材などの中間製品、焼き上げたパンといった段階ごとの保管方法にも明確な区分が求められます。
誤った保管をしていると、「異物混入」や「腐敗・変質」といったリスクが高まり、営業停止や回収騒ぎにつながる恐れもあります。
保管スペース設計の基本
保健所が求める保管環境の基本的なポイントは以下の通りです。
温度管理ができること(冷蔵・冷凍・常温の3区分)
食材ごとに適切な温度帯で保管できるよう、冷蔵庫・冷凍庫を複数台用意する必要があります。
常温保管でも、通気性や湿度に配慮した棚やコンテナの使用が求められます。
食材の種類ごとに分ける
原材料(小麦粉・バターなど)と調理済み(焼いたパン・サンドイッチ具材など)は、物理的に分けて保管します。
特に生もの(卵・乳製品・加熱前の具材)と焼成済みパンを同じ場所で保管するのはNGです。
食品と非食品(洗剤・ダンボールなど)の区別を徹底
洗剤や包装資材、清掃用具などは食品と同じ空間で保管せず、専用の保管スペースを設けましょう。
棚や収納容器は清掃しやすい構造に
棚は床から10cm以上の高さを確保し、通気性のあるメッシュ素材などが理想的です。壁に直接食品を置くのは避け、収納容器も蓋つきで洗いやすいものを使用しましょう。
冷蔵庫・冷凍庫の管理ポイント
冷蔵・冷凍庫については、以下のようなポイントが確認されることが多いです。
・食材ごとにラベルを貼り、使用期限・開封日を明記する
・過積載を避けて、冷気が循環するように配置する
・清掃記録をつける(週1回以上の清掃が理想)
・温度計を設置し、毎日温度チェック・記録をする
保健所によっては、温度記録表の提示を求められることもあります。
Excelや紙で記録を残すようにしておくと安心です。
原材料の入荷〜保管の流れも大事
仕入れた原材料の「入荷時チェック」から「保管」「使用」に至るまでの一連の流れが、衛生管理上とても重要です。
例えば
・入荷時に賞味期限・異常の有無を確認
・すぐに適切な場所へ保管(冷蔵なら即冷蔵庫へ)
・使いかけの食材は密閉容器に入れて日付ラベルを貼る
・古いものから使う「先入れ先出し」を徹底する
これらの運用がルール化されているかどうかも、許可取得の際に問われるポイントとなります。
材料の保管体制は、店舗の規模に関わらず衛生管理の「要」です。
作業効率だけでなく、安全・信頼されるパン屋づくりのためにも、計画段階からしっかりと設計しておきましょう。
許可の種類を選ぶ
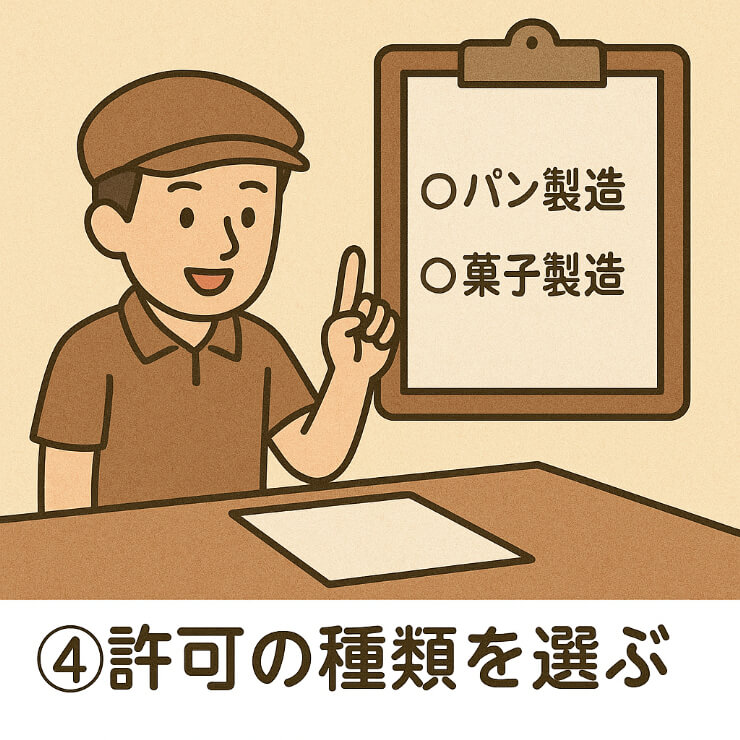
パン屋を開業するにあたって、保健所からの営業許可は不可欠です。
しかし一口に「パン屋」といっても、店舗の営業形態や提供する商品内容によって、取得すべき許可の種類が異なります。
間違った許可で営業を始めると、後で変更・追加の手続きが必要になり、時間やコストのロスにつながるため、最初の段階で正しく判断することが重要です。
パン屋に関係する主な営業許可の種類
パン屋で必要になる可能性がある許可は、主に以下の3つです。
菓子製造業許可
→ パンの製造・販売のみを行う場合(テイクアウトのみ)
飲食店営業許可
→ 店内にイートインスペースを設けて、その場で飲食を提供する場合
喫茶店営業許可
→ 簡単な軽食・飲み物の提供がメインの場合(食事は提供しない)
それぞれの許可の特徴と違い
菓子製造業:パン・焼き菓子などの製造販売
製造し、包装して販売(テイクアウト)店内飲食がないことが前提です。
飲食店営業:パン+飲み物や軽食を提供し、店内で飲食可能な場合
調理・配膳・食器洗浄などを含みます。
厨房設備・座席・トイレの要件が追加されます。
喫茶店営業:コーヒーや軽食のみの提供で簡易な営業
火を使った調理は限定的です。
パンの製造販売には不向きです。
自分の店舗に合った許可をどう選ぶ?
例えば次のようなケースでは、それぞれの許可が必要になります。
パンを焼いて、包装して販売するだけ(テイクアウト専門)
→ 菓子製造業許可のみでOK。
パンと一緒に、店内でコーヒーを提供し、飲食スペースがある
→ 菓子製造業許可+飲食店営業許可の両方が必要。
既製品のパンを仕入れて、コーヒーと一緒に提供する簡易カフェ
→ 飲食店営業許可または 喫茶店営業許可のみでOK(パンの製造がないため)。
店舗の設備やオペレーションが複合的になる場合には、複数の許可を取得する必要があるケースが多くなります。
実際には、地域の保健所で店舗図面や営業内容を元に判断してもらうのが最も確実です。
申請から許可取得までの流れ(簡略版)
①保健所へ事前相談(営業内容と図面を持参)
②必要な許可の確認と申請書の記入
③必要書類の提出(図面・機器リスト・水道・排水情報など)
④現地検査(保健所職員による設備確認)
⑤問題なければ営業許可証が交付され、営業開始可能
注意!業態変更時は許可の追加が必要
開業当初はテイクアウト専門で「菓子製造業許可」のみで始めたとしても、後からイートインスペースを追加したり、ドリンク提供を始めたりする場合には「飲食店営業許可」を追加取得する必要があります。
営業形態が変わった際には必ず保健所に相談しましょう。
許可の種類を誤ると、営業停止や指導の対象になる可能性もあります。
余裕をもって保健所と綿密に相談し、自分のパン屋に最適な許可を確実に取得しましょう。
衛生管理者の設置

パン屋をはじめとする食品を扱う店舗では、衛生管理の責任者=衛生管理者を明確に設置することが求められます。
これは保健所からの指導に基づくもので、店舗の衛生状態を一定の基準以上に保つために非常に重要な役割を担います。
衛生管理者とは?
衛生管理者とは、店舗内の衛生状況を監督・記録・改善する責任者のことです。
必ずしも国家資格を持つ必要はありませんが、保健所からは「責任者を1人決めておくこと」が求められます。
中小規模のパン屋であれば、店主自身が衛生管理者を兼任することもよくあります。
主な役割と業務内容
衛生管理者が担う主な業務は以下の通りです。
・日々の清掃・衛生チェックの実施・指導
・従業員の手洗い・身だしなみの指導
・冷蔵庫の温度管理と記録
・異物混入や食材管理に関するルール策定
・厨房設備の衛生点検・記録
・食中毒発生時の対応マニュアル整備
・HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理の実施と記録(※後述)
このように、日々の衛生状況を把握し、必要な予防策を講じることで、食品事故のリスクを大幅に減らすことができます。
HACCP(ハサップ)との関係
2021年6月から、すべての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されました。
パン屋もその対象に含まれます。
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食中毒や異物混入などのリスクを事前に洗い出し、重要管理点を継続的に監視・記録する衛生管理手法です。
衛生管理者はこのHACCPに基づいた管理を行うために、
・製造工程の見える化(フローチャートの作成)
・重要管理ポイント(加熱温度、保存温度など)の設定とチェック
・記録の保存と定期的な見直し
などを実施・管理する責任を持ちます。
衛生管理者になるには特別な資格が必要?
基本的には資格不要ですが、次のような衛生管理に関する講習会や研修の受講が推奨されます。
・食品衛生責任者講習(各自治体や保健所が実施)
・小規模事業者向けHACCP講習
・各業界団体が提供するeラーニング
これらの講習を受けておくことで、HACCPの基礎知識を身に付けられ、衛生管理者としての信頼性も高まります。
保健所の検査時に見られるポイント
保健所の営業許可検査や定期巡回時には、衛生管理者が次のような対応を求められることがあります。
・誰が衛生管理者かを明確に説明できる
・管理記録(日々の温度チェックや清掃記録など)を提示できる
・衛生ルールが現場で守られているかの確認
適切な管理体制があることを示せれば、信頼度も高くなり、営業上の安心材料にもなります。
小さな店でも「衛生のプロ」を意識して
衛生管理者は、ただの“担当者”ではなく、店舗全体の信頼と安全を守るキーパーソンです。
特にパン屋では、小麦粉やバターなどカビや虫の発生リスクがある食材を扱うため、衛生管理の質が店の信用を左右します。
開業準備の段階から「誰が衛生管理を担うのか?」「どうやって記録を取るか?」を明確にしておくことで、スムーズな許可取得と、事故のない運営につながります。
作業着や衛生帽の準備

パン屋を開業するにあたり、衛生面での徹底が求められるのは作業着や衛生帽です。
これは、スタッフや製造過程での異物混入を防ぎ、食品の安全性を保つために欠かせない要素となります。
特に食品衛生管理の視点では、食品に触れる全ての人が適切な服装をしているかどうかが重要なポイントになります。
作業着・衛生帽の役割と必要性
衛生管理の徹底
衛生帽や作業着は、食品製造中に髪の毛や衣服から落ちる異物混入を防ぐ役割を持っています。パン屋では粉を使用するため、衣服に付着した粉が製品に入り込む可能性があり、これも管理対象となります。
清潔感の維持
衣服が清潔であることは、店舗の信頼性にも直結します。衛生帽をかぶり、作業着をきちんと整えることで、お客様に「衛生管理に配慮している店舗だ」と印象づけることができます。
規定に基づいた管理
衛生管理の基準や保健所の監査基準に従って、適切な作業着・衛生帽を着用しなければならないことが法律で定められています。例えば、パン屋における規定では、食材を扱うスタッフが髪の毛を覆う衛生帽やネットキャップを着用することが求められます。
衛生帽(キャップ)の選び方
髪の毛を完全に覆うもの
衛生帽の最大の役割は、髪の毛や頭皮からの異物を防ぐことです。髪が長いスタッフやお団子頭のスタッフも、髪の毛が一切露出しないように、完全に覆うことができるキャップが必要です。
通気性と快適さ
衛生帽は長時間着用するため、通気性が良い素材を選ぶことが大切です。ポリエステルやメッシュ素材など、通気性の良いものを選びましょう。これにより、長時間の作業中も快適さを保つことができます。
使い捨てタイプと洗濯可能タイプ
衛生帽には使い捨てタイプと洗濯して再利用できるタイプがあります。使い捨てタイプは、一度使ったらすぐに廃棄するため、衛生面では非常に効果的ですが、コストがかかります。再利用可能なタイプは、定期的に洗濯する手間がかかりますが、コストを抑えることができます。
作業着(ユニフォーム)の選び方
作業着は、パン屋での作業に適した清潔で機能的なものである必要があります。
食品に触れる部分は、耐久性があり清潔を保ちやすい素材
作業着は、食材を扱うため、ポリエステルやコットン混紡など、手洗いや洗濯に耐えられ、清潔感を保ちやすい素材で作られていることが求められます。
長時間の作業でも快適であることが重要です。
シンプルで動きやすいデザイン
作業着は、作業中の動きやすさも重要なポイントです。
シンプルなデザインで、作業中に引っかかりにくいものを選びましょう。
また、作業着にはポケットがある場合が多いため、物が落ちないようにする工夫も必要です。
作業着の交換ルール
衛生管理者が定める「作業着交換ルール」に従い、定期的に交換・洗濯を行うことが大切です。
作業中に汗や汚れが付着するため、衛生的に問題がないように交換頻度を設けておきましょう。
スタッフ毎にユニフォームを準備
衛生管理の一環として、スタッフごとに専用の作業着を準備することが推奨されます。また、同じユニフォームでも、使い分けることで、衛生面での混同を防げます。
さらに気を付けたい衛生管理のポイント
手袋の着用
食品を直接触ることが多いパン屋では、使い捨ての手袋を使用することも一般的です。
手袋の交換をこまめに行い、衛生面を徹底しましょう。
エプロンの着用
作業着とは別に、エプロンの着用を推奨します。
エプロンは清潔を保つために毎日洗濯し、使い捨てのエプロンも使用可能です。
靴の衛生管理
靴も、厨房内に汚れを持ち込まないように滑り止めのある衛生的なものを選びます。
また、スタッフが靴を履き替えられるようなシューズラックを設置することも一つの方法です。
害虫・害獣対策

パン屋は、小麦粉・砂糖・バターといった虫やネズミの好む食材を多く扱うため、害虫・害獣の対策は営業許可取得の際にも非常に重視されるポイントです。
店舗の清潔さを保つだけでなく、店舗の構造や設備の工夫が重要になります。
たとえパンが美味しくても、虫がいたらお客様の信頼は一気に失われてしまいます。
保健所が重視するチェックポイント
保健所の許可検査では、以下のような点がチェックされます。
・外部からの侵入経路の遮断(ドア・窓・換気口などの隙間の有無)
・排水溝や配管周辺の密閉性(害虫の侵入口になりやすい)
・ゴミの保管場所の衛生状態(フタ付きでこまめに廃棄されているか)
・捕虫器やネズミ捕獲器の設置状況
・過去に発生した形跡(フン・羽・食害など)の有無
これらは、設備図面の段階から対応が必要なものも多く、開業前の設計でしっかり考慮することが求められます。
よくある侵入経路と対策例
ドアや窓の隙間
自動ドアやドア下部の隙間埋め(ドアスイープ等)を設置
換気扇や排気口
メッシュフィルターの設置・定期清掃
排水口
トラップ付きの排水口の使用・定期洗浄
屋外のゴミ置き場
密閉容器に収納・清掃の徹底
食材の納入ルート
入荷後すぐに清掃・害虫の混入チェックを行う
害虫・害獣対策の具体例(パン屋の場合)
捕虫器の設置
→特に照明に引き寄せられる飛翔性昆虫(ショウジョウバエなど)の対策に有効。入口付近やバックヤードに設置するのがおすすめです。
ネズミ捕獲器の設置
→ 食材保管庫や厨房の隅に設置しておき、定期的に点検しましょう。
毎日の掃除ルールを明確に
→食材のくず・粉が床や機器に残らないよう、調理後すぐの清掃を徹底。特にオーブン周りや作業台の下など“死角”になりやすい箇所は重点的に。
業者による定期点検・防除契約
→害虫駆除業者と月1回〜2回の定期契約をしておくと、万一の発生時も迅速に対応でき、保健所への説明材料にもなります。
害虫・害獣発生を「予防」する視点が大切
すでに発生してから駆除するのではなく、「そもそも入れない・住まわせない」ことが衛生管理の基本です。
パン屋は粉や糖分の扱いが多いため、ちょっとした清掃漏れが虫の繁殖を招きやすいです。
たとえば
・粉をこぼしたらすぐに拭き取る
・食材の開封済み袋は密閉容器で保管
・フロアのモップ清掃を毎営業日終業後に行う
・壁・床のひび割れは見逃さず修繕する
といった日々の積み重ねが、トラブルの予防につながります。
パン屋は「におい」と「粉」に注意
パン屋特有の香ばしいにおいや糖分・油脂を含む食材は、害虫・害獣にとって格好のターゲットです。
保健所からの指導も厳しいポイントなので、営業許可前に対策を講じておくことが非常に重要です。
常に「虫やネズミが入りにくい・寄りつきにくい店舗づくり」を心がけることで、お客様に安心して利用していただける店舗運営が可能になります。
使い捨て手袋・洗剤の常備

パン屋では、衛生的に食品を扱うことが最も重要です。
そのため、使い捨て手袋や洗剤の準備と使用は、衛生管理の基本中の基本となります。
手袋や洗剤の使用方法を適切に整え、常に清潔を保つことが、食品事故や衛生問題を防ぐためには欠かせません。
使い捨て手袋の重要性と管理方法
手袋を使用するタイミング
パンの製造・加工を行う際、手袋は直接食品に触れる部分を清潔に保つために必要不可欠です。
特に、パン生地をこねるときや、完成したパンを取り扱うときは、手袋を使用することで、異物混入や細菌の感染を防ぐことができます。
また、手袋を使用するタイミングとしては、食材の取り扱い時やお客様の注文を受けた際も重要です。
手袋を使い分けることで、異物の混入を防ぎます。
使い捨て手袋の選び方
素材
食品を扱う際に使用する手袋は、食品用の手袋でなければなりません。
ポリエチレン製やニトリル製など、食品衛生法に基づいた素材を選びましょう。
ポリエチレンは薄くて軽いため短時間の使用に向いており、ニトリルは厚手でしっかりとした手袋です。
ニトリル手袋は、化学物質や油脂に強いので油分が多いパン製造でも適しています。
サイズ
手袋はスタッフ1人1人に合ったサイズを選ぶことが大切です。
大きすぎると作業がしづらく、小さすぎると破れる可能性が高くなります。
適切なサイズの手袋を準備することで、作業効率が向上し、衛生的にも問題が起こりにくくなります。
手袋の使用ルール
手袋の交換頻度
手袋は使い捨てのため、食材を触った後、トイレに行った後、ゴミを捨てた後などに必ず交換します。
また、手袋に破れが生じた場合もすぐに交換しましょう。
使い捨て手袋は頻繁に交換することが、衛生管理には欠かせません。
手袋を外すタイミング
手袋を外す際は、内側を触らず外側を持って慎重に外すことが重要です。
外した手袋はすぐに適切に廃棄し、手を洗うことを忘れないようにします。
手袋の常備
備蓄管理
作業に必要な手袋は、常に一定の量を備蓄しておくことが重要です。
発注を忘れないように、在庫管理をしっかりと行うことが、衛生的な作業環境を維持するために必要です。
保管方法
手袋は湿気や直射日光を避けて、乾燥した場所に保管することが大切です。
また、清潔な場所に保管し、汚れやほこりが付かないように気をつけましょう。
洗剤の常備と管理
使用する洗剤の種類
食器用洗剤
食器や調理器具を洗うために、食品用洗剤を常備します。
これらの洗剤は、手肌に優しく、かつ強力に汚れを落とす成分が含まれています。
食器を洗う際に使用する洗剤には、食品衛生法に適合したものを選ぶことが求められます。
厨房用洗剤
厨房内の床や作業台の清掃には、強力な除菌効果を持つ洗剤を使用します。
油脂や粉がこびりつきやすいため、効果的に洗浄できる洗剤を選びましょう。
除菌スプレー
調理器具や食材置き場の除菌には、速乾性のある除菌スプレーを常備しておくことをお勧めします。
これにより、作業後すぐに器具や作業場を消毒できます。
洗剤の使用頻度
毎日の清掃
作業終了後、または昼休憩時などに、厨房内や作業場全体を清掃します。
特に、作業台やオーブン、トースターなど食材を直接扱う設備は毎日洗浄が必要です。
定期的な深層清掃
定期的に、厨房の隅やエアコン、換気扇の清掃も行います。
これにより、隠れた汚れを取り除き、衛生状態を保ちます。
洗剤の備蓄管理
発注管理
洗剤も手袋と同様に、常に一定量を備蓄しておくことが大切です。
在庫を確認し、早めに発注しておくことで、使用中に足りなくなることを防ぎます。
保存場所
洗剤は直射日光を避け、湿気の少ない場所で保存します。
また、子供や他のスタッフが誤って使用しないように、安全な場所に保管することが重要です。
使い捨て手袋と洗剤の常備で衛生を保つ
パン屋での衛生管理において、使い捨て手袋や洗剤は必需品です。
手袋は食品に触れるスタッフ全員が必ず使用し、交換・廃棄のタイミングを守ることで、異物混入や感染症のリスクを最小限に抑えることができます。
また、洗剤は清掃・消毒に欠かせないアイテムであり、定期的な補充や適切な保管方法を守ることが、店内の衛生状態を保つために重要です。
適切な管理を行い、清潔な作業環境を提供することが、お客様の信頼を得るための基本となります。
清掃計画の作成

パン屋では、清掃は衛生管理の基礎となります。
厨房内や店舗内が清潔であることは、食品の安全を守るためには欠かせません。
特にパン製造においては、粉や油分などが散らばりやすく、定期的な清掃が必須です。
そのためには、清掃計画を作成し、スタッフ全員が一貫して衛生的な環境を維持することが求められます。
清掃計画の目的と重要性
衛生環境の維持
清掃計画を作成することで、常に清潔で衛生的な作業環境が維持できます。
パン屋では、粉や油脂、食品のカスが発生しやすく、これらが堆積すると害虫の繁殖やカビの発生を引き起こす原因となります。
定期的な清掃が害虫や病原菌の発生を防ぎ、製品の品質を保ちます。
食品事故の防止
清掃計画を徹底することで、異物混入や衛生上の問題を未然に防ぐことができます。
パン屋では食品が多く取り扱われるため、清掃が不十分だと、細菌やカビが繁殖しやすく、食品衛生上のリスクを増大させます。
保健所への対応
清掃計画は、保健所の衛生管理基準に適合するためにも必要です。
保健所の定期的な衛生検査では、清掃の徹底がチェックされるため、計画的な清掃活動を行っていることが示されると、信頼性のある店舗運営が評価されます。
清掃計画の作成方法
清掃項目のリストアップ
まず最初に、清掃すべき場所や清掃項目をリストアップします。これには以下のような項目が含まれます。
・厨房内の床、壁、天井
・作業台や製造機器(オーブン、ミキサー、トースターなど)
・食材保管庫や冷蔵庫
・食器や調理器具
・ゴミ捨て場や排水口
・スタッフが触れるドアノブやスイッチ
各エリアごとに清掃の頻度や方法を明確に定めることが、計画を作成する上での第一歩です。
清掃の頻度の設定
清掃は一度きりではなく、定期的に行うことが大切です。
清掃の頻度を日次、週次、月次などに分けて設定します。
例えば
日次清掃
毎日終業後に行うべき清掃(床の拭き掃除、作業台の清掃、ゴミの処理)
週次清掃
毎週行うべき清掃(冷蔵庫や食材保管庫の整理、換気扇の清掃)
月次清掃
毎月行うべき深層清掃(厨房の隅の清掃、エアコンや換気設備の点検)
これにより、どの清掃がどのタイミングで行われるかが明確になり、スタッフも仕事を効率的にこなすことができます。
清掃担当者の指定
各清掃項目ごとに担当者を割り振り、責任を持たせることが重要です。
スタッフ全員が協力して清掃を行うのではなく、役割分担を明確にすることで、効率的に作業が進みます。
また、定期的に担当者をローテーションすることで、全員が清掃の重要性を理解し、店舗全体の衛生が保たれます。
清掃方法と使用する器具の記載
清掃の際に使用する洗剤や道具についても、清掃計画に記載します。
例えば
・厨房の床掃除には中性洗剤を使用し、モップで拭く
・作業台や設備の清掃には、アルコール系除菌スプレーを使用する
・ゴミ箱や排水口には強力な消臭剤や除菌洗剤を使う
使う洗剤や道具を明記することで、清掃方法に統一感が生まれ、誤った方法で清掃が行われるリスクを減らします。
清掃計画に組み込むべきチェックリスト
日次清掃チェックリスト
・作業台の拭き掃除
・床の掃除(粉や油が散らばりやすいため特に重要)
・食材や道具の収納エリアの整理整頓
・ゴミの廃棄・ゴミ箱の清掃
週次清掃チェックリスト
・冷蔵庫、保管庫内の整理
・換気扇やフィルターの掃除
・食器洗浄機の洗浄・消毒
・床の細かい部分や壁の拭き掃除
月次清掃チェックリスト
・天井や照明の清掃
・エアコンや換気設備の点検・清掃
・冷凍庫や冷蔵庫の内部の清掃
・隅や高い場所の掃除
清掃計画の確認と改善
清掃計画を作成した後、スタッフとの確認を行い、理解を深めることが大切です。
定期的に清掃計画の効果を見直し、必要に応じて改善を加えます。
スタッフからフィードバックを受け取り、実際の作業に合わせた柔軟な対応が求められます。
また、清掃状況を記録することで、計画が実行されているかどうかを確認できます。
例えば、清掃後にサインをもらう仕組みを作り、後から確認できるようにします。
計画的な清掃が衛生管理を強化
清掃計画をしっかりと作成し、定期的に実行することで、パン屋の衛生状態を高水準で維持することができます。
計画を立てることによって、日常的な清掃作業が組織的に行われ、店舗全体が常に清潔で衛生的な環境を保つことが可能になります。
スタッフの協力と、計画的な清掃活動を実施することで、パン屋の品質と安全性を守り、お客様に安心して利用していただける店舗を運営することができます。
書類の整備

パン屋を開業する際、保健所や行政機関から求められる書類や記録を適切に整備することは、法令遵守と衛生管理を強化するために非常に重要です。
清掃計画やスタッフの衛生管理状況を記録に残すことは、後々のトラブル防止や、保健所の検査においても重要な役割を果たします。
書類整備の目的と重要性
法令遵守の証明
書類を整備することで、店舗が衛生管理を守っている証明となり、行政機関や保健所の指導がスムーズに進みます。
特に、衛生管理や清掃記録、食品取り扱いの記録は、適切に残しておくことで、後々のチェックや検査で証拠として活用できます。
衛生管理の確実な実施
日々の衛生管理の記録を残すことで、清掃や消毒、手洗い、手袋の使用など、スタッフの行動が標準化され、一貫して実施されていることを証明できます。
また、記録をもとに改善点を見つけることも可能です。
問題発生時の対応
食品に関する問題が発生した場合、記録が整備されていれば、原因を追求する際の証拠として役立ちます。例えば、異物混入や衛生状態の不良が発覚した場合、いつ、どのスタッフがどのような衛生管理を行っていたかを調べることで、早期に問題を特定できます。
整備すべき主な書類
営業許可証・各種届出書
営業許可証:パン屋を開業するために必要な営業許可証は、必ず保管しておく必要があります。この許可証は店舗内で見やすい場所に掲示しておくことが求められます。
届出書類:食品衛生法に基づいて、保健所に提出する届出書類や、必要な衛生管理計画書なども整理して保管します。
清掃記録・衛生管理記録
清掃記録:清掃計画に基づいた日々の清掃活動を記録します。スタッフが実施した清掃作業について、日付と担当者を記載し、チェックリストに沿って行ったことを記録として残します。これにより、清掃が適切に行われているかを後から確認できます。
衛生管理記録:衛生管理に関連する記録として、手洗いの実施、手袋の使用、消毒液の使用状況などを記録します。定期的にチェックリストを使ってスタッフが衛生管理の徹底を確認できるようにします。
スタッフの衛生教育・健康管理記録
衛生教育の記録:スタッフが衛生管理についての教育を受けたことを記録するため、定期的に行われる衛生研修や、衛生教育の受講証明書を保管しておきます。これにより、スタッフ全員が最新の衛生基準を理解し実行していることを証明できます。
健康診断記録:定期的にスタッフの健康診断を受けることが義務付けられている場合、特に食品を取り扱うスタッフに対しては、健康診断の結果を整備しておきます。病歴や感染症の有無、食中毒のリスクがないかの確認が行われていることを記録に残します。
食品の取り扱い記録
食材の入荷・保管記録:食材の仕入れ日や保管場所、保存方法を記録します。食材のロット番号や消費期限も記録として残し、必要に応じて追跡できるようにしておきます。
温度管理記録:冷蔵庫や冷凍庫の温度管理を行っている場合、その温度記録を毎日記録し、適切な温度で保管されていることを確認します。これにより、食材が安全に保管されていることを証明できます。
消毒・除菌記録
消毒・除菌作業記録:調理器具や作業台の消毒・除菌作業も記録として残しておきます。消毒を実施した日付や使用した消毒薬、担当者名などを記入します。この記録があれば、衛生管理が徹底されていることを示す証拠になります。
害虫・害獣対策記録
害虫駆除・害獣対策の実施記録:害虫や害獣の監視、駆除作業を行った記録も残します。定期的に害虫駆除業者に依頼している場合、その作業内容や実施日なども記録しておくことが必要です。
書類の保管方法
整理整頓された保管場所
書類はきちんと整理して、保管場所を決めておくことが重要です。
一般的には、ファイルキャビネットやロッカーなどで保管し、すぐに取り出せるように整理します。
保管場所は清潔で、湿気や直射日光が当たらない場所が理想です。
デジタル化の活用
近年では、紙の書類をデジタル化して管理することも増えています。
スキャンしてPDFファイルとして保管し、PCやクラウド上で管理することで、書類の劣化を防ぎ、アクセスも簡単になります。
デジタルデータにはセキュリティ対策を施し、適切に管理することが求められます。
定期的な見直しと更新
書類は一度作成して終わりではなく、定期的に見直しと更新が必要です。
例えば、スタッフの健康診断結果や衛生教育記録は定期的に更新し、古い情報を更新する必要があります。
また、書類が期限を迎えた場合は適切に処分し、最新の状態に保つことが求められます。
書類管理で信頼性と衛生管理を強化
パン屋において、書類の整備は法令遵守と衛生管理の強化に欠かせません。
しっかりとした記録を残すことで、店舗の衛生状況が常に確認でき、問題が発生した際の対応が迅速に行えます。
また、保健所の検査や行政機関の指導にも、整備された書類が信頼性を高める材料となります。
書類整備は面倒に思えるかもしれませんが、長期的に見れば店舗運営の基盤を支える重要な要素です。
整理整頓された書類を活用して、清潔で安全なパン屋の運営を行いましょう。
まとめ
パン屋の開業は、多くの方にとって夢の実現に向けた大きな一歩です。
しかし、保健所対策を後回しにしてしまうと、営業許可が下りずに開業が遅れてしまう可能性もあります。
設備や衛生面の基準を事前にしっかり確認し、必要な準備を整えることが、スムーズな開業とその後の安定した営業につながります。
大切なのは、ポイントを丁寧に押さえながら、誰もが安心して利用できる清潔で安全なパン屋づくりを目指すことです。
夢のスタートを成功させるためにも、保健所対策は計画的に取り組んでいきましょう。
テンポスでは開業に関するさまざまな情報を発信しています。
どうぞご参考になさってください。
#パン屋 #開業 #保健所対策 #開業を成功させる


























