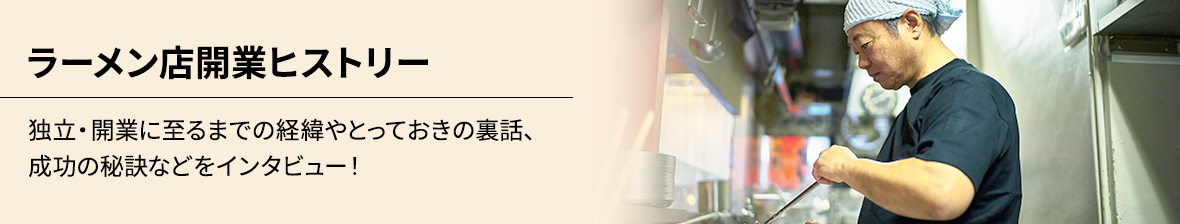一見どれも同じように見える業務用炊飯器ですが、実は「お店の業態」によって最適なタイプはまったく異なります。
白米を大量に炊いて提供する居酒屋と、ライスをサイドメニューとして少量出すラーメン店、玄米や炊き込みご飯を扱うカフェでは、必要とする容量・機能・スピードが違うのです。
この記事では、和食居酒屋・ラーメン店・カフェごはん店の3業態を例に、それぞれに合う炊飯器のタイプと、導入後の運用ポイント・実際によくある成功と失敗を紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。
また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!
目次
■ 和食居酒屋:大量炊飯と長時間保温がカギ

◎ 一度に炊く量とスピードが勝負
和食居酒屋では、ディナータイムのピークに合わせて一気に大量のご飯を炊き上げる必要があります。
炊き上がりのスピードと安定した品質を両立するには、ガス式の大容量炊飯器(3〜5升炊き)が最もおすすめです。
ガスなら火力が強く、短時間でムラなく炊けるため、ふっくら粒立ちの良いご飯を安定して提供できます。
また、炊飯中の熱効率が高いガス式は、白米を中心に出す居酒屋のような店舗で特に重宝します。
電気式でも対応は可能ですが、炊飯時間が長くなりやすく、ピーク時の対応が遅れるリスクがあるため、スピードを重視するならガス式が有利です。
◎ 保温機能と風味維持の工夫
営業中は炊いたご飯を長時間保温することが多いため、保温性能の高さも重要なポイントです。
ガス炊飯器でも保温機能付きタイプを選ぶか、専用の保温ジャーを併用すると、味や香りの劣化を防げます。
長時間保温ではご飯の乾燥や黄ばみが問題になりますが、保温中に軽く撹拌することでムラを抑えられます。
また、保温ジャーを2台用意し、「炊きたて」と「保温済み」で区分して使うと、ピーク時の提供もスムーズです。
◎ 日々の清掃で炊き上がりを保つ
営業終了後の釜の手入れは、翌日の炊き上がりを左右します。
釜底に残ったデンプン汚れは焦げやニオイの原因になるため、その日のうちに洗浄・乾燥を行いましょう。
定期的に内釜やフタのパッキンを点検することも、安定した品質を維持するコツです。
◎ よくある失敗と対策
和食居酒屋でありがちな失敗は、「電気炊飯器で大量炊きをして時間が間に合わなかった」ケースです。
また、保温しすぎて後半のご飯の風味が落ちることもよくあります。
これらを防ぐには、炊飯器+保温ジャーの2台体制が理想です。
炊くスピードと保温品質を分担させることで、常に美味しいご飯を提供できる体制が整います。
和食居酒屋における炊飯器選びは、「量」「スピード」「保温性」の3要素が鍵です。
ガス式の火力と専用ジャーを上手に組み合わせることで、どの時間帯でも安定した炊き上がりを実現できます。
RR-300C リンナイ ガス炊飯器3升 2.0~6.0L 都市ガス/プロパンガス 幅492×奥行423×高さ426(mm)【業務用/新品/送料無料】

■ ラーメン店:スピード重視&コンパクトが正解

◎ サイドメニュー向けは“小回りのきく炊飯器”を
ラーメン店では、ご飯はメイン料理ではなく、チャーシュー丼や餃子セットなどのサイドメニュー用として提供されることがほとんどです。
そのため、炊飯量は多くなく、1〜1.8升炊き程度の小型電気炊飯器が最適です。
電気式なら設置場所の自由度が高く、コンセントがあればどこでも使用できます。
さらに、火を使わないため安全性が高く、狭い厨房でも安心して導入できます。
卓上やカウンター下に置けるコンパクトモデルを選べば、限られたスペースを有効活用できるでしょう。
◎ 重要なのは“スピード”と“扱いやすさ”
ラーメン店では、注文から提供までのスピードが命です。
炊飯器も、短時間で安定した炊き上がりができるものを選ぶのがポイントです。
IH加熱タイプの電気炊飯器は、火力が強くムラが少ないため、忙しい時間帯でも炊きたてを提供しやすくなります。
また、炊飯量が少ない分、保温機能より炊飯スピードと清掃のしやすさを重視すると良いでしょう。
特に深夜営業や連続営業を行う店舗では、炊飯サイクルを短くし、常に新しいご飯を提供するほうが、味と香りの維持につながります。
◎ 設置環境とメンテナンスも意識
ラーメン店の厨房は熱気や湯気がこもりやすいため、炊飯器を置く場所にも注意が必要です。
蒸気が逃げにくい位置に設置すると、炊飯器の内部に結露が発生し、故障や衛生トラブルの原因になることがあります。
換気扇や排気ダクトの近くに設置し、蒸気を効率的に逃がすレイアウトを意識しましょう。
使用後は、釜やフタをしっかり乾燥させておくことも大切です。
特にフタ裏のパッキン部分は汚れが残りやすいため、こまめな清掃が必要です。
◎ 成功事例と失敗例
あるラーメン店では、電気式の1升炊き炊飯器を採用したことで、お昼のピーク時でも常に炊きたてご飯を提供できるようになり、定食メニューの売上が20%アップしたそうです。
一方で、容量を抑えすぎた店舗では、「途中でご飯が切れてしまい、再炊飯に時間がかかった」という失敗もあります。
このようなトラブルを防ぐには、「一度の炊飯で何人前を出すか」をあらかじめ計算しておくことが重要です。
必要に応じて、小型炊飯器を2台設置する“分散炊飯”も効果的です。
ラーメン店における炊飯器選びは、「スピード」「扱いやすさ」「設置の自由度」がカギです。
電気式の小型モデルを上手に運用すれば、省スペースかつ効率的に、美味しいご飯を提供し続けることができます。
【セット商品】JCC-270P【タイガー】炊飯ジャー 1升5合炊き +しゃもじM +しゃもじ入れ

■ カフェごはん店:多彩なメニュー対応力がポイント

◎炊飯器も「メニューの一部」として考える
カフェごはん店では、白米だけでなく、玄米・雑穀米・炊き込みご飯・リゾット風メニューなど、バリエーション豊かなご飯メニューを提供するケースが多いです。
そのため、炊飯器は“ご飯を炊く道具”というより、“メニューづくりの一部”として考えることが大切です。
調理の自由度を高めるには、温度や圧力を細かく調整できる高機能モデルが適しています。
◎多機能モデルが強い味方に
カフェ業態におすすめなのは、圧力IHタイプやスチーム機能付きの電気炊飯器です。
圧力IHは、もちもち感のある白米や、しっかりとした玄米の炊き上がりが得意。
スチーム機能付きなら、時間が経ってもふっくら感をキープできるため、ランチピークを越えてもクオリティを保てます。
特に「予約炊飯」「保温時の湿度制御」などの細かな設定ができるモデルは、仕込みや営業時間のリズムに合わせやすく便利です。
◎サイズよりも「調理の柔軟性」で選ぶ
一般的にカフェでは炊飯量が中規模(3〜5升)で済むことが多いですが、複数の品種を同時に炊くことが多いため、1台の大容量モデルよりも、小型炊飯器を2台使い分ける方法も効果的です。
たとえば、白米用と玄米・炊き込み用で分けることで、味のブレや香り移りを防ぎ、メニューごとの最適な仕上がりを追求できます。
◎実際の店舗事例:調理の幅が広がった成功パターン
あるカフェでは、従来のシンプルな電気炊飯器から圧力IHタイプに切り替えたところ、「玄米メニューの注文率が2倍に増えた」といいます。
お客様から「お米がおいしくなった」「食感が全然違う」といった声が増え、炊飯器のグレードアップがブランディングにもつながりました。
◎まとめ:カフェの個性は炊飯器でつくれる
カフェごはん店における炊飯器選びは、単なる効率化ではなく「お店の世界観を支える要素」として重要です。
炊き分け機能や多段階設定ができるモデルを選ぶことで、メニューの幅を広げながら品質を安定させることができます。
炊飯器の機能をうまく活かすことが、“料理の表現力”を高める近道です。
SR-STS18VC-W【パナソニック】スチームIHジャー炊飯器 幅292×奥行365×高さ267(mm)【業務用/新品】【送料無料】

■ まとめ:炊飯器選びは“店のオペレーション設計”の一部
◎炊飯器は「厨房オペレーションの要」
炊飯器は単なる調理機器ではなく、飲食店のオペレーション効率と提供品質を左右する“要”の存在です。
どれだけおいしい料理を作れても、ご飯の炊き上がりが不安定だったり、ピーク時に間に合わなかったりすれば、全体の流れが崩れてしまいます。
つまり、炊飯器選びは“味”と“回転率”の両立を支える、経営判断の一部なのです。
◎業態ごとに「最適解」は違う
和食居酒屋では「大量炊飯+長時間保温」、ラーメン店では「スピードと省スペース」、カフェごはん店では「多彩なメニュー対応力」と、求められる性能はまったく異なります。
どの炊飯器が良いかは、炊飯量や提供スピード、メニュー構成によって変わります。
自店の営業スタイルを具体的にイメージしたうえで、「1日あたりの炊飯回数」「ピーク時間」「保温時間」などを基準に選定することが重要です。
◎導入後のメンテナンス性・運用も忘れずに
炊飯器は毎日使うものだからこそ、清掃のしやすさや耐久性、パーツ交換の容易さも見逃せません。
特にガス式はパワーがある一方で、メンテナンス性を考えると電気式に軍配が上がる場合もあります。
導入後のスタッフの扱いやすさや清掃手順まで含めて検討すると、長期的なコストパフォーマンスが高まります。
◎「現場目線」での選定が失敗を防ぐ
カタログスペックだけで判断せず、実際に厨房での動線や作業リズムに合っているかを確認することが大切です。
炊飯タイミングを仕込み作業と並行できるか、盛り付け導線を妨げない位置に置けるかなど、オペレーションの中に組み込んで考えると、導入後の“使いにくさ”を防げます。
◎炊飯器選びは「戦略的な設備投資」
結局のところ、炊飯器は厨房機器の中でも投資効果が非常に高いカテゴリーです。
適切なタイプを選べば、提供品質の安定、スタッフの負担軽減、ロス削減につながります。
つまり、炊飯器選びは単なる機器購入ではなく、“店の生産性を上げる戦略的な投資”と言えるのです。
店舗の成長を見据えたうえで、長期的に運用できる1台を選ぶことが、繁盛店づくりの第一歩になります。

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。
テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。
是非ご活用ください。
業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。
是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
#飲食店 #厨房 #炊飯器 #オペレーション #最適解 #メンテナンス性 #現場目線 #戦略的設備投資 #サイズ #炊飯タイプ #スペース